うへ、これは重いですね。僕自身も思い当たる節が大いにあります(汗)。でも、、、「論理の違い」というのはどこにでも避けがたく存在するわけで、それ自体は別に悪いことじゃないし、どっちが良いとか悪いということじゃないと思います。各々に必然性と必要性があると思っています。そこで、「本部の論理」が往々にして「虫の目」に無関心なのは全くをもってそのとおりなんですが、それが常に間違っているかというとそうともいえない。というか「神の目」であればこそ見えてくるものがやはりある(と思いたい)。逆に「虫の目」が常に生きられる世界に注がれているとしても、その眼に常に曇りがないかといえばそうともいえない。問題は、これまで互いの論理の「摺り合わせ」が十分に行われてこなかった、あるいはそれを補完するシステムが未整備だったということなんじゃないでしょうか。論理の違いなんてものは、都市と農村、地域と国家、国家と世界まで広げなくても、石川さんがいうような、それこそ一町内にだってあるわけで、一住民と自治会長さんの立場、見方ってのはやはり違うでしょう。ただ、石川さんがいうように、「本部の論理」(というか広域の論理)というのは、常に権力とか権威と表裏一体なところがあって、行使の仕方を誤るとまずいことになるというのはそのとおりですよね。
最新の画像[もっと見る]
-
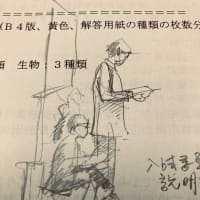 説明を聞く
1年前
説明を聞く
1年前
-
 千駄堀付近の軽車道
1年前
千駄堀付近の軽車道
1年前
-
 戸定が丘の仕事場
1年前
戸定が丘の仕事場
1年前
-
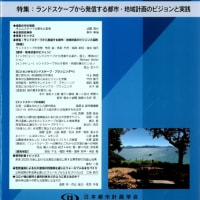 英国におけるグリーンインフラ・プランニング:イングランドのケーススタディ
3年前
英国におけるグリーンインフラ・プランニング:イングランドのケーススタディ
3年前
-
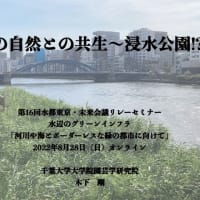 川の自然との共生:浸水公園!?
3年前
川の自然との共生:浸水公園!?
3年前
-
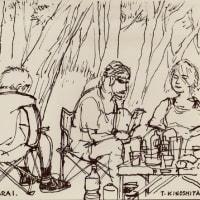 大洗キャンプ場にて At the Oarai Campsite
3年前
大洗キャンプ場にて At the Oarai Campsite
3年前
-
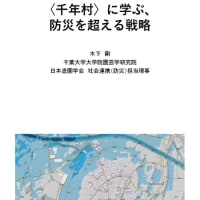 〈千年村〉に学ぶ、防災を超える戦略
3年前
〈千年村〉に学ぶ、防災を超える戦略
3年前
-
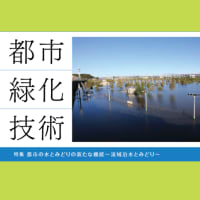 流域治水と都市公園〜グリーンインフラの視点からのアプローチ
3年前
流域治水と都市公園〜グリーンインフラの視点からのアプローチ
3年前
-
 Nature journaling and sketch session presented by Rain Gardeners' Club
3年前
Nature journaling and sketch session presented by Rain Gardeners' Club
3年前
-
 Nature journaling and sketch session presented by Rain Gardeners' Club
3年前
Nature journaling and sketch session presented by Rain Gardeners' Club
3年前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます