東浩紀、北田暁大によるスリリングな対談記録(NHKブックス1074,2007)。ネタ満載。地域の個性とか場所性とか言いつつ、ラ系も彼らが言うところの「ジャスコ的な」まちづくりに荷担してきたのではないかという疑念が浮かび上がる。メディア論、社会学的な概念を多用しながらも、彼らが常にアーキテクチャやランドスケープの実態を念頭に置いて議論を進めているのでわかりやすい。六本木ヒルズも、恵比寿ガーデンプレイスも、あの手の再開発はみんな「ジャスコ的」と烙印を押し、都心の「郊外化」を指摘する。そしてこうした「郊外化」を免れている数少ない地域として青葉台や成城等のコミュニティ意識の強い住宅地をあげるが、それとて企業によってねつ造された強固な物語性に支えられた広告都市、シミュラークル・シティにほかならないとバッサリ。後ほどまたゆっくりレビューしたいと思います。
最新の画像[もっと見る]
-
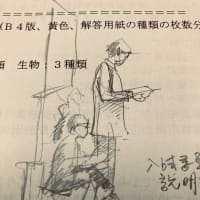 説明を聞く
2年前
説明を聞く
2年前
-
 千駄堀付近の軽車道
2年前
千駄堀付近の軽車道
2年前
-
 戸定が丘の仕事場
2年前
戸定が丘の仕事場
2年前
-
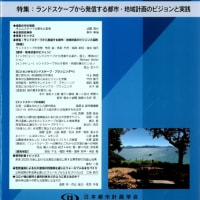 英国におけるグリーンインフラ・プランニング:イングランドのケーススタディ
3年前
英国におけるグリーンインフラ・プランニング:イングランドのケーススタディ
3年前
-
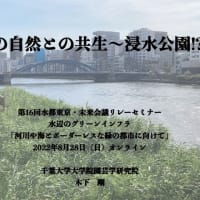 川の自然との共生:浸水公園!?
3年前
川の自然との共生:浸水公園!?
3年前
-
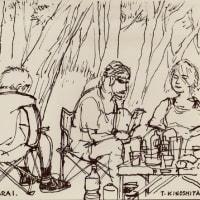 大洗キャンプ場にて At the Oarai Campsite
3年前
大洗キャンプ場にて At the Oarai Campsite
3年前
-
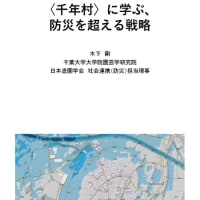 〈千年村〉に学ぶ、防災を超える戦略
3年前
〈千年村〉に学ぶ、防災を超える戦略
3年前
-
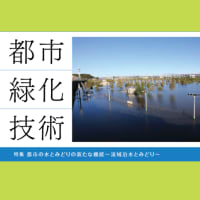 流域治水と都市公園〜グリーンインフラの視点からのアプローチ
3年前
流域治水と都市公園〜グリーンインフラの視点からのアプローチ
3年前
-
 Nature journaling and sketch session presented by Rain Gardeners' Club
3年前
Nature journaling and sketch session presented by Rain Gardeners' Club
3年前
-
 Nature journaling and sketch session presented by Rain Gardeners' Club
3年前
Nature journaling and sketch session presented by Rain Gardeners' Club
3年前










まだ怖くて読んでないので憶断でごめんなさい。
でも昔澁澤栄一がつくった田園調布とか大岡山とか(あと講義できいたはずなのに忘れました)、物質的なというか、近くを散歩すると人が生きている力強い感じを受けたんですが、ここも浸食された郊外なんでしょうかねえ。
物語なしに人は生きられないって思うんですが、どうでしょう。その物語の一部をつくってくのが建築とか造園とかいう設計計画屋さんだと。
それはそれとして、おっしゃるとおりただの物語にどれだけ本気で、リアリティをもたせられるかに賭けたいですよね。仕事してるとそこが一番憂鬱になるとこですが。いろんな折衝とかで。
物語性って、曖昧だけど場所固有性だと思います。まあそれは学部の計画設計演習のコンセプトになるくらいあたりまえなんだろうけど。
でもそれがどの範囲の人を対象にするかってとこと、どの文化を対象にするかなんじゃないかなあって思います。「場所」の言葉通りですが。
対象範囲を、いまは自己責任とかいってるし個人に属するとしてしまうと、それはそうなんだけど、建築・造園設計、少なくとも計画の範疇じゃなくなってしまう(って設計と計画を過小評価し過ぎか)。小説読んだり、音楽きいたり、映画みたり、絵画とか彫刻で感じとけって。
ハーバーマスとかはあまりよんでませんが、彼らの言う公共圏より狭く、人口や密度や総生産高的には今でいう昔の谷戸とか里山とかの範囲内、それも生物全体を対象にするわけではなく、人間のエコロジー(エコノミー)が存在する程度、ちょっと前でいう回覧板がまわり町内会長がいる地区程度が、場所固有性の範囲じゃないかなあと。いまは回覧板なんてないのかもしれませんが(ちなみに僕の住んでいた葵区ではきちんと廻ってます)。まさか高級(?)高層マンションに住む人がまわしてるとは思えませんが、回覧板で地域の情報を交換しているところってどのくらいあるんでしょうか。五人組からはじまる日本独自の文化(?)なはずだと。ああ、日本の話しをすると場所と文化がごっちゃになってしまう。
その意味だと、ジャスコ的なもの(なんかジャスコを標的にしてるみたいなので、イオンとかでもいいけれども)ってのは、生産とかロジスティックとか販売を、品物を手に取って買うっていうちょっと昔の場所固有性のシステムを模倣しながら、距離とか時間を劇的に短縮してますよね。(通販は、大昔の呉服屋かなんかの、閉架式販売に似てます)。確かに時間距離に依存しなくなるシステムを作っている。恵方巻を広めたのはセブンイレブンでした。(1999以降)。
同時に、立地条件はというと、郊外的ロードサイド駐車場巨大大規模店のほかにも、東京山手線西側付近に駐車場なしビル型店舗も出店している。(←ドンキと一緒にしちゃってるかもしれません)
ってことは、時間距離に依存せず、すぐに結果の出る「昔ながらの立地的なイメージ」「富裕層の多く住むところの立地することによるイメージ」を取り込みたいのかなあっていう当たり前の戦略も感じます。商品展開は、濃淡あれほとんど一緒なはずなのに。物語で差異化し、実際の商品は均一化っていう。
仕事してて、景観法の単純な未来を見る気がします。色彩+表面の意匠統一+高さ制限っていう。ブルシット!!
打開策をうてないぼくは...!
じつは東京はでっかい郊外なのかもって思ってきました。やっぱり天皇が長年いた京都がリアル都市なのかもって。
ちゃんとこの本読んでみます。
そして、実動部隊の僕らコンサルが企画書つくって自治体に売り込まねば。いや、ちょっとちがうかな。
うは、ながい。