今年は「更科日記」1000周年
今からちょうど1000年前、ある旅の一行が習志野市内を西に向って通り過ぎて行きました。上総(かずさ)国の国司(上総介)を務めた菅原孝標(すがわらのたかすえ、菅原道真(みちざね)の曽孫の子)が、任期を終えて京都に戻る姿でした。孝標の娘(名前は伝わっていません。孝標女(たかすえのむすめ)と呼ばれています)が日記体の回想録『更級日記』の中に、京都まで3ヶ月ほどの旅の様子を記しています。

菅原孝標の女(むすめ)、市原に現る!
https://www.city.ichihara.chiba.jp/maibun/sarasina2/profile2.htm
(市原市五井駅前の菅原孝標の女像)

「石山寺縁起絵巻」に描かれた、菅原孝標女のまどろんだ姿
市原市が「更科日記」の出発点
寛仁(かんにん)4年(1020)、彼女は数え13歳でした。上総国府(現在の市原市)から下総(しもうさ)国を通って武蔵国に入る足取りを『更級日記』から抜き出してみましょう。
旧暦9月3日、門出の儀式をして「いまたち」という所へ移動します。15日には下総国に入り、「いかだ」という所に泊まっています。続く17日の早朝、「いかだ」を出発し「深き河を舟にて渡る。」とあります。また、その夜は「くろとの浜」という所に泊まっています。翌朝早く、そこを出発。この日は下総国と武蔵(むさし)国の境にある「太井川」の上流、「松里の渡し」の船着場に泊まって、一晩中、船で荷物を対岸に渡したとあります。
この行程の中で現在の習志野市域を通過しているはずなのですが、ここに出てくる地名が現在のどこなのか、昔から諸説言われています。いくつか紹介すると、
*「いまたて」については、市原市馬立という説と、現在のJR八幡宿駅付近と考える説があります。
*「いかだ」は「いけだ」と考えられ、池田郷、すなわち現在の千葉市中央区寒川町あたりとされます。また、「深き河」は千葉市の都(みやこ)川であろうとされています。
*「くろとの浜」は千葉市の黒砂海岸とされます、しかしこれでは、宿泊するには出発した池田郷から近すぎるではないかという批判があり、批判説は「くろとの浜」を船橋市大神宮下とすることが多いようです。なお、孝標女は「くろとの浜」の情景を「片つかたはひろ山なる所のすなごはるばると白きに松原茂りて月いみじうあかきに、風のおともいみじう心細し」(片方は広い山になっている所の、はるか向こうまで砂浜が白く広がっている。松原が茂って、月がたいそう明るく、風の音もひどく心細い)と書いています。
(くろとの浜=船橋市大神宮下説)
http://sarasina.jp/products/detail46.html
*「松里の渡し」は、現在の松戸と考える説と市川市国府台付近と考える説があります。
どれが正しいかを推理する前に、この時代の街道がどうなっていたのかを考えてみることにしましょう。
昔は、下総(千葉県北部)より上総(千葉県中西部)の方が京に近かった?
国の名前は都(京都)に近い方から「上・下」(上野・下野)、「前・中・後」(例えば越前・越中・越後)となるはずなのに、房総半島は下総、上総、安房の順番になっています。これは変だと思いませんか。
実は古代の東海道は、相模(さがみ)国(神奈川県)から海路(今で言うアクアライン)、上総国に出て北上、下総国から常陸(ひたち)国(茨城県)へと続いており、武蔵国(東京都)は東海道ではありませんでした。三浦半島から海上を富津へ渡り、上総国府(市原市)から成田周辺を経て利根川を渡り、常陸国府(石岡市)に至るのが東海道だったのです。これであれば、上総、下総の順番になりますね。
武蔵国が東山道から東海道に編入されたのは、宝亀(ほうき)2年(771)のことだったといいます。この頃から、京都から相模国に下ってきた後、武蔵国へ出て下総国府(市川市)から上総国府を目指すルートが整備されます。ちょうど現代の、東海道線を東京駅で降りて、総武線、内房線に乗り換えるのと同じですね。
千葉県の下総、上総ってなんで逆?
古代、「駅」が30里ごとに置かれ、馬・食糧を提供した
また駅制と言って、各国の国府を結ぶ幹線道路には約30里(16km)ごとに駅を置き各駅には馬を備えて、緊急の通信にあてました。「続日本紀(しょくにほんぎ)」という記録には、神護景雲(じんごけいうん)2年(768)、この新ルート上にあった下総国井上(いかみ)、浮島、河曲(かわわ)の3つの駅は、交通も多くなったので、それぞれの駅に5頭配置してあった馬を10頭に増やすことにしたと書かれています。この井上駅は市川市国府台あたり、浮島駅は幕張周辺、また河曲駅は千葉市新宿あたりと考えられています。
大化の改新でこのような国の制度、道や駅の制度ができたものの、平安時代も延喜(えんぎ)の頃(900年前後)になるとうまく機能しなくなってきたとされています。孝標一行が旅をした寛仁4年はさらにその120年後になりますが、しかし「いかだ」から武蔵国に至る幹線道路はまだ残っていたと考えるのが妥当ではないでしょうか。そして、「いかだ」が河曲駅あたり、「松里の渡し」が井上駅周辺。そう考えると、「くろとの浜」と浮島駅の関係が問題になってきます。
「浮島」は習志野市津田沼・鷺沼付近
それでは浮島駅が現在のどこなのか。これも昔から幕張はじめ諸説あるのですが、『千葉県の歴史 通史編 古代2』(平成13年、千葉県発行)はズバリ、浮島駅は習志野市津田沼・鷺沼付近、と推定しています。
これについて「広報習志野」の平成15年2月1日号「新ならしの散策」No.61「鷺沼・津田沼付近に東海道の駅があった!?」は、次のように記しています。
…さらに心強いのは、角川書店版『日本地名大辞典』の千葉県版に「最初幕張説を主張した吉田東伍も『大日本読史地図』で鷺沼の西の谷(やつ)に浮島駅を置いた」と記述があることです。そして千葉県史も現在、浮島駅は鷺沼・津田沼付近と推定しています。
https://www.city.narashino.lg.jp/smph/citysales/shizen/walk/sansaku/h15/sansaku061.html
https://www.city.narashino.lg.jp/smph/citysales/shizen/walk/sansaku/h15/sansaku062.html
吉田東伍博士(1864~1918)は地名学の泰斗、独力で『大日本地名辞書』11巻(明治33年)を編纂したことで知られています。その『大日本地名辞書』の中では、浮島駅は幕張と推定されています。しかし、博士の死後、昭和10年に出版された『大日本読史地図』ではご覧のように、浮島は現在の習志野市谷津あたり、また黒戸浜は千葉市黒砂海岸と書かれています。こうした先行研究を受けて『千葉県の歴史』も習志野市内と考えているのでしょう。
それらしき遺跡が発見されていない現在、いずれの説も決定打に欠けると言えますが、 上にも述べたように、古代の駅というものは原則として等距離に置かれていたということを忘れるべきではないでしょう。市川市の国府台(こうのだい:井上駅)から千葉市新宿(河曲駅)まで、現代の国道14号線でおよそ28kmです。浮島駅はその中間点にあったはずですが、市川からも千葉からも等距離になる地点は習志野市津田沼になることは指摘しておいてよいことでしょう。
東京湾を臨(のぞ)んで詠(うた)った「くろとの浜の 秋の夜の月」
最後に、『更級日記』の「くろとの浜」の場面には次のような和歌が記されています。「くろとの浜」が黒砂海岸であれ船橋大神宮であれ、また浮島駅が幕張であれ谷津や津田沼であれ、これがちょうど今から1000年前の東京湾岸の風景であることには間違いがないのです。
まどろまじ こよひならでは いつか見む くろとの浜の 秋の夜の月
(今夜は一睡もしないことにしましょう。だって今夜をおいて、いつ見るのです。くろとの浜の秋の夜の月を。)
*『更級日記』の現代語訳は、左大臣どっとこむ
https://koten.kaisetsuvoice.com/SarashinaNikki/Sara02.html
のものを引用しました。(ニート太公望)
コメントをお寄せください。
<パソコンの場合>
このブログの右下「コメント」をクリック⇒「コメントを投稿する」をクリック⇒名前(ニックネームでも可)、タイトル、コメントを入力し、下に表示された4桁の数字を下の枠に入力⇒「コメントを投稿する」をクリック
<スマホの場合>
このブログの下の方「コメントする」を押す⇒名前(ニックネームでも可)、コメントを入力⇒「私はロボットではありません」の左の四角を押す⇒表示された項目に該当する画像を選択し、右下の「確認」を押す⇒「投稿する」を押す










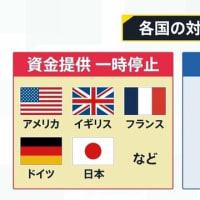


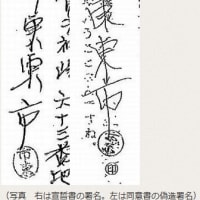
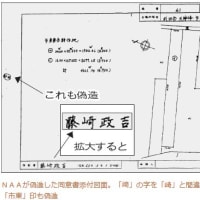




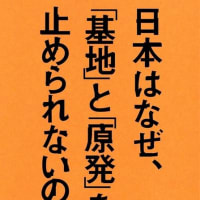





「更科日記」に習志野が登場するなんて、時空を超えて、一緒に旅をしているようです。
お勉強の古典が、身近な、生きたものになります。
ありがとうございます。