| 霧の塔の殺人 | ||
|---|---|---|
 |
読了日 | 2016/08/18 |
| 著 者 | 大村友貴美 | |
| 出版社 | 角川書店 | |
| 形 態 | 文庫 | |
| ページ数 | 471 | |
| 発行日 | 2011/09/25 | |
| ISBN | 978-4-04-394473-6 | |
 刻にいすみ市刈谷の女性からのハガキが届き、兄上のT.Y.氏の訃報だった。T.Y.氏は高校の時の同窓生で、今年4月に入院するまで、ユナイテッド航空で現役で働いており、近年は年賀状のみの付き合いだったが、毎年の賀状でお互いの元気なことを確かめあっていた。
刻にいすみ市刈谷の女性からのハガキが届き、兄上のT.Y.氏の訃報だった。T.Y.氏は高校の時の同窓生で、今年4月に入院するまで、ユナイテッド航空で現役で働いており、近年は年賀状のみの付き合いだったが、毎年の賀状でお互いの元気なことを確かめあっていた。
4月に皮膚癌で虎の門病院に入院したが、すでに手遅れの状態だったらしく、7月18日に他界したという。
千葉県立大多喜高校を昭和33年に卒業したことから、大高33回と名付けたクラス会を毎年行っているが、彼は世界を飛び回るような仕事柄か、初期の会合に出た切りその後は顔を見せることがなくなっていた。
我々の年代になると、毎年のように少しずつ物故者が増えて寂しい限りだが、これも自然のなせる業では仕方のないことだ。妹さんには早速失礼とは思ったが、電話でお悔やみを申し上げた。

巻末の西上心太氏の解説に「殺人シリーズ」3作目という紹介があるが、ミステリーには不可欠といえるほどの殺人だから、ほとんどのミステリーには出てくる現象を、シリーズ名にするにはちょっとおかしな具合だ。
しかし、横溝正史賞(現在は横溝正史ミステリ大賞と名称が変わっている)を受賞したデビュー作「首挽村の殺人」、その後の「死墓島の殺人」、そして本書「霧の島の殺人」と続いたタイトルからのシリーズ名だ。前述のように一般的に多くのミステリーには殺人事件はつきものだから、殺人シリーズという呼び方に僕はおかしさを感じたのだが、1作目の「首挽村の殺人」を読んだとき僕は、横溝正史氏の岡山県を舞台にした一連の傑作ミステリーを思い起こして、いかにも賞にふさわしい作品だと思った。
今回は前2作と名刑事・藤田警部補のたたずまいが少し異なるような気がするまま読み進めたが、最終的にはやはりいつもの名刑事ぶりを見せることになって、僕としては落ち着いた気分になったのだが・・・・。

 の時代は電話だけでなく通信網が発達しており、パソコンの普及によりインターネットは、都市部のみならず地方の小さな町村までに行き届いているから、地方の田舎の事件とは言え名探偵一人の手に委ねるといったことは物語の世界にもふさわしくない。
の時代は電話だけでなく通信網が発達しており、パソコンの普及によりインターネットは、都市部のみならず地方の小さな町村までに行き届いているから、地方の田舎の事件とは言え名探偵一人の手に委ねるといったことは物語の世界にもふさわしくない。
時代の流れがミステリーの舞台にまで、変化を与えることは否めないが、しかい、この3部作はそうした環境の変化さえものともせず、辺境の地の事件を鮮やかに描く。そうした昔ながらの探偵小説の面白さを、そこここに見せていくストーリー展開に、僕はワクワクしながら読み進める。
著者は出身地の岩手県をこよなく愛していると見え、よく知った土地柄や人情の機微を物語に盛り込んで、探偵小説をものにしている。ミステリーというよりここは探偵小説といったほうがふさわしいと思っている。
前2作で事件解明に活躍した県警捜査1課の藤田警部補は、ここでも最後には名推理を披露するのだが、今度は現代的なストーリーの中での活躍を期待したいが、もうここで終わりなのか?
夏の甲子園はベストエイトによる準々決勝が今日行われて、千葉県代表として木更津総合高校が勝ち残っていたが、残念ながら作新学院に3-0で敗れた。この時期になると、暑い夏も終わりが近づいてきたことを感じる。
にほんブログ村 |













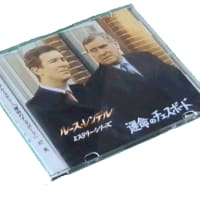

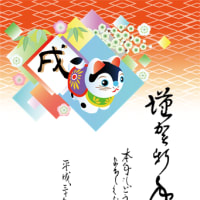





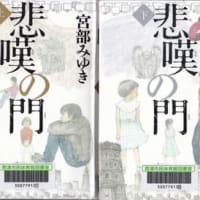
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます