
津軽三味線を習いだす頃、この本を読みました。
三味線奏者、高橋竹山の半生を軸に、仁太坊や梅田峯月など津軽三味線の名手を語りながら、その時代の青森県の情景と芸人の世界を描き出しています。
この本は昭和50~51年に執筆されており、当時まだ存命だった高橋竹山との間に交わした話や、明治から大正にかけて生きた芸人を実際に見た人の話の聞き取りは、時代の持つ雰囲気を濃厚に漂わせています。
まだ貧しかった時代に目の見えない人が生きていくためには、男はボサマ、女はイタコになるのが青森でのならいだったこの時代、真冬に着物一枚だけで門付けをして歩くのは寒さ以上に心が痛むことだったとしても、その日の食べ物にありついてその日の命を永らえるただひとつの方法だったとしても、現在では想像もできない生き方です。
口をあけると雪が入ってくるような吹雪の中を、目の見えない人が次の町を目指して歩いていく。それも今のような道路ではなく防寒着といえるものもなく。
その時代はボサマといわれる三味線弾きなどの遊芸人はさげすみの対象でした。
ほんの数年前に「津軽三味線など習うのは恥ずかしいことだ」とご主人に言われたご婦人の話を聞きました。
同じ頃、70代の方から「ちいさいころはボサマがこの辺にも来ていて、よく追いかけて石を投げたりしたナ、今思えば悪いことをした」という話も聞いています。
吉田兄弟が海外公演をこなすこの時代でも、ボサマが門付けをして歩いた時代の記憶はいまだ微かに残っている、青森とはそんな不思議なところです。
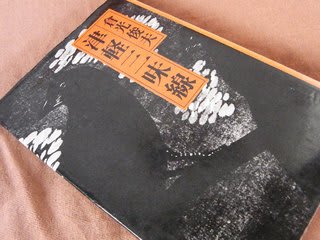
三味線奏者、高橋竹山の半生を軸に、仁太坊や梅田峯月など津軽三味線の名手を語りながら、その時代の青森県の情景と芸人の世界を描き出しています。
この本は昭和50~51年に執筆されており、当時まだ存命だった高橋竹山との間に交わした話や、明治から大正にかけて生きた芸人を実際に見た人の話の聞き取りは、時代の持つ雰囲気を濃厚に漂わせています。
まだ貧しかった時代に目の見えない人が生きていくためには、男はボサマ、女はイタコになるのが青森でのならいだったこの時代、真冬に着物一枚だけで門付けをして歩くのは寒さ以上に心が痛むことだったとしても、その日の食べ物にありついてその日の命を永らえるただひとつの方法だったとしても、現在では想像もできない生き方です。
口をあけると雪が入ってくるような吹雪の中を、目の見えない人が次の町を目指して歩いていく。それも今のような道路ではなく防寒着といえるものもなく。
その時代はボサマといわれる三味線弾きなどの遊芸人はさげすみの対象でした。
ほんの数年前に「津軽三味線など習うのは恥ずかしいことだ」とご主人に言われたご婦人の話を聞きました。
同じ頃、70代の方から「ちいさいころはボサマがこの辺にも来ていて、よく追いかけて石を投げたりしたナ、今思えば悪いことをした」という話も聞いています。
吉田兄弟が海外公演をこなすこの時代でも、ボサマが門付けをして歩いた時代の記憶はいまだ微かに残っている、青森とはそんな不思議なところです。
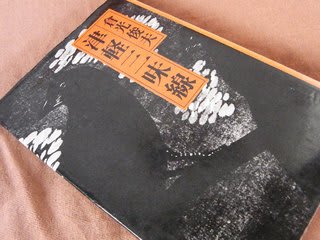
















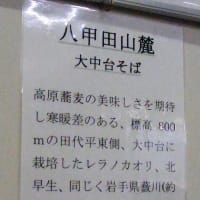



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます