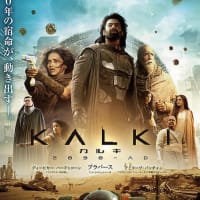※宮部みゆき(1960-)「神無月」(1993年、33歳)『日本文学100年の名作、第8巻、1984-1993』新潮社、2015年、所収
(1)
岡っ引き(親分)が黙々と飲んでいたが、ふと「神無月だ。去年の今頃、押し込みがあった」と居酒屋の親父に言った。
(2)
長屋で畳職人の男がひとり、病気の八つの娘のためにお手玉を縫っている。この子を産んで女房は命を落とした。女房の命をもらって来たこの子のために「どんな高価(タカ)い薬も買う」と男は言う。
(3)
「毎年、神無月に奇妙な押し込みがある」と岡っ引きは気づいた。八年前からだ。ところが盗られた金はいつも5両からせいぜい10両。「段取りを決めて、年中行事みたいに、きっちりこなしていく。しかも賊は一人だ。人を殺めることもない。」賊はおそらく「堅気」だ。
(4)
「当たり前の働きで稼ぐ以上の金が要る」とわかった時、男は心を決めた。「他人様に迷惑をかけたくないが、自分の子供の命がかかっているから仕方ない。去年は相手が飛びかかって来たので、刺すしかなかった。本当に危ないところだった」と男は思った。「今年は少し、大きな金を持ち帰ろう。」
(5)
「この先、何年かは危ないことをしないで済むように、賊は、今年は大金を狙うかもしれない」「無理をして危ない真似をするかもしれない」「歯止めがきかなくなり、本当に人を手にかけちまう前に、袖をとらえて引き戻してやらねえと」と岡っ引き(親分)が言った。そして「襲われた家どうしにはつながりはねえ」と言った。
(6)
黒い頭巾を懐(フトコロ)におさめ「おとっちゃんはこれから出かけてくる。夜明けまでには戻ってくる」と男は寝ている娘に話しかけた。「おめえは神無月の月末に生まれた。神様が留守にしちまう月だ。だからお前はこわれものの身体を持って生まれてきた。おっかさんも死んでしまった」と男は言った。
(6)-2
「とっちゃんは神さまに見られては困るようなことをする。だから神様が留守の神無月にするんだ」。
(7)
「賊は狙った家の造りをよく知っているから大工かと思って調べたら、大工に縁のなかった家があった。お得意先に出入りする油売り、魚屋、町医者も考えて調べたが、みな違う」と岡っ引き(親分)が言った。居酒屋の親父が「渡り職人の畳屋じゃないですか?あちこちの家に行きますよ」と言った。岡っ引き(親分)は合点がいった。「有難うよ。間に合うといいがな」とぐいと立ち上がった。
(8)
男、「たたみ職 市蔵」が年に一度のおつとめのため、夜道をいそいでいく。岡っ引きが不思議な押し込みの袖を、少しでも早くとらえるため、夜道をいそいでいく。神様は、出雲の国に去っている。
《感想》おそらくありえないが、あったらいいなと思われる「岡っ引き」像。この小説と違って、現実の「岡っ引き」は普通、権力をかさにきて弱い者にえばり散らす。そして権力にできるだけうまく取り入り生きる。人間社会は無残だ。宮部みゆき氏はユートピアの「岡っ引き」を描く。
(1)
岡っ引き(親分)が黙々と飲んでいたが、ふと「神無月だ。去年の今頃、押し込みがあった」と居酒屋の親父に言った。
(2)
長屋で畳職人の男がひとり、病気の八つの娘のためにお手玉を縫っている。この子を産んで女房は命を落とした。女房の命をもらって来たこの子のために「どんな高価(タカ)い薬も買う」と男は言う。
(3)
「毎年、神無月に奇妙な押し込みがある」と岡っ引きは気づいた。八年前からだ。ところが盗られた金はいつも5両からせいぜい10両。「段取りを決めて、年中行事みたいに、きっちりこなしていく。しかも賊は一人だ。人を殺めることもない。」賊はおそらく「堅気」だ。
(4)
「当たり前の働きで稼ぐ以上の金が要る」とわかった時、男は心を決めた。「他人様に迷惑をかけたくないが、自分の子供の命がかかっているから仕方ない。去年は相手が飛びかかって来たので、刺すしかなかった。本当に危ないところだった」と男は思った。「今年は少し、大きな金を持ち帰ろう。」
(5)
「この先、何年かは危ないことをしないで済むように、賊は、今年は大金を狙うかもしれない」「無理をして危ない真似をするかもしれない」「歯止めがきかなくなり、本当に人を手にかけちまう前に、袖をとらえて引き戻してやらねえと」と岡っ引き(親分)が言った。そして「襲われた家どうしにはつながりはねえ」と言った。
(6)
黒い頭巾を懐(フトコロ)におさめ「おとっちゃんはこれから出かけてくる。夜明けまでには戻ってくる」と男は寝ている娘に話しかけた。「おめえは神無月の月末に生まれた。神様が留守にしちまう月だ。だからお前はこわれものの身体を持って生まれてきた。おっかさんも死んでしまった」と男は言った。
(6)-2
「とっちゃんは神さまに見られては困るようなことをする。だから神様が留守の神無月にするんだ」。
(7)
「賊は狙った家の造りをよく知っているから大工かと思って調べたら、大工に縁のなかった家があった。お得意先に出入りする油売り、魚屋、町医者も考えて調べたが、みな違う」と岡っ引き(親分)が言った。居酒屋の親父が「渡り職人の畳屋じゃないですか?あちこちの家に行きますよ」と言った。岡っ引き(親分)は合点がいった。「有難うよ。間に合うといいがな」とぐいと立ち上がった。
(8)
男、「たたみ職 市蔵」が年に一度のおつとめのため、夜道をいそいでいく。岡っ引きが不思議な押し込みの袖を、少しでも早くとらえるため、夜道をいそいでいく。神様は、出雲の国に去っている。
《感想》おそらくありえないが、あったらいいなと思われる「岡っ引き」像。この小説と違って、現実の「岡っ引き」は普通、権力をかさにきて弱い者にえばり散らす。そして権力にできるだけうまく取り入り生きる。人間社会は無残だ。宮部みゆき氏はユートピアの「岡っ引き」を描く。