
夏野菜の植え付けも、一段落です。
ソロソロ、秋冬用のぼかし肥の仕込みの時期です。
昨年は、4月18日に仕込んでいます。
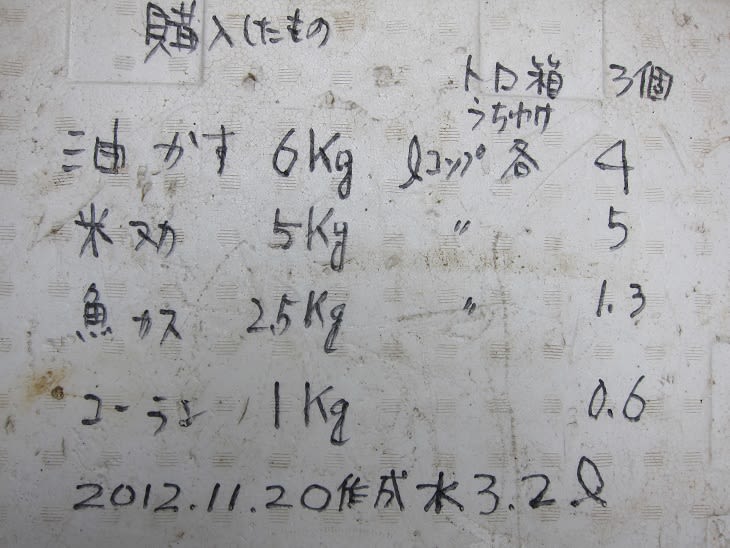
材料は、発泡スチロールのフタに書いてある通りです。
昨年の冬に作った時のものです。
材料の中で、私は魚かす(魚骨粉)をタップリと入れます。
魚かすは、価格は高いですがアミノ酸を多く含み、野菜の甘さが断然増します。
私の野菜が美味しいのは、魚かすの性と言っても過言ではありません。

先ず、それぞれの材料を入れます。

作るのは、何時ものようにトロ箱三個分です。

水を入れて、よく混ぜます。
材料は全部で14,5キログラム。
それに対し、水は9リットル位を入れます。
ぼかし肥作りは、水の量が一番重要です。
ビチャビチャでもダメ。
少なくてもダメ。
材料をつかみ握りしめたら、固まり、突っついたら、壊れるぐらいがベストです。

出来上がりです。

最後は網を被せて、物置に保管しました。
気温が、最高で20度前後。
ジワジワと発酵させるには、良い時期です。
ぼかし肥は、発酵温度が60度ぐらいの高温ではダメです。
暑い夏場に作ると、一気に温度が60度と高温になり、一日で発酵終わり、悪臭、最悪の場合ウジ虫がわきます。
寒い、真冬の場合も私のように少量を作るときは、中々発酵が進まず、腐敗するケースがあります。
と言うことで、春秋作るのが一番。
暫くは、物置で様子を見ます。






























