杓子定規と汚職の間 つづき:大人とは何?シリーズ⓶
 社会は人々の了解事項のもとで複雑化し、大勢の人を養います。その基本はなんといっても言語。それに加えて慣習と法規があります。慣習と法規が一定の対立を持って社会を支えている…、このことは子供のころは分からないものです。いや、大人でも...。
社会は人々の了解事項のもとで複雑化し、大勢の人を養います。その基本はなんといっても言語。それに加えて慣習と法規があります。慣習と法規が一定の対立を持って社会を支えている…、このことは子供のころは分からないものです。いや、大人でも...。
大勢の人を動かすのですから明文の法規というものがあって、それを越えないように人々は振る舞います。しかし、大規模なものになると、いかに深刻な規則であろうと、人々の脳裏から消えることがしばしばあります。それ以上に問題なのは、大規模なものは「たてまえ」であって、現実は違うんだという「大人」の基準によって人々がふるまう傾向があることです。いわゆる「本音」です。本音の付き合いをするとき、声をひそめ、薄笑いを浮かべながらをするのがいつものことです。もしあなたが舞台で演技をする人ならきっと頷いていただけることでしょう。この意識が麻薬の作用を働き、大規模で、深刻な規則を無視させるようになると...、さあ、たいへん。仮にちゃんとこのメカニズムが分かっている人がいてあなたを貶めようとしたとしたら、あなたは一生を棒にふるようなことにもなりかねません。どうですか。こんな抽象的な語りくちでも、某官庁の汚職事件を思い浮かべる人は、あるなまなましいものをお感じにならないでしょうか。
 その反対に、杓子定規とういものがあります。規則というものは何か目的があってそれを達成するための道具です。道具なので不完全な点がたくさんあります。絶対守らなければならない条項もあれば、なかには「玉虫色」と言って意味のないものもあります。その違いを認識しないで石頭で規則通りに行動する、というのも考えもの...。いや、それ以上に危険なものがあります。世の中には、軍隊のように命令系統が厳格な大組織というものもあれば、数人で共同する仲間、小企業もあります。その両方があって社会が成り立つものです。数人で共同する仲間の間ではお互いの意図を察して、慣習に基づいて行動します。「前はこう決めましたが、今回はこれで参りましょう」ということの連続です。それを成り立たせるのが<信頼感>です。人間の、ある意味、根源的な感情です。しかし、現代のような大きな社会においては信頼感がなりたつ限界というものがあります。この点は法規に厳格に、この点はあうんの呼吸で、と臨機応変に対応しなければなりません。
その反対に、杓子定規とういものがあります。規則というものは何か目的があってそれを達成するための道具です。道具なので不完全な点がたくさんあります。絶対守らなければならない条項もあれば、なかには「玉虫色」と言って意味のないものもあります。その違いを認識しないで石頭で規則通りに行動する、というのも考えもの...。いや、それ以上に危険なものがあります。世の中には、軍隊のように命令系統が厳格な大組織というものもあれば、数人で共同する仲間、小企業もあります。その両方があって社会が成り立つものです。数人で共同する仲間の間ではお互いの意図を察して、慣習に基づいて行動します。「前はこう決めましたが、今回はこれで参りましょう」ということの連続です。それを成り立たせるのが<信頼感>です。人間の、ある意味、根源的な感情です。しかし、現代のような大きな社会においては信頼感がなりたつ限界というものがあります。この点は法規に厳格に、この点はあうんの呼吸で、と臨機応変に対応しなければなりません。
 ここで、大人というものの一つの条件が見えてまいりました。「大人だからルールを守れ」だけでは大人の条件としては不十分。かと言って、先ほどの「本音のつきあい」が大人の条件のはずはありません。信頼感と規則の意味の理解という両輪に基づいて、その場に適切な判断を下せることが大人である一つの条件だと思います。この判断を下せる人は少し話すと分かります。落ち着いた人柄が自ずと現れます。その判断ができない人は、やはり、少しお付き合いすると分かるものです。杓子定規どころかある種狂気をはらんでいる場合もあるので注意したいです。G. K.チェスタートンは「理性以外のすべてを失った人は狂人である」と述べましたが、後者の人には極端な場合、これが当てはまる場合もありそうです。会社で新人を採用する方、どう思われますか?。頷いていただけるでしょうか。しかし、あまりに短期のお付き合いだと分からないこともありますしねえ...。
ここで、大人というものの一つの条件が見えてまいりました。「大人だからルールを守れ」だけでは大人の条件としては不十分。かと言って、先ほどの「本音のつきあい」が大人の条件のはずはありません。信頼感と規則の意味の理解という両輪に基づいて、その場に適切な判断を下せることが大人である一つの条件だと思います。この判断を下せる人は少し話すと分かります。落ち着いた人柄が自ずと現れます。その判断ができない人は、やはり、少しお付き合いすると分かるものです。杓子定規どころかある種狂気をはらんでいる場合もあるので注意したいです。G. K.チェスタートンは「理性以外のすべてを失った人は狂人である」と述べましたが、後者の人には極端な場合、これが当てはまる場合もありそうです。会社で新人を採用する方、どう思われますか?。頷いていただけるでしょうか。しかし、あまりに短期のお付き合いだと分からないこともありますしねえ...。











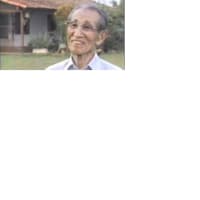
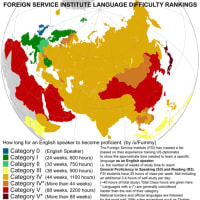




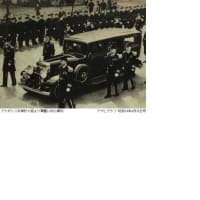
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます