昨年7月、同じ日に季羨林・任継愈という二人の大学者が亡くなった。
しかし、季羨林に比べて、任継愈はあまり評判がよくない。
まず、その研究にあまり新しい意見がない。
そして、何でもかんでも唯物論的に記述したからだろう。
かなりの博識で、古代から近代に至るまで、諸子百家に儒仏道、史学・文学・自然科学に渡って、更には近代西洋の概念まで用いて著作をなしたが、その多くは、優等生の書いた教科書、に過ぎない。
実際、彼の『中国哲学史』は、40年以上に渡って、中国の哲学科の大学生向けの基本教材として用いられ続けた。しかし、学術研究として見ると、ほとんど旧来の定説を離れておらず、もの足りない。
そして、旧来の説と異なるのは、ただ、唯物論的に思想史を記述したことのみである。
仏教が如何なる経済・政治的状況の上に生まれたのか、ある時代の儒教学説がどのように抑圧者の利益に貢献したのか、一貫してこのような視点で語っている。
ただ、このように言うこともできる。
彼の学問は、常に一般大衆を対象としたものであり、そして、新しい時代の新しい哲学を生むことを目指したものだったのである、と。
そもそも、任継愈が中国哲学史の研究を始めたのは、一般の人々のことを考えたからであった。
彼は当初、真理や永遠性といったことの追究を志し、哲学科にいた。
しかし、1938年、盧溝橋事件に伴う大学南遷の旅中、困窮した農民と荒廃した農村を目の当たりにした。ある労働者に「何故アヘンを吸うのか」と尋ねると、
「吸得起,戒不起(吸うための金はあるが、やめるための金はない)」と言われたという。
つまり、アヘンは安価だが、吸うのをやめれば仕事ができないのだ。こうした貧困・落伍に対して、真理や永遠性の探究がどうして役に立つであろうか。
これをきっかけにして、彼は中国に根ざした思想研究を志し、中国一般大衆の文化的レベル向上という目的意識を掲げたのである。
晩年にも、以下のように語っている。
個人でいくら才能があり、いくら努力しても、その社会全体の大きな流れに沿うものでなければ何の作用も期待できない。そして、社会全体の知的レベルが低ければ、社会の問題を正確に認識して解決することはできず、甚だしくはエリート層までもが参加して愚かな行いをすることになる、と。
そして、このような考えの下で、「民族的認識」「群体的認識」のレベルアップを自らの任務とした。
つまり、民智の向上を目的としたからこそ、高度な語彙をちりばめた学術的レベルの高い研究ではなく、平易な文章で定説を普及させる教科書的著作を発表し続けたのである。
また、新しい時代の新しい哲学について、任継愈は以下のように考えていた。
中国の過去の哲学と連続するものであり、旧哲学から完全に離れて一から建設したり、外国のものを全て移植したりするものではない。将来の中国文化が外来文化を吸収するのにあたっては、もともとあるものの上に接木をすることはできても、溶接で無理にくっつけることはできない。
中国哲学の歴史的任務は、当時の人間が持っている知識を利用し、吸収できる文化的遺産を吸収し、中国哲学史上の具体的内容と結合させ、社会主義の要求に答える中国独自の哲学体系を創建することである。
等々(『任継愈学術文化随筆』所収「従中華民族文化看中国哲学的未来」)。
新しい時代の新しい中国の大衆の要求(任継愈はこれをマルクス主義と考えた)に答える新しい哲学体系の構築が必要なのであるが、その新しい哲学体系も中国の伝統的な文化や哲学と整合するものでなければならないと考えていたのである。そのための試みの一つが、新時代の語彙によって、伝統文化中の様々な事柄について記述し直すということだったのではないだろうか。つまり、新しい時代の概念を用いて伝統文化を理解することによって、新しい文化と伝統文化との間の連続性を実現しようとしたように思われるのである。
そして、第一の理念、一般大衆の知的レベルを向上させるというのも、この第二の理念と連環するものであった。新しい哲学体系は「群体的認識」から乖離しては社会的に効力を持ち得ない。そもそも、全体的な民智が低ければ、新しい時代の問題を正確に捉える概念が生まれることすら難しい。この第二の理念を実現するためには、第一の理念の実現が不可欠なのである。
そして、これらの理念は、著作のみならず、その編纂事業にも反映されている。
彼が主編を務めたものだけでも、『宗教詞典』・『道蔵提要』・『中国科学技術典籍通彙』・『中国蔵書楼』・『中国版本文化叢書』・『墨子大全』・『仏教大辞典』・『中華大蔵経』(漢文部分)、『中華大典』等々多数に上る。
こうした事業は、中国文化について分野の壁を越えた綜合的・体系的な研究を促すためのものであるとともに、その成果を一般に供するためのものでもあった。
彼自身、このように語っている。「今回の古代科学技術典籍の整理は、まだ初歩に過ぎない。……(中略)……現在はまだ、一般の読者の閲読に供するための、点校注釈本や訳文を付した普及版を出版するほどの力量はない」(『中国科学技術典籍通彙』総序)、「我々の国家の現状から考えるに、古籍をしっかり加工した整理事業が本当に必要である。ただ影印本を出すというだけではいけない」(『世紀老人的話 任継愈巻』、pp.130-131)
伝統文化・伝統思想の粋を、専門家以外の人間でも吸収できる形で広く公開することを目指したのである。そして、それは古今東西のあらゆる分野の知を融合させた、中国独自の新しい哲学体系を成立させることを最終的な目的としていたといえよう。
私は、一般論として、
ある一つの明確なイデオロギーによってなされた学問は、
その時代には大きく流行するかもしれないが、
数百年という単位では長続きしないものだと思っている。
任継愈の学問も、マルクス主義の色彩が強すぎるために、
もはや現在すでに古臭いものとなっている。
しかし、表層の言葉から一歩掘り下げて眺めた時、
そこには何か普遍的な理念が見出せる。
現在、彼の著作を引用する論文はほとんどない。
しかし、彼の思想は、決して過去のものではなく、
我々の進むべき、一つの方向を示し続けているように思えてならない。
しかし、季羨林に比べて、任継愈はあまり評判がよくない。
まず、その研究にあまり新しい意見がない。
そして、何でもかんでも唯物論的に記述したからだろう。
かなりの博識で、古代から近代に至るまで、諸子百家に儒仏道、史学・文学・自然科学に渡って、更には近代西洋の概念まで用いて著作をなしたが、その多くは、優等生の書いた教科書、に過ぎない。
実際、彼の『中国哲学史』は、40年以上に渡って、中国の哲学科の大学生向けの基本教材として用いられ続けた。しかし、学術研究として見ると、ほとんど旧来の定説を離れておらず、もの足りない。
そして、旧来の説と異なるのは、ただ、唯物論的に思想史を記述したことのみである。
仏教が如何なる経済・政治的状況の上に生まれたのか、ある時代の儒教学説がどのように抑圧者の利益に貢献したのか、一貫してこのような視点で語っている。
ただ、このように言うこともできる。
彼の学問は、常に一般大衆を対象としたものであり、そして、新しい時代の新しい哲学を生むことを目指したものだったのである、と。
そもそも、任継愈が中国哲学史の研究を始めたのは、一般の人々のことを考えたからであった。
彼は当初、真理や永遠性といったことの追究を志し、哲学科にいた。
しかし、1938年、盧溝橋事件に伴う大学南遷の旅中、困窮した農民と荒廃した農村を目の当たりにした。ある労働者に「何故アヘンを吸うのか」と尋ねると、
「吸得起,戒不起(吸うための金はあるが、やめるための金はない)」と言われたという。
つまり、アヘンは安価だが、吸うのをやめれば仕事ができないのだ。こうした貧困・落伍に対して、真理や永遠性の探究がどうして役に立つであろうか。
これをきっかけにして、彼は中国に根ざした思想研究を志し、中国一般大衆の文化的レベル向上という目的意識を掲げたのである。
晩年にも、以下のように語っている。
個人でいくら才能があり、いくら努力しても、その社会全体の大きな流れに沿うものでなければ何の作用も期待できない。そして、社会全体の知的レベルが低ければ、社会の問題を正確に認識して解決することはできず、甚だしくはエリート層までもが参加して愚かな行いをすることになる、と。
そして、このような考えの下で、「民族的認識」「群体的認識」のレベルアップを自らの任務とした。
つまり、民智の向上を目的としたからこそ、高度な語彙をちりばめた学術的レベルの高い研究ではなく、平易な文章で定説を普及させる教科書的著作を発表し続けたのである。
また、新しい時代の新しい哲学について、任継愈は以下のように考えていた。
中国の過去の哲学と連続するものであり、旧哲学から完全に離れて一から建設したり、外国のものを全て移植したりするものではない。将来の中国文化が外来文化を吸収するのにあたっては、もともとあるものの上に接木をすることはできても、溶接で無理にくっつけることはできない。
中国哲学の歴史的任務は、当時の人間が持っている知識を利用し、吸収できる文化的遺産を吸収し、中国哲学史上の具体的内容と結合させ、社会主義の要求に答える中国独自の哲学体系を創建することである。
等々(『任継愈学術文化随筆』所収「従中華民族文化看中国哲学的未来」)。
新しい時代の新しい中国の大衆の要求(任継愈はこれをマルクス主義と考えた)に答える新しい哲学体系の構築が必要なのであるが、その新しい哲学体系も中国の伝統的な文化や哲学と整合するものでなければならないと考えていたのである。そのための試みの一つが、新時代の語彙によって、伝統文化中の様々な事柄について記述し直すということだったのではないだろうか。つまり、新しい時代の概念を用いて伝統文化を理解することによって、新しい文化と伝統文化との間の連続性を実現しようとしたように思われるのである。
そして、第一の理念、一般大衆の知的レベルを向上させるというのも、この第二の理念と連環するものであった。新しい哲学体系は「群体的認識」から乖離しては社会的に効力を持ち得ない。そもそも、全体的な民智が低ければ、新しい時代の問題を正確に捉える概念が生まれることすら難しい。この第二の理念を実現するためには、第一の理念の実現が不可欠なのである。
そして、これらの理念は、著作のみならず、その編纂事業にも反映されている。
彼が主編を務めたものだけでも、『宗教詞典』・『道蔵提要』・『中国科学技術典籍通彙』・『中国蔵書楼』・『中国版本文化叢書』・『墨子大全』・『仏教大辞典』・『中華大蔵経』(漢文部分)、『中華大典』等々多数に上る。
こうした事業は、中国文化について分野の壁を越えた綜合的・体系的な研究を促すためのものであるとともに、その成果を一般に供するためのものでもあった。
彼自身、このように語っている。「今回の古代科学技術典籍の整理は、まだ初歩に過ぎない。……(中略)……現在はまだ、一般の読者の閲読に供するための、点校注釈本や訳文を付した普及版を出版するほどの力量はない」(『中国科学技術典籍通彙』総序)、「我々の国家の現状から考えるに、古籍をしっかり加工した整理事業が本当に必要である。ただ影印本を出すというだけではいけない」(『世紀老人的話 任継愈巻』、pp.130-131)
伝統文化・伝統思想の粋を、専門家以外の人間でも吸収できる形で広く公開することを目指したのである。そして、それは古今東西のあらゆる分野の知を融合させた、中国独自の新しい哲学体系を成立させることを最終的な目的としていたといえよう。
私は、一般論として、
ある一つの明確なイデオロギーによってなされた学問は、
その時代には大きく流行するかもしれないが、
数百年という単位では長続きしないものだと思っている。
任継愈の学問も、マルクス主義の色彩が強すぎるために、
もはや現在すでに古臭いものとなっている。
しかし、表層の言葉から一歩掘り下げて眺めた時、
そこには何か普遍的な理念が見出せる。
現在、彼の著作を引用する論文はほとんどない。
しかし、彼の思想は、決して過去のものではなく、
我々の進むべき、一つの方向を示し続けているように思えてならない。










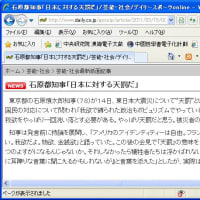

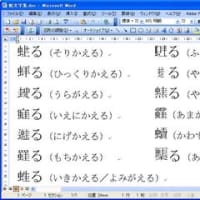




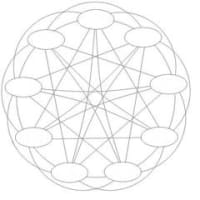


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます