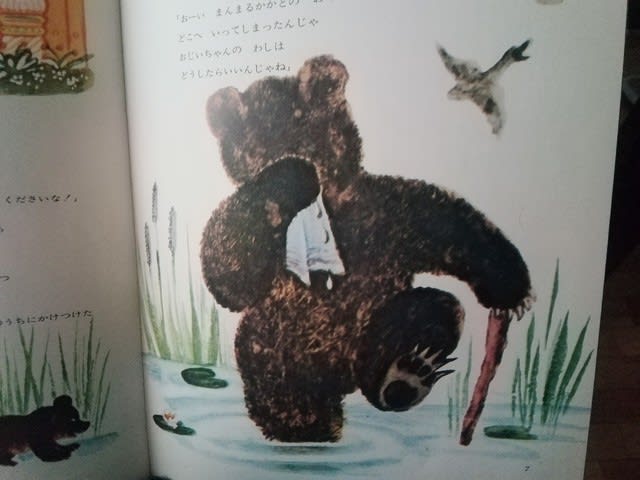この本のことをこんなに書くつもりはなかったのですが、最後にどうしてもご紹介したいピアニストがいます。
バイロン・ジャニス(Bayron Janis)
アメリカのピアニストで、ホロヴィッツの最初の弟子で一番長く教えを受けていた人物です。
ホロヴィッツはレッスンで模範演奏を示すことはなかったそうです。
しかし、レッスンが終わるといつも楽しそうに演奏を聴かせてくれ、それが一晩中続くことも珍しくなかったと。
あまりに彼の演奏を聴きすぎてしまったので自分自身を見失い、彼の真似をして弾くようになってしまった。5年間学びその後5年かけて彼の演奏の影響からやっと抜け出したそうです。
インタビュアーの焦さんが、「あなたのショパンの演奏には他のどのピアニストとも比べられない魔力があり、ショパン自身が弾いているのではないかと思うほどです」とおっしゃっているので、どんな演奏をされる方かと興味を持ち演奏を探してみました。
こちらです。
Byron Janis plays Chopin's Ballade No. 1 Opus 23 (1952 rec.)
第一音、ホロヴィッツっぽいと思いましたがそのあとは違います。
聴き入ってしまいました。そして続けて3回も聴いてしまいました・・
この曲好きですが聴き飽きてしまっていて、こんなに聴くつもりはなかったのに。
ジャニスさんはショパンがいつもすぐそばにいる気がすると。
ショパンは演奏している時、ピアノを弾いている感覚ではなく魂を表現している感覚だったのではないか。彼自身よく「どこかへ」「あそこに」と言っていたようだと。現実ではないどこか。
第3巻は存じ上げないピアニストが多いのですが、聴いて一番驚いたのがジャニスさんです。
ここから先は、バラードの演奏を聴いた翌々日に読んで知ったことです。
ジャニスさん、子供の頃のケガで左手小指の感覚がないのだそうです。
45歳頃に関節炎になり、63歳頃関節炎の痛みがひどくなり手術をし親指の先を失ったそうです。
絶望感を味わいながら毎日を過ごし、やりきれない思いを何曲かの歌曲にしたそうです。それが友人に素敵だとほめられ、ミュージカルの台本に曲をつけることを勧められ、この経験が希望を与えてくれたと。
他の方法で自分を表現することができる、人生には様々な可能性があると考えられるようになり、手の問題にも立ち向かうことができるようになったそうです。
練習方法を工夫し、再び演奏できるようになったとのことです。
敬服。
レオン・フライシャーが右手を故障した話は有名ですが(局所性ジストニア)、彼は右手に問題が生じても音楽を追求することをやめなかったそうです。考えてもいなかった、教育活動に身を投じ、指揮にも挑戦することに。
障害を負う前より良い音楽家、良い教師になったと思うと。一つの窓が閉ざされても他にたくさんの窓がある。人間は不断に成長していけると思うと話されています。
バイロン・ジャニス(Bayron Janis)
アメリカのピアニストで、ホロヴィッツの最初の弟子で一番長く教えを受けていた人物です。
ホロヴィッツはレッスンで模範演奏を示すことはなかったそうです。
しかし、レッスンが終わるといつも楽しそうに演奏を聴かせてくれ、それが一晩中続くことも珍しくなかったと。
あまりに彼の演奏を聴きすぎてしまったので自分自身を見失い、彼の真似をして弾くようになってしまった。5年間学びその後5年かけて彼の演奏の影響からやっと抜け出したそうです。
インタビュアーの焦さんが、「あなたのショパンの演奏には他のどのピアニストとも比べられない魔力があり、ショパン自身が弾いているのではないかと思うほどです」とおっしゃっているので、どんな演奏をされる方かと興味を持ち演奏を探してみました。
こちらです。
Byron Janis plays Chopin's Ballade No. 1 Opus 23 (1952 rec.)
第一音、ホロヴィッツっぽいと思いましたがそのあとは違います。
聴き入ってしまいました。そして続けて3回も聴いてしまいました・・
この曲好きですが聴き飽きてしまっていて、こんなに聴くつもりはなかったのに。
ジャニスさんはショパンがいつもすぐそばにいる気がすると。
ショパンは演奏している時、ピアノを弾いている感覚ではなく魂を表現している感覚だったのではないか。彼自身よく「どこかへ」「あそこに」と言っていたようだと。現実ではないどこか。
第3巻は存じ上げないピアニストが多いのですが、聴いて一番驚いたのがジャニスさんです。
ここから先は、バラードの演奏を聴いた翌々日に読んで知ったことです。
ジャニスさん、子供の頃のケガで左手小指の感覚がないのだそうです。
45歳頃に関節炎になり、63歳頃関節炎の痛みがひどくなり手術をし親指の先を失ったそうです。
絶望感を味わいながら毎日を過ごし、やりきれない思いを何曲かの歌曲にしたそうです。それが友人に素敵だとほめられ、ミュージカルの台本に曲をつけることを勧められ、この経験が希望を与えてくれたと。
他の方法で自分を表現することができる、人生には様々な可能性があると考えられるようになり、手の問題にも立ち向かうことができるようになったそうです。
練習方法を工夫し、再び演奏できるようになったとのことです。
敬服。
レオン・フライシャーが右手を故障した話は有名ですが(局所性ジストニア)、彼は右手に問題が生じても音楽を追求することをやめなかったそうです。考えてもいなかった、教育活動に身を投じ、指揮にも挑戦することに。
障害を負う前より良い音楽家、良い教師になったと思うと。一つの窓が閉ざされても他にたくさんの窓がある。人間は不断に成長していけると思うと話されています。










 )
)