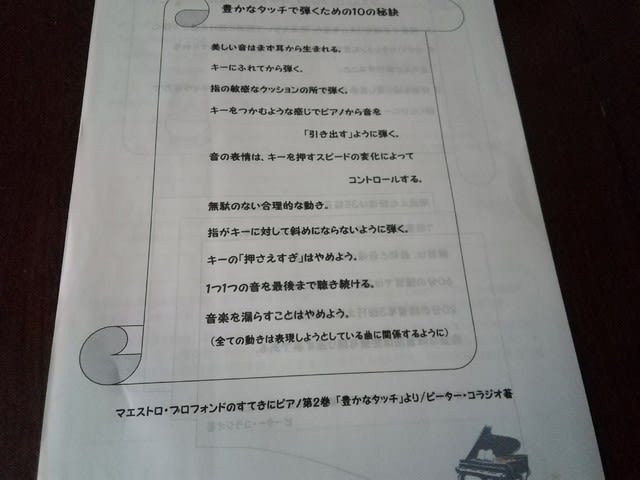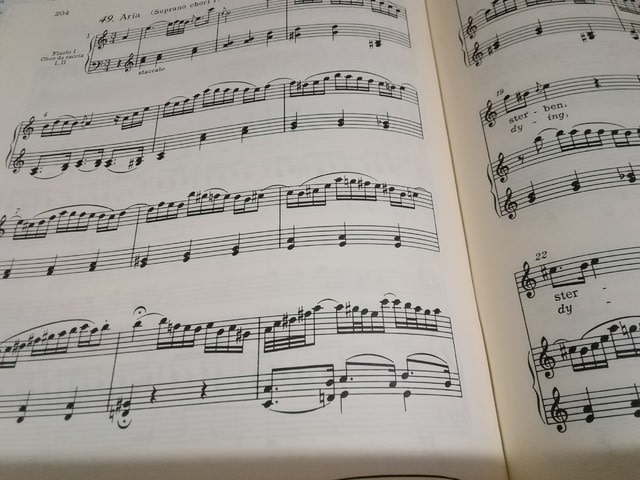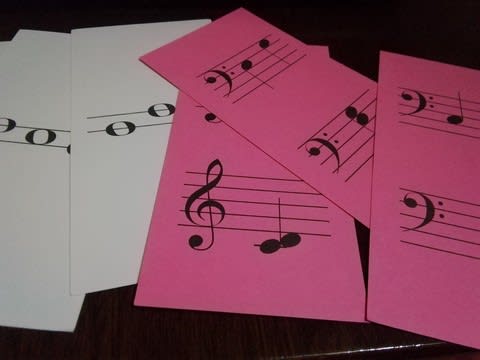遅ればせながら「羊と鋼の森」を読んでいます。
大人の生徒さんが面白いと仰るので、それでは読んでみるかと。
まだ読み始めたばかりですが、考えさせられることが色々とあり、調律師さんの話ですが生徒さんに対する自分への問いかけにも思えます。
ドキッとしたのが、
「求められていないところでがんばっても得るものはない」と言い放つ先輩調律師の言葉。
私なんてこの毎日だと思い、自分のしていることは無駄なことなのかと、しばし考え込んでしまいました。
わからないだろうと思われて一律の調律しかしてもらえない人のことを思うと胸が重たくなると、主人公。
もしかしたらわかるようになるかもしれない。
秋野さん(先輩調律師)の調律した音を聴いてピアノに目覚める可能性だってあるのではないか。
と主人公はさらに思います。
そうそう、このことを信じて私はレッスンを続けています。
信じなければ続けられない。
主人公が予定外の調律を一人でしてしまい、大失敗をした日に憧れの調律師さんに「きっとここから始まるんですよ」と愛用のハンマーをプレゼントされる場面で、また自分に置き換えて考えてしまったことが書かれていました。
「森の入り口に立った僕に、そこから歩いてくればいいと言ってくれているのだ」
これから彼は鬱蒼とした森の中を歩いて行かなければいけません。
体育館で初めて聴いたその調律師さんの音を求めて調律師の道に進んだ主人公。
あれから少しも近づいてはいない。もしかしたら、これからもずっと近づくことはできないのかもしれない、と主人公。
私自身も森の中で近付くこともできないものを求めているのかと思ったり、生徒さんのレッスンでは、まずは森の入り口に皆を立たせたいと思ったり。
森の大きさは色々とあると思いますが、森に入るには身支度が必要です。
サンダルで飲み物も持たず入って、迷ってしまったら苦しい思いをするでしょう。
身支度するには子供の内は親御さんに手伝ってもらう必要があります。
生徒さんとは、できれば森の中を一緒に歩いて色々発見したいと思うのです。
一人で歩ける日までは。
大人の生徒さんが面白いと仰るので、それでは読んでみるかと。
まだ読み始めたばかりですが、考えさせられることが色々とあり、調律師さんの話ですが生徒さんに対する自分への問いかけにも思えます。
ドキッとしたのが、
「求められていないところでがんばっても得るものはない」と言い放つ先輩調律師の言葉。
私なんてこの毎日だと思い、自分のしていることは無駄なことなのかと、しばし考え込んでしまいました。
わからないだろうと思われて一律の調律しかしてもらえない人のことを思うと胸が重たくなると、主人公。
もしかしたらわかるようになるかもしれない。
秋野さん(先輩調律師)の調律した音を聴いてピアノに目覚める可能性だってあるのではないか。
と主人公はさらに思います。
そうそう、このことを信じて私はレッスンを続けています。
信じなければ続けられない。
主人公が予定外の調律を一人でしてしまい、大失敗をした日に憧れの調律師さんに「きっとここから始まるんですよ」と愛用のハンマーをプレゼントされる場面で、また自分に置き換えて考えてしまったことが書かれていました。
「森の入り口に立った僕に、そこから歩いてくればいいと言ってくれているのだ」
これから彼は鬱蒼とした森の中を歩いて行かなければいけません。
体育館で初めて聴いたその調律師さんの音を求めて調律師の道に進んだ主人公。
あれから少しも近づいてはいない。もしかしたら、これからもずっと近づくことはできないのかもしれない、と主人公。
私自身も森の中で近付くこともできないものを求めているのかと思ったり、生徒さんのレッスンでは、まずは森の入り口に皆を立たせたいと思ったり。
森の大きさは色々とあると思いますが、森に入るには身支度が必要です。
サンダルで飲み物も持たず入って、迷ってしまったら苦しい思いをするでしょう。
身支度するには子供の内は親御さんに手伝ってもらう必要があります。
生徒さんとは、できれば森の中を一緒に歩いて色々発見したいと思うのです。
一人で歩ける日までは。