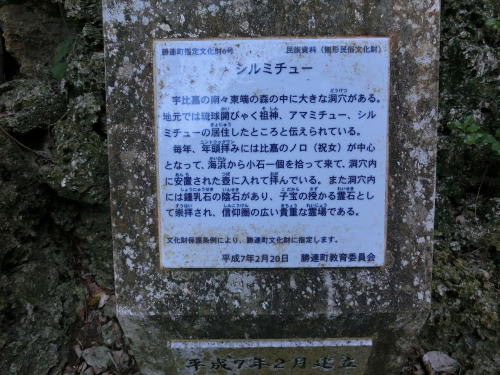尚 宣威王の墓

尚 宣威王の墓 ( 手前 ) と親族の墓 ( 奥 )

尚 宣威王の親族の墓

墓の前にある尚 宣威王の経歴が彫られた碑文

この長い階段の上に墓がある

階段の登り口にある 「 尚宣威王御墓 」 と彫られた墓標
沖縄市にある美来工業高校 ( 旧・中部工業 ) の裏門前を抜けると 「 かやま橋 」 が架かっている。
その橋を渡り切って、すぐに左に曲がると尚 宣威王の墓がある。
尚 宣威王の墓は、階段を上った崖の中腹にある横穴墓で、入り口を布石で塞いである。
第二尚氏・尚 円王が病死し、世子の久米中城王子 ( のちの尚 真王 ) は幼少ということで、
諸君に推されて尚 宣威王 ( 尚 円王の弟 ) が王位に就いた。
尚 宣威王は越来王子として六年間、越来グスクにいたが、
即位してからは首里城に共住した。
しかし、在位六か月後に 「 神のお告げがあり、尚 真こそ王を継ぐべき 」 と、
神女が託宣した。
これは神の仕草をする神女と、尚 真の母とが策略したものであろう。
尚 宣威は退位し、越来村に隠遁した。
その子孫は湧川殿内門中である。
長男の越来王子朝理 ( 湧川殿内の始祖 ) は越来間切り総地頭だったが、
二世からは越来間切り美里の脇地頭に下がった。
後年、尚 真王の四男・朝福が越来王子になり、越来間切り総地頭になった。