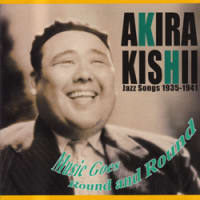24日土曜の夜、アンスティチュ・フランセ(東京・市谷船河原町)で《追悼 梅本洋一 映画批評=現在と並走すること》というイベントが開かれ、楊徳昌(エドワード・ヤン)監督『ヤンヤン 夏の想い出』(2000)の35mmフィルム上映と旧「カイエ・デュ・シネマ・ジャポン」編集委員のうち3名のトークショーがおこなわれた。梅本が「カイエ・デュ・シネマ・ジャポン」誌の休刊最終号(2001)に寄稿した『ヤンヤン』についての批評「映画で思考するためには」は、現在発売中の「nobody」誌最新号に再掲載されている。
トークには、主催の「nobody」編集部から田中竜輔、高木佑介両氏のダブル司会、旧「カイエ」からは稲川方人、安井豊作、そして私が壇上に上がった。始まる前、私は主催者にひとつのお願いをした。それは映画上映のあと、トークを始める前に、梅本洋一および彼を追うように先日逝去したご母堂のために1分間の黙祷をおこないたいという依頼である。葬儀にしろ法事にしろ、儀式というものは、死者のためではなく、残された生者のためにある。梅本洋一本人は堅苦しい形式性を嫌う人だったから、黙祷など嫌がるだろうが、私個人にとってそれは必要な儀礼である。結果、観客の方々にまでお付きあいをいただいた。カジュアルさを好む梅本洋一に対し、あえて形式性を押し当てていじめたいという悪戯心もある。
 思えば、楊の『ヤンヤン 夏の想い出』もまた、儀式の映画である。結婚式に始まり、葬式で終わる。台北に生きるある一族の老若男女それぞれのひと夏の生の断面をポリフォニックに語っているかに見えながら、生そのものが形成する儀式の総体的な円環から決して逃れようとしない。楊徳昌の映画は、IT産業や高層マンションなど現代的な意匠を散りばめつつも、熱海への一泊旅行が写っているといった引用にとどまらぬレベルで小津安二郎との親近性が濃厚である。それはもっぱら、この儀式の円環性が証拠立てているのだ。
思えば、楊の『ヤンヤン 夏の想い出』もまた、儀式の映画である。結婚式に始まり、葬式で終わる。台北に生きるある一族の老若男女それぞれのひと夏の生の断面をポリフォニックに語っているかに見えながら、生そのものが形成する儀式の総体的な円環から決して逃れようとしない。楊徳昌の映画は、IT産業や高層マンションなど現代的な意匠を散りばめつつも、熱海への一泊旅行が写っているといった引用にとどまらぬレベルで小津安二郎との親近性が濃厚である。それはもっぱら、この儀式の円環性が証拠立てているのだ。
ラスト、一族の長であるお祖母ちゃん(唐如韞)が亡くなり、葬式がおこなわれる。脳卒中で昏睡状態となった祖母に話しかけることを拒否して母親(金燕玲──楊徳昌作品の常連であるこの人は素晴らしい女優だ・左の写真)から “冷たい孫” と叱られていた小学生の孫・洋洋(張洋洋)が、祖母の死に際してついにみずから言葉を獲得し、誰に言われるでもなく祭壇の前に歩み寄り、弔辞を述べる。このラストカットの感慨は格別なものがある。そしてそれはつい5ヶ月前、青山葬儀所でわれわれ自身が読んだ弔辞の記憶に繋がっていくのである。
トークには、主催の「nobody」編集部から田中竜輔、高木佑介両氏のダブル司会、旧「カイエ」からは稲川方人、安井豊作、そして私が壇上に上がった。始まる前、私は主催者にひとつのお願いをした。それは映画上映のあと、トークを始める前に、梅本洋一および彼を追うように先日逝去したご母堂のために1分間の黙祷をおこないたいという依頼である。葬儀にしろ法事にしろ、儀式というものは、死者のためではなく、残された生者のためにある。梅本洋一本人は堅苦しい形式性を嫌う人だったから、黙祷など嫌がるだろうが、私個人にとってそれは必要な儀礼である。結果、観客の方々にまでお付きあいをいただいた。カジュアルさを好む梅本洋一に対し、あえて形式性を押し当てていじめたいという悪戯心もある。
 思えば、楊の『ヤンヤン 夏の想い出』もまた、儀式の映画である。結婚式に始まり、葬式で終わる。台北に生きるある一族の老若男女それぞれのひと夏の生の断面をポリフォニックに語っているかに見えながら、生そのものが形成する儀式の総体的な円環から決して逃れようとしない。楊徳昌の映画は、IT産業や高層マンションなど現代的な意匠を散りばめつつも、熱海への一泊旅行が写っているといった引用にとどまらぬレベルで小津安二郎との親近性が濃厚である。それはもっぱら、この儀式の円環性が証拠立てているのだ。
思えば、楊の『ヤンヤン 夏の想い出』もまた、儀式の映画である。結婚式に始まり、葬式で終わる。台北に生きるある一族の老若男女それぞれのひと夏の生の断面をポリフォニックに語っているかに見えながら、生そのものが形成する儀式の総体的な円環から決して逃れようとしない。楊徳昌の映画は、IT産業や高層マンションなど現代的な意匠を散りばめつつも、熱海への一泊旅行が写っているといった引用にとどまらぬレベルで小津安二郎との親近性が濃厚である。それはもっぱら、この儀式の円環性が証拠立てているのだ。ラスト、一族の長であるお祖母ちゃん(唐如韞)が亡くなり、葬式がおこなわれる。脳卒中で昏睡状態となった祖母に話しかけることを拒否して母親(金燕玲──楊徳昌作品の常連であるこの人は素晴らしい女優だ・左の写真)から “冷たい孫” と叱られていた小学生の孫・洋洋(張洋洋)が、祖母の死に際してついにみずから言葉を獲得し、誰に言われるでもなく祭壇の前に歩み寄り、弔辞を述べる。このラストカットの感慨は格別なものがある。そしてそれはつい5ヶ月前、青山葬儀所でわれわれ自身が読んだ弔辞の記憶に繋がっていくのである。