マイナビニュース、旅と乗り物記事からです。通過列車に近づくのはとても危険であるというお話。それを飛行機の浮上原理から説明した記事です。
記事:通過列車の近くにいると危険! 理由は飛行機が飛ぶ原理で説明できる
列車の正面を見ながら乗っていると、たまに通過駅なのに、ホームぎりぎり近くに立っている人を見かけますが、そういうのは冷っとします。運転士も当然汽笛を鳴らして、注意喚起。しかしこれを注意喚起と取らず、「威嚇」の意味に取られる人がいるんだそうですね。
高速で通過すると、通過列車の周囲は空気が移動します。空気が移動、すなわち風です。風が発生するということとは、負圧がかかっているわけで、周囲から巻き込むような空気の動きが発生します。
つまり通過列車に吸い込まれるような動きをします。
実は、踏切遮断機近くでカメラを構えて、怖かった思いがあります。
兵庫県西宮市の阪急神戸線武庫之荘駅近くの踏切で。
三宮方面の特急列車接近でカメラを構えたところ、115km/hの速度は当たり前ですが、風圧が凄い。
まず吹き飛ばされるような風圧で、先頭車の真ん中あたりから吸い込まれるような動き。
今だと(杖携行)絶対に列車に吸い込まれていると思います。
この時の撮影画像を探してみましたが、該当無いということは写していないようです。
おそらくカメラ構える体が揺れて、撮影になならなかっただろうと思います。
そういう経験があるので、今では地下鉄駅で、列車進入時には、ホーム柱に手を添えて体を支えているほど。
こういうのは、物理の原理で説明できますし、十分想像できますが、中にはぶつかる位置ではないから、ということで、ホーム端ギリギリのところにいる方がいます。物理などの科学が不得意なのでしょうね。
通過列車には十分気を付けたいものです。
***
ところでいつも名鉄一宮駅から乗る、一宮始発の急行列車、直ぐ後に普通電車が発車するダイヤゆえ、次の駅、妙興寺駅では、その普通に乗る人が多数。
時間的に普通列車到着の頃に急行通過なので、接近放送で、ホーム端に立たれる人を多く見ます。
急行通過の後、普通なのですが、そういう順序を理解するのは、私のような鉄ヲタぐらいで、多くの人は時刻表を見て、そろそろ時間だ、ということえ接近放送があれば普通列車の到着と思われるのかもしれません。
記事:通過列車の近くにいると危険! 理由は飛行機が飛ぶ原理で説明できる
列車の正面を見ながら乗っていると、たまに通過駅なのに、ホームぎりぎり近くに立っている人を見かけますが、そういうのは冷っとします。運転士も当然汽笛を鳴らして、注意喚起。しかしこれを注意喚起と取らず、「威嚇」の意味に取られる人がいるんだそうですね。
高速で通過すると、通過列車の周囲は空気が移動します。空気が移動、すなわち風です。風が発生するということとは、負圧がかかっているわけで、周囲から巻き込むような空気の動きが発生します。
つまり通過列車に吸い込まれるような動きをします。
実は、踏切遮断機近くでカメラを構えて、怖かった思いがあります。
兵庫県西宮市の阪急神戸線武庫之荘駅近くの踏切で。
三宮方面の特急列車接近でカメラを構えたところ、115km/hの速度は当たり前ですが、風圧が凄い。
まず吹き飛ばされるような風圧で、先頭車の真ん中あたりから吸い込まれるような動き。
今だと(杖携行)絶対に列車に吸い込まれていると思います。
この時の撮影画像を探してみましたが、該当無いということは写していないようです。
おそらくカメラ構える体が揺れて、撮影になならなかっただろうと思います。
そういう経験があるので、今では地下鉄駅で、列車進入時には、ホーム柱に手を添えて体を支えているほど。
こういうのは、物理の原理で説明できますし、十分想像できますが、中にはぶつかる位置ではないから、ということで、ホーム端ギリギリのところにいる方がいます。物理などの科学が不得意なのでしょうね。
通過列車には十分気を付けたいものです。
***
ところでいつも名鉄一宮駅から乗る、一宮始発の急行列車、直ぐ後に普通電車が発車するダイヤゆえ、次の駅、妙興寺駅では、その普通に乗る人が多数。
時間的に普通列車到着の頃に急行通過なので、接近放送で、ホーム端に立たれる人を多く見ます。
急行通過の後、普通なのですが、そういう順序を理解するのは、私のような鉄ヲタぐらいで、多くの人は時刻表を見て、そろそろ時間だ、ということえ接近放送があれば普通列車の到着と思われるのかもしれません。













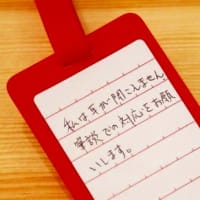
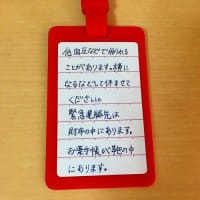





電車や自動車等の側で感じる空気の流れ(吸い寄せられる力)はこの原理ではなく、循環流とそれがはがれた際にはがれた部分から発生する過流によります。
これは揚力を発生させる力とは関係なく、風を切る動きとは別に物体の周囲に張り付いてぐるぐる回る空気の流れです・・・・・・厳密には違うんですが、実際に周囲に与える影響を勘案すると、こういう表現でまあいいでしょう。
当然ながら、進行方向後部では、物体が進行する方向とは逆方向に流れようとする力が出来ますから、これが大きな抵抗となります。通常は進行方向から押し寄せる空気の圧力に負けて、物体後方から循環流が「はがれて」、過流となって渦を巻く形になります。
電車で揚力が問題になる速度は200キロ以上の速度息ですのでクッタ・ジュコーフスキーの定理は実は当てはまらなかったりします。
なかなかこの空気の流れを説明するのが難しいんですが、近視的に見た空気の物理的動きとしてはカルマン渦を想像するとよいでしょう。
カルマン渦は物体後方に発生するので、通過中の電車の側方に対する吸い寄せとは現象自体が違うんですが、高速の電車の通過があると側方面に沿ってはがれる空気と循環する空気が交互に現れるような形がカルマン渦のような空気の流れを成します。
これが電車等の最接近時に一度跳ね飛ばされるような衝撃を受けて、一瞬の後に吸い寄せられる原因となります。
車両連結面でそれらとは関係なく、外に発散する過流がありますので(N700はその過流による抵抗を抑えるために全周ホロを備えている)、通過電車によほどに接近していない限りは、吸い込まれる前に弾かれるのですが、時速百キロ前後の四角い電車の場合は約0.75秒ごとに身体を前後に揺さぶられる(線路長手方向に正対していると仮定した場合)ことになりますから、荷物を持っていたりするとバランスを崩して倒れこむことになりかねませんし(人間は正面方向に重たい、アンバランスな重量配分なのでほぼ間違いなく前に向かって倒れることになる)、買い物袋等を持っているとまず間違いなくそれが吸い込まれて身体ごと持っていかれることになりかねません。
それでも成人男性ならよほどの事が無い限り理論上は大丈夫なんですが(60キロの体重をもっっている標準成体の表面積であればの話)、例えば電車進行方向から強い風が吹いているとか、湿度が高いとか(湿度が高いと吸い込む力は強くなる)、強い勢力の高気圧の勢力下とか(空気密度が高いので同じ速度でも吸い込む力は強くなる)、その両方とか(日本の夏ではありがちな状況)、立っているときの態勢とか服装とか持っている・背負っている荷物とか・・・いろいろな理由で劇的に強い力を受ける可能性があります。
時速130キロ程度までなら30センチ以上離れれば(あくまでも理論上は)まず安全ですが、手荷物などを勘案すれば50センチ以上離れるのがベストです。
高速運転に適した形状を持つ車両、たとえば681系の非貫通先頭車とかパノラマスーパーの豊橋側とかは吸い込む力が強くなりますので大変危険です。
そのため名鉄の特急・快速特急でパノラマスーパーを使っている場合は、通過駅で上りと下りの通過速度を変えている場合があるそうです。
新幹線の場合は途轍もなく強い吸引力を発揮します。特に500系は激烈であって、時速300キロの場合、3メートル以上はなれていた騒音測定マイクのスポンジが吸い込まれたなんて話があるほどです。
通過駅での安全を勘案して683系4000番代車の先頭形状が貫通構造車両と同一になったとか、287系の形状が空気抵抗と循環流のバランスを取った結果とか言われています。
E259系も循環流より過流の方が大きく出る形状だそうで、速度向上を狙うカタチとしては抵抗が大きく、無駄が多いんだそう。
あまり良い話ではありませんが、直前飛び込み人身事故ではE217系の場合は、たいていは下に巻き込まれるのに対して、E259系の場合はホーム上に弾き飛ばすのは、その特性ゆえだということです。
・・・なんだか話がとっちらかりましたが、普段大丈夫だから明日も大丈夫とは限らないという事はみんなに知っていてもらいたいですね。
100回大丈夫だったからと言っても一回吸い込まれればそれで全部終わりですし、そんなことに命をかけるのは馬鹿馬鹿しいですし。
実は毎日の通勤でそういうところで一日の運を消費しているとか考えると、ものすごくもったいないとか。そういう考え方でもいいから、皆さんには危険な事をやめてもらいたいですね。
高速通過列車による風圧は、子どもの頃、新幹線の通過で何度か経験しました。
ひかり号には乗せてもらえず、もっぱらこだまのみ。
こだま号はひかり号の通過待ちを何度かします。
その時の揺れって、かなりのものですね。
ひかり号が横に来た時点と去る時点でふわっと車体が揺れます。
そこで列車が通過する時は、巻き込むような風圧が発生するのだな、と子供心に理解しました。
熱海駅は待避線が無く、ホーム柵・ドアなのはその理由だろうとも思いました。
尤も新幹線お熱海駅はカーブしていて、高速通過できませんけど。
名鉄電車は、一宮在住ということで、一宮~豊川稲荷間の急行に乗ります。
この系統の急行、上下とも新清洲駅で対向する特急列車とすれ違いますが、まさしく新幹線こだま号のような車体の揺れ方。
車内にいたので安全でしたが、あの距離で通過列車のそばにいたら危ないと思います。
ところでその名鉄、岐阜行きと豊橋行きとで通過時の速度が違うんですか?
2200や1700では関係なく120キロで通過します。
681系、683系では非貫通先頭車では確実に速度を落として駅を通過します。
非貫通型先頭車のほうが飛び込まれやすいという統計の結果もあるらしいで、吸い込みに対する対策だけとは言いきれないようです。
253系よりE259系の方が明らかに飛び込まれる割合が多い(というか激増している)という結果も出ていて、JR東日本が頭を抱えているそうで。ここまで来ると吸い込みがどうとか言う以前の話なんですが。