東洋経済ONLNE記事からです。少し前の東京の地下鉄、暑さ対策として車両に冷房機を搭載せず、トンネルを冷やす「トンネル冷房だった」という記事。
記事:地下鉄暑さ対策、昔は「トンネル冷房」だった
これ、今では信じられない話ですが、鉄道車両の冷房機搭載が一般的になり、その昔は「今年の鉄道各線、冷房化率は?」などといった記事が見当たらなくなるほど冷房化が進んだ当時でも、営団地下鉄と都営地下鉄の車両には全く冷房がありませんでした。
営団地下鉄と直通運転する会社の車両、都営地下鉄と相互直通運転する会社の車両、いずれも会社車両は冷房が付いていましたが、地下鉄線へ入ると冷房を止めていました。信じられないですね。
この理由は、当時の営団地下鉄からの文書にありますが、そもそも昭和46年に千代田線に、サイリスタチョッパ制御方式の6000系が導入された理由にもなります。
地下鉄は当然ながらトンネルの連続。車両から放出される熱の行き場がありません。
昔(戦前・戦後のレベル)は地下水があって、トンネルも冷えましたが、その地下水の低下で車両からの発熱はそのままトンネル内に留まるのみ。
車両からの発熱で大きなところは、抵抗器からの発熱です。直流電気で直列・並列・弱メ界磁の組み合わせ制御をするうちは、この抵抗器の発熱から逃れるわけにはいきません。
そこで抵抗器が無く、電子回路だけで制御できる「サイリスタチョッパ制御」の車両が導入された次第です。
抵抗器はその名の通り「抵抗」です。つまり電流を熱に変える機能。熱に変わるということは、それだけ無駄に電力を消費することになり、後にこのサイリスタチョッパ制御の車両は「省エネ車両」とされるようになりました。
そうして車両側からの発熱を抑え、さらにトンネル内の空間自体を冷やすことで、夏場の暑さ対策としていました。
しかし、車両自体の冷房化の要望(というか要求)は高く、営団地下鉄でも都営地下鉄でも車両に冷房を搭載することとなり、トンネル冷房は止めることとなりました。そこにどのような意思形成があったのかは分かりませんが、頑なに車両冷房を拒否し、乗り入れ車両の冷房を止めてまで乗り入れしていたのに、なぜ車両冷房となったのか不思議です、一つには小型軽量化で、能力の割には排熱が少ないのかもしれませんが。
ちなみに、昭和2年の東京地下鉄開業当時のキャッチフレーズは、「夏涼しく、冬暖かい、地下鉄道へどうぞ」というものでした。
最初の地下鉄線は今の銀座線ですが、昔は確かに涼しかったそうです。
記事:地下鉄暑さ対策、昔は「トンネル冷房」だった
これ、今では信じられない話ですが、鉄道車両の冷房機搭載が一般的になり、その昔は「今年の鉄道各線、冷房化率は?」などといった記事が見当たらなくなるほど冷房化が進んだ当時でも、営団地下鉄と都営地下鉄の車両には全く冷房がありませんでした。
営団地下鉄と直通運転する会社の車両、都営地下鉄と相互直通運転する会社の車両、いずれも会社車両は冷房が付いていましたが、地下鉄線へ入ると冷房を止めていました。信じられないですね。
この理由は、当時の営団地下鉄からの文書にありますが、そもそも昭和46年に千代田線に、サイリスタチョッパ制御方式の6000系が導入された理由にもなります。
地下鉄は当然ながらトンネルの連続。車両から放出される熱の行き場がありません。
昔(戦前・戦後のレベル)は地下水があって、トンネルも冷えましたが、その地下水の低下で車両からの発熱はそのままトンネル内に留まるのみ。
車両からの発熱で大きなところは、抵抗器からの発熱です。直流電気で直列・並列・弱メ界磁の組み合わせ制御をするうちは、この抵抗器の発熱から逃れるわけにはいきません。
そこで抵抗器が無く、電子回路だけで制御できる「サイリスタチョッパ制御」の車両が導入された次第です。
抵抗器はその名の通り「抵抗」です。つまり電流を熱に変える機能。熱に変わるということは、それだけ無駄に電力を消費することになり、後にこのサイリスタチョッパ制御の車両は「省エネ車両」とされるようになりました。
そうして車両側からの発熱を抑え、さらにトンネル内の空間自体を冷やすことで、夏場の暑さ対策としていました。
しかし、車両自体の冷房化の要望(というか要求)は高く、営団地下鉄でも都営地下鉄でも車両に冷房を搭載することとなり、トンネル冷房は止めることとなりました。そこにどのような意思形成があったのかは分かりませんが、頑なに車両冷房を拒否し、乗り入れ車両の冷房を止めてまで乗り入れしていたのに、なぜ車両冷房となったのか不思議です、一つには小型軽量化で、能力の割には排熱が少ないのかもしれませんが。
ちなみに、昭和2年の東京地下鉄開業当時のキャッチフレーズは、「夏涼しく、冬暖かい、地下鉄道へどうぞ」というものでした。
最初の地下鉄線は今の銀座線ですが、昔は確かに涼しかったそうです。













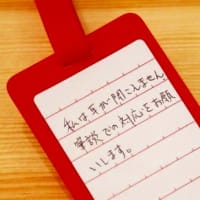
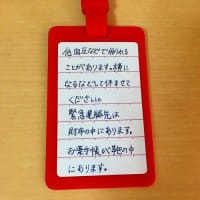





浅草線の場合、1980年代は京成京急の冷房車は冷房を切っていたようですが、1990年代に入ると、抵抗制御車でも地下線内で冷房を使うようになったようです。
自分は体験したことは無いのですが、この時期の浅草線の各駅は暑かったらしいです。
あまりにトンネル内の温度が上がると、床下機器が損傷するというのもあるため、冷房化を見送っていたのではないかと思います。
複線トンネルがほとんどの東西線は、抵抗制御の5000系や国鉄301系103系のまま冷房化していますので、単線シールドトンネルではない限り、トンネル内の温度上昇は、運転上は問題ないようです。
もともと地下式鉄道は、隧道の断面積から車両限界が厳しく冷房機搭載は難しい面もありました。
そこへ抵抗制御ゆえの発熱があり、冷房機の熱交換の発熱が重なることへの深い懸念があったように感じます。
トンネル内の気温上昇自体は、走行には影響はないですが、お客さんの環境ですね。
そこでトンネル自体を冷やす方針が立てられました。
トンネル冷房ですと、車両冷房のような小型化する必要もなく、かなりの冷房容量が得られます。
床下機器が損傷するような温度になれば、とてもお客さんが乗っておられる状況ではなくなりますね。
都営地下鉄は確かに冷房化が遅かった印象です。
暑かったですね。
営団と都営の違いを、まざまざと感じた一面。
千代田線は単線シールドトンネルなので、自然通風式の抵抗器の放熱ができなかったそうです。
103系1kではないですが、電機的にほぼ同じの東西線用301系で、そんな床が焼けるほどの熱さ、というのを聞いたことがあります。
抵抗制御式なので、どうしても熱くなりますね。
名古屋市地下鉄の鶴舞線で、名鉄100系の床が、無茶苦茶熱かったことがありました。
ホームに入ってきた電車の床下から熱風どころか、車内に乗り込むと、靴の底を通して床が熱い。
常磐線の103系1kもそんな状況だろう思います。
ゆえに電力消費量が、営団の6000と全然違うので、相互乗り入れの車両使用量に差をつけよ、と会計検査院からの指摘でした。