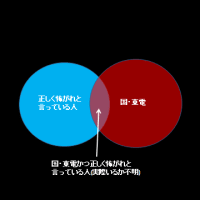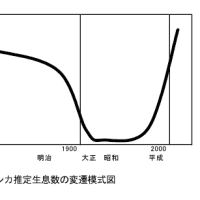さて、長々と池田氏は外来生物問題をわかってね~と書いてきたわけですが、じゃあ交雑のどこが問題なの?ということにはふれていませんでした。なので、交雑による問題点の一つを紹介します。
セイヨウオオマルハナバチという昆虫をご存知でしょうか。トマトの受粉に使用され、外来生物法が施行されるときもブラックバスの次くらいにはマスコミで取り上げられた外来生物です。このセイヨウオオマルハナバチが在来のマルハナバチと交雑すると、受精はするものの受精卵が発育しないことが実験で確かめられました。これは、在来のマルハナバチにとって大きな不利益です。子孫を残すことができないのですから、セイヨウオオマルハナバチと交尾した在来のマルハナバチの遺伝子は消滅してしまいます。(実際はセイヨウオオマルハナバチのみと交雑するわけではないが、セイヨウオオマルハナバチの精子で受精することが不利益になるのは確か)
しかし、これだけで即問題と決め付けることはできません。野外ではまれにしか交雑しないのであれば、交雑の危険性はそれほど高くないでしょう。この交雑の頻度をしらべる調査がおこなわれました。野外から採種した在来のマルハナバチ(オオマルハナバチ、エゾオオマルハナバチ)の女王体内に蓄えられていた精子のDNAを分析したところ多くの女王からセイヨウオオマルハナバチのDNAが検出されました。このことは交雑が野外でも起きていることを示しています。
参考文献
外来生物のリスク管理と有効利用 第9章 輸入昆虫のリスク評価とリスク管理
セイヨウオオマルハナバチという昆虫をご存知でしょうか。トマトの受粉に使用され、外来生物法が施行されるときもブラックバスの次くらいにはマスコミで取り上げられた外来生物です。このセイヨウオオマルハナバチが在来のマルハナバチと交雑すると、受精はするものの受精卵が発育しないことが実験で確かめられました。これは、在来のマルハナバチにとって大きな不利益です。子孫を残すことができないのですから、セイヨウオオマルハナバチと交尾した在来のマルハナバチの遺伝子は消滅してしまいます。(実際はセイヨウオオマルハナバチのみと交雑するわけではないが、セイヨウオオマルハナバチの精子で受精することが不利益になるのは確か)
しかし、これだけで即問題と決め付けることはできません。野外ではまれにしか交雑しないのであれば、交雑の危険性はそれほど高くないでしょう。この交雑の頻度をしらべる調査がおこなわれました。野外から採種した在来のマルハナバチ(オオマルハナバチ、エゾオオマルハナバチ)の女王体内に蓄えられていた精子のDNAを分析したところ多くの女王からセイヨウオオマルハナバチのDNAが検出されました。このことは交雑が野外でも起きていることを示しています。
参考文献
外来生物のリスク管理と有効利用 第9章 輸入昆虫のリスク評価とリスク管理