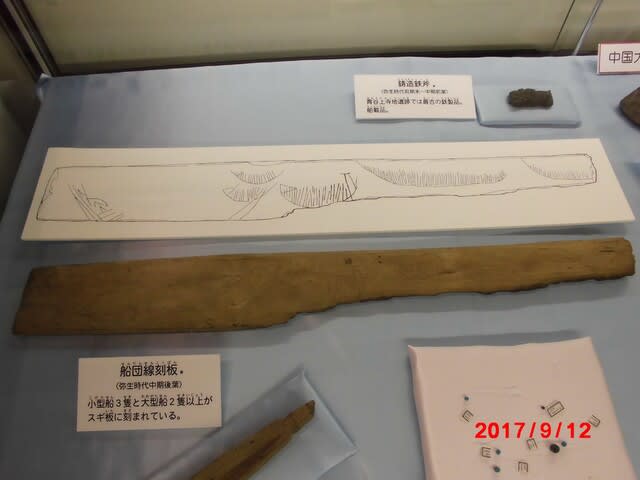今回から鳥取県立博物館の展示品を紹介する。初回は縄文時代の土器を中心とした遺物である。

パネルに説明されているように、縄文土器は15000年前に製作が始まった、これは世界最古であり、我々の祖先は世界最先端のテクノロジーを駆使していたのである。土器の厚さは5mmほどである。中国の玉蟾岩遺跡(ぎょくせんがん)の土器の厚さは1cm以上であった。この時代のナイル川流域やメソポタミアでは、まだ土器を作る技術をしらなかった。縄文人は土器により食べ物を煮炊きし、健康増進に寄与していたと思われる。縄文時代は世界に先駆けた時代であったことを誇りたい。




以下は、石製品である。

下左は玦状耳飾りである。日本の縄文時代と同時代の中国・長江下流域の遺跡からも、この玦状耳飾りが出土する。縄文人は15000年前に中国本土と交流があった証であり、縄文人は世界に誇る日本人の祖であったことになる。
<続く>