【掲載日:平成23年9月13日】
天地に 足はし照りて
我が大君 敷き坐せばかも 楽しき小里
天平勝宝四年(752)四月九日
盧舎那大佛開眼会
聖武上皇 孝謙天皇 光明皇太后 出御の許
文武百官 僧尼一万 打ち揃う
橘奈良麻呂 藤原八束 大伴古慈斐 重責担当
大伴・佐伯 両氏中心の 五節・久米舞 奉納
舞に合わせ 鼓打つは 橘諸兄以下大官十六名
全ての取り仕切り 藤原仲麻呂
麗々しい催し 家待 記録に留めず
やはりに 財の費え 民駆り出し
快しとしない 橘諸兄心境 追随か
大仏開眼会 後
孝謙女帝 皇居帰らず 藤原仲麻呂私邸へ
そこを 御座所とし 日々の起居
その後も しばしばの私邸行幸
【藤原仲麻呂屋敷へ 天皇・皇太后行幸
黄葉した沢欄見て 仲麻呂らに 賜う歌】
この里は 継ぎて霜や置く 夏の野に 我が見し草は 黄葉ちたりけり
《この里は 年中霜が 置くのんか さっきの夏草が 色付きおるよ》
―孝謙天皇―(巻十九・四二六八)
一方 聖武上皇
左大臣橘諸兄邸での 宴席に 座を暖める
【十一月八日】
外のみに 見ればありしを 今日見ては 年に忘れず 思ほえむかも
《噂には 聞いて居ったが 来てみると 忘られんほど 立派なもんや》
―聖武天皇―(巻十九・四二六九)
葎延ふ 賎しきやども 大君の 坐さむと知らば 玉敷かましを
《みすぼらし こんな家でも 上皇が お越しなるなら 玉敷かせたに》
―橘諸兄―(巻十九・四二七〇)
松蔭の 清き浜辺に 玉敷かば 君来まさむか 清き浜辺に
《松繁る 清い池縁 玉敷くと また来られるで 清い池縁》
―藤原八束―(巻十九・四二七一)
天地に 足はし照りて 我が大君 敷き坐せばかも 楽しき小里
《天と地を 照らしなされる 上皇が お越しになれば この里楽し》
―大伴家持―(巻十九・四二七二)
宴に出向いたものの この歌 奏せず
果たして 家待の心境や 如何に
孝謙天皇の 為されよう
咎めだてなさらぬ 聖武上皇
先に作りし お召備えの歌 共々
文箱の底に 眠る運命か










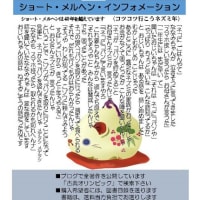
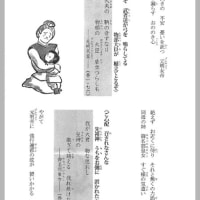
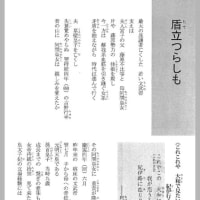
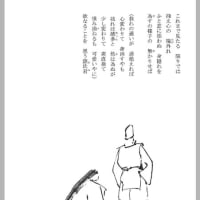
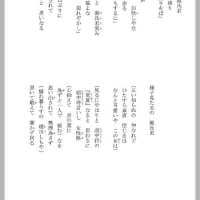
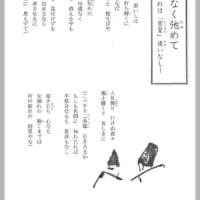

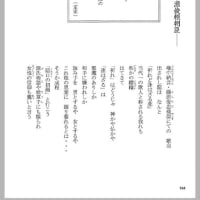
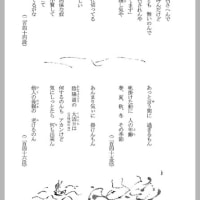
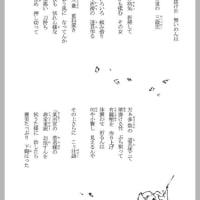
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます