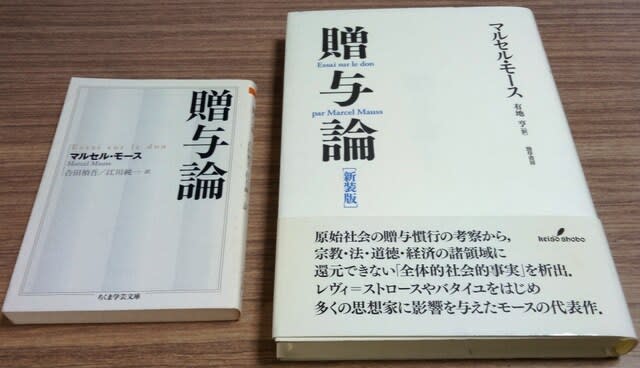
マルセル・モース/有地亨訳『贈与論』(勁草書房、1962年、新装版2008年)を読んだ。
長らく絶版(品切れ?)だった時にはものすごく読んでみたいと思っていたので、新装版が発売されるとすぐに購入したのだが、いざ手に入れてからは本棚に並べたままになっていた。
ようやく時間を気にしないで読書ができるようになり、読むことにした。
本文よりも詳細な注の方が分量が多いのだが、注はほとんど読み飛ばした。十分に理解できたとはとても言えないが、面白かった。
未開ないし原始社会において行われる「義務的贈答制」(互酬的贈答・返礼)を対象に、贈答を受けた場合に、返礼を義務づける規則は何であり、贈答品の内部に潜むいかなる力によって受贈者は返礼を義務づけられるのか、という問いに対して、モースは、ポリネシアなどの南洋諸島、アメリカ・インディアン、エスキモー(当時の用語に従う)など北米の民族誌研究の成果、さらには古代ギリシャ、ローマ法、インドの慣習などを検討することによって回答を試みる。
ものが贈与され、相手がそれを受領した場合に、返礼の義務を生じさせる力は、贈与されたものの中に存在する。贈与、受領、返礼という一連の現象は、たんなる経済的、法的現象であるにとどまらず、政治的、家族的現象でもあり(社会階級や氏族、家族にかかわる)、宗教的(呪術、アニミズムにかかわる)でもある(253頁)。
このような互酬的贈答・返礼を規律しているのは経済的要因(取引)ではなく、宗教的、呪術的、道徳的、感情的、そして法的な意義を有する「全体的社会事実」(有機的統一体、社会制度全体)であり、かかる互酬的贈答・返礼によって氏族間、家族間の安定が図られていると結論する。
要約に自信はないが・・・。
わが国の法学者でモースのこの著書を最も深く参照したのは広中俊雄教授の「契約とその保護」だが、ぼくは読んでいない。ただ法学部の初学生だった頃に幾代・鈴木・広中共著『民法の基礎知識(1)』(有斐閣)という本で、広中氏の「無償契約はなぜ要物契約なのか」という小論を読んだ。等価交換を当然の前提と考えていたぼくは、この小論で、現代社会に残る無償契約、とくに贈与の不思議さを知らされた。
現代においても、贈与は、経済的な価値の均衡が支配する売買や賃貸借などの有償契約とはまったく異なる性質を持っている。
子どもに与えるお年玉や誕生祝い、婚約の際に交換する結納や婚約指輪、寺社等に対するお賽銭やお布施、喜捨は何のためになされるのか。あるいは結婚式や就職祝いなどにおける饗宴(時として大盤振る舞い)は何のために行われるのか。これら授受されるもの、提供されるものに経済的価値しかないとは現代人も考えていないだろう。
ドイツ民法には、「忘恩行為」があった場合には「贈与」を取り消すことを認める条文があるが、この条文なども前時代の亡霊が近代民法に混入したものと思っていたが、前時代の亡霊どころではない、原始以来の人間社会の全霊がこもった規定だったのだ。
十分に理解できなかったのは、ポトラッチ、すなわち徹底した破壊行為である。
ポトラッチは、かんべむさし『ポトラッチ戦史』(講談社文庫、1979年)ではじめて知って、衝撃的印象が残ったが(「ポトラッチ」などという習俗はかんべの創作ではないかと最初は思った)、モースの中でもいくつかの事例が紹介されている。
自分自身のささやかな蔵書類の断捨離すらままならないでいるのに、自分が獲得し、保有するものすべてを徹底的に破壊しつくすなどということが如何なる心理的メカニズムによって可能になるのか、本書を読んでもぼくには理解できなかった。そんな鷹揚さはとうていぼくには不可能である。
モースは本書の最後で、この研究によって、いかにして『キヴィリタス』(civiltas)、『公民精神』(civisme)の結論に達しうるかがわかる、それを意識的に嚮導する技術こそソクラテスのいうところの「政治」(Poitique)であると結んでいる。“civiltas” には注がついていて、「市民間の権利、義務の関係がお互いに素直に認められ、それがお互に完全な程度にまで守られ、保障されている、いわば市民的な社会の理想を表現した概念」とされる(260頁、306頁)。
なお、吉田禎吾・江川純一訳のちくま学芸文庫版では、この個所は、<古い用語を再び用いるなら--「礼儀正しさ(civilite)」、また今言われているような「公民精神(civisme)」という結論をいかにして導きうるのか(が)明らかになる>と訳してある(292頁)。
これこそ、民主主義の精神、あの “virtue” だろう。
戦後の家族法学は人類学、社会学からどんどん離れていってしまったように思うが、この訳業が、穂積陳重、(台湾時代の)岡松参太郎、(初期の)中川善之助、青山道夫とつづくわが国の家族法学の水脈の一つの到達点を示す作品であることは間違いない。大学を卒業されてから10年足らず(9年目)にこの訳業を完成されたことにも驚嘆する。
有地先生とは、編集者時代に九州大学の研究室でお会いしたことがあった。米軍のジェット機が轟音を立てて低空を通過するたびに会話を中断しなければならなかった。先生は「今度は私の自宅へお出で下さい」と仰って下さった。
九大をご定年後、学会の仕事の準備で一度だけ聖心女子大学の先生の研究室にお伺いしたことがあった。軽井沢のような木立の中に低層の建物が点在する聖心女子大の構内に入ったのは、その時一度だけである。九大の研究室とは打って変わって静かな研究室だった。
それらのご恩、ご学恩に何ら応えられなかったことを恥じるばかりである。
2020年10月27日 記















