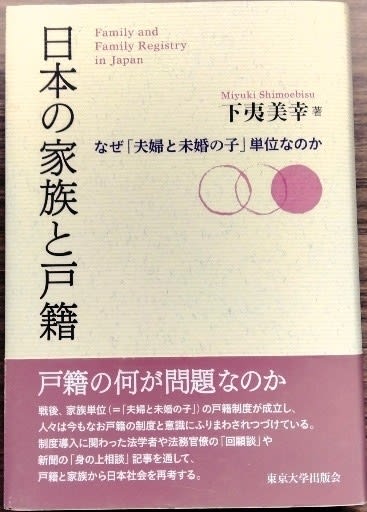「建築でたどる日本近代法史」の第8回は、旧中野刑務所。
出典は朝日新聞1983年2月23日付の記事。「消える “思想犯の獄舎” --73年の歴史、中野刑務所」と見出しがうってある(上の写真)。
記事によれば、この建物は明治43年(1910年)に着工し(?)、大正4年(1915年)に完成したようだ。戦後は米軍に接収されたが昭和32年に返還され、中野刑務所として新たに発足したという。昭和50年(1975年)に法務省が廃止を決定し、敷地12万平方メートルの一部は都と中野区に払い下げられた。800人いた受刑者は昭和57年までに他の刑務所に移され、職員も配転されたという。
建物については、「レンガ造りの十字型獄舎」としか書いてないが、「名建築の名が高」く、取り壊しを知った建築家たちが調査に訪れているという。「十字舎房」と書いたものもある。
記事に付された写真を見ると、中央に監視塔があって、その周りに数棟の獄舎が放射線状に延びる姿は、典型的なベンサムのパノプティコン(全監視)方式の監獄建築である。
記事は、中野刑務所の来歴を簡単にしか書いてないが、中野刑務所はもともとは豊多摩監獄として発足し、その後豊多摩刑務所と名称を変更した。
「思想犯の獄舎」として知られたのは、治安維持法によって左翼から自由主義者までが片っ端に投獄された戦前の豊多摩刑務所時代である。戦後の中野刑務所になってからは、建前上は「思想」を理由に罰せられることはなくなったので、学生運動の活動家が収容されたくらいである。
記事によれば、沼袋駅から200mの距離とあるから、「中野」刑務所というより、「豊多摩」刑務所のほうが地理的にも相応しいかもしれない。ぼくは豊多摩刑務所というのは、水道通りの豊多摩高校のあたりにあったのかと思っていた。
「思想犯の獄舎」と見出しをつけながら、この記事は、中野刑務所に収容されていた思想犯の名前をまったく書いていない。ネットで調べてみると、中野区立中央図書館のHPに、「収監の作家・文化人--中野刑務所 1910-1983」と題して、中野(=豊多摩)刑務所の主な収容者の紹介があった。
それによれば、河上肇(昭和8年1月~6月)、三木清(同5年7月~11月、同20年6月~9月)、小林多喜二(同5年8月~6年1月。死亡は同8年)、壷井繁治(同5年8月~6年4月、同7年6月~9年5月)、中野重治(同5年5月~12月、同7年5月~9年5月)、亀井勝一郎(同3年4月~5年春)らが豊多摩刑務所に収容されていた。埴谷雄高の名前もあった。まさに「思想犯の獄舎」である。
豊多摩刑務所に収容された思想犯の中で、一番有名なのは三木清だろう。彼は治安維持法違反で検挙、投獄され、1945年8月の敗戦によって占領軍(GHQ)が思想犯の解放を命じたにもかかわらず、人々が気づかなかったために釈放されることなく、同年の9月26日に豊多摩刑務所で獄死した。悲劇的な話である。高校生の頃、三木の『人生論ノート』を読んだが、ぼくの人生には影響を与えなかった。
中野刑務所の跡地は、現在では平和の森公園になっているとのことである。
「獄舎」といえば、長谷川尭の『神殿か獄舎か』が、ぼくの建築物への関心の始まりだったが、この本は断捨離してしまって、手元にない。「獄舎」の何が語られていたのだろう。
一時期はまっていた山田風太郎の『地の果ての獄』という明治伝奇ものは、網走監獄が舞台だった。網走監獄の囚人たちが、屯田兵と一緒に北海道開拓に従事した物語だった(と思う)。
2023年6月24日 記