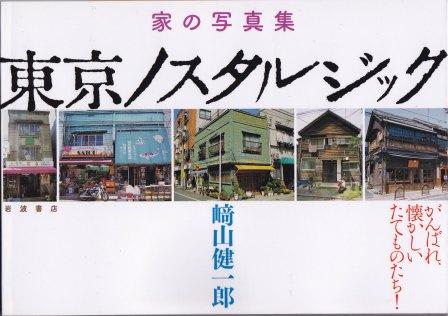川本三郎『郊外の文学誌』(岩波現代文庫、2012年)を読んだ。
川本三郎は、20代後半の頃によく読んだ作家(物書き)のひとりである。

『朝日のようにさわやかに』(1977年、筑摩書房)、『同時代を生きる「気分」』(1977年、冬樹社)、『雑エンターテイメント』(1981年、学陽書房)、『走れナフタリン少年』(北宋社、1981年)、『町を歩いて映画の中に』(1982年、集英社)、などなど。
しかし、『同時代を生きる「気分」』を読んだ時には、彼とは「同時代を生きていない」気分を感じたし、その後、『雑 ~ 』や『ナフタリン ~ 』などは文字通り「雑」な感じがして、やがて遠ざかってしまった。

・・・と書いていて気になったので、これらの本を引っ張り出して眺めてみた。
『郊外の文学誌』によると、川本は阿佐ケ谷に住んでいたらしいが、ぼくはてっきり西荻窪の住人だと思っていた。
ぼくが中学校に通っていた昭和40年頃、西荻窪駅北口には“映画館通り”という路地があって、左右に映画館が3軒並んでいた。川本の映画本の中に、確か西荻の“映画館通り”のことが書いてあったので、彼を西荻の住人と勘違いしたようだ。今回探してみても『シネマ裏通り』にわずかに「西荻名画座」という文字が出てくるだけだった。
しかし、大発見もあった。『シネマ裏通り』には“ピンク映画”の思い出がけっこう出てくるのだが、その中で、大西康子のことを、“忘れもしない「網のなかの女」”と書いているのだ。ぼくだって「忘れもしない大西康子」、同姓同名のクラスメイトがいたのだ。「網のなかの女」も「100万人の夜」か「近代映画別冊」でスチール写真を見た。
マリリン・モンローよりジェーン・マンスフィールドのほうがいいとも書いてある。これも同感。彼女が来日した時に「週刊プレイボーイ」か何かに掲載された彼女のグラビア(確か三つ折りの大きなカラー写真だった)をもっていたはずなのだが、どこかにしまいこんで見つからない。

『シネマ裏通り』は表紙のカバーがフェリーニの“道”というのもいい。できればアンソニー・クインがジュリエッタ・マシーナを置き去りにするシーンだともっと良かったが。
『雑エンターテイメント』も、当時隆盛を極めていたサブカルチャー雑誌に書いた原稿を集めたので「雑」と冠したらしい。たしかにいろんな雑誌があった。自分のことを「フリーの売文業者」と書いている。

前置きが長くなったが、『郊外の文学誌』に戻ろう。
『郊外の文学誌』は近代東京の「郊外」を舞台にした小説、「郊外」に移り住んだ作家を辿った随筆(?)である。「文学散歩」というのは一段格下の文章とみる筆者の考えに従うと「評論」なのかもしれない。
そんなことはともかく、この本は面白かった。
文学のことは分からないのだが、何といっても、自分の身近で思い出深い場所や地名がたくさん出てくるので。
ちなみに、この本に出てくる「郊外」は東京の郊外に限られる。しかも、大部分は中央線(というよりかつての甲武鉄道)の沿線、飯田橋から、大久保、中野、阿佐ケ谷、荻窪あたりまでで、それに蒲田、青山、八王子あたりの話も少し出てくる程度である。
東京では、関東大震災と東京大空襲を2つの画期として、市中や下町を追われた人々が大量に東京の西部に移動したが、かれら「小市民」の暮らしぶりを郊外に移住した作家の伝記や作品の中にたどって行く。
「郊外」の定義も難しい。
要するに「東京」ないし「(旧)市中」さらには「東京市」などに対立する概念である。だが、「山の手」と一致するわけでもない、「田園」とも「武蔵野」とも違う(288頁)、「田舎」「片田舎」「ムラ」でもない。「辺境」のニュアンスはあるがたんなる辺境でもない。「場末」とも違う。
いずれにしろ、「郊外」が指す地域は、時代が下るとともに次第に西へと移っていく。
漱石の時代には大久保も飯田橋も「郊外」なら、青山も「郊外」だった。やがて「中野」あたりが「郊外」になり、結核病みの作家が療養生活を送っている。そういえば中野には肺結核専門の国立中野療養所があった。
そして、関東大震災と郊外電車の開発によって、阿佐ケ谷、荻窪が「郊外」になり、「境」「三鷹」「小金井」も「郊外」になっていく。
釣り人などが雑踏する二子玉川を避けて、永井荷風が「鄙びた」(!)田園調布を散策する記述なども印象的だ。
意外だったのは、東京の西部の人間にとっては東の方は全部「下町」だと思っていたのだが、もともとは日本橋界隈だけが「下町」で、墨田、江戸川、葛飾など、東京の東にも「郊外」があり(283頁)、しかも西の「郊外」と同様に東に延長していったという(293頁)。これらの地域は「新下町」などと呼ばれることもあったらしい(299頁)。
小津安二郎の「風の中の雌鶏」や「東京物語」に登場する荒川放水路周辺も「郊外」だそうだ(285頁)。
八王子、横浜、鎌倉など、「郊外」が拡がるはるか前から発展していた東京の西部や西南部の町との関係や、旧市中のお屋敷街の来歴も知りたくなった。
ぼくの個人的な関心としては、「郊外」の住人たちが、持ち家だったのか、借家暮らしだったのか、それが当時の貨幣価値でどのくらいだったのか、それが小説家の私生活や作品にどう反映されているのかなども、近代日本の寄生地主の土地所有や不動産賃貸借(貸家資本)の実態などに興味があるぼくとしては知りたいところである。

上のようなことを調べる必要があって、末弘厳太郎『農村法律問題』(農文協、1977年。最初の改造社版は大正13年)を読んだのだが、同書には次のような記述がある。
「大正十年借地法が施行されてより此方、同法施行区域たる東京及び隣接町村に於ては借地を求むる者のみ多くして、土地を買はんとする者は寧ろ減少し、又之と反対に大地主にして土地の売却を希望するもの多きに拘らず、之を賃貸せんとする者が一般に減少した。・・・建物保護法と借地法とに依って借地権が法律上きわめて強固のものとなった以上、巨費を投じて所有権を取得せんよりは、其の資本は之を別途に利用して利益を得つつ、其利息の中より借地料を支払ふことにする方が遥かに利益である。」
あるいは、水本浩『借地借家法の基礎理論』(一粒社、1966年)によれば、「わが国における借地人層は都市の中間層(厳格に見れば中間下層と労働者上層が多い)が主であった。日本資本主義は、先進諸国の帝国主義への移行期において体制的スタートを切ったために、・・・早急に巨大資本の形成を見たかたわら、封建的諸関係がかなり広汎に持ち越された・・・。そのような後れた面を反映して、部厚く零細企業が滞留せしめられるとともに、生来の無産労働者ならざる小資産者的サラリーマンおよび労働者が大幅に生み出されたのであった。このような社会階級的基礎の上に、木造という比較的安価な建築様式が手伝い、・・・自己住宅や小営業のための小面積借地が広汎に成立してきたのである。」
「わが国の借地人層は、・・・勤労大衆の位置を占めてきた」。「中間層の中でも、その上部(中間上層)は自己所有地における小住宅所有者層であったのであるから、借地人層は、中間層(中間下層)の下部が主な部分であった。」という記述にも出会った。
分かりにくい、というか実感しにくい文章なのだが、幸いに小津安二郎のいわゆる「小市民」映画を見ていたので、時代の雰囲気を伺うことはできた。
川本の本に、文士(売文業者)の収入(原稿料)や住居の所有形態、購入費用などが書いてあったら助かったのだが。
2012/3/27 記