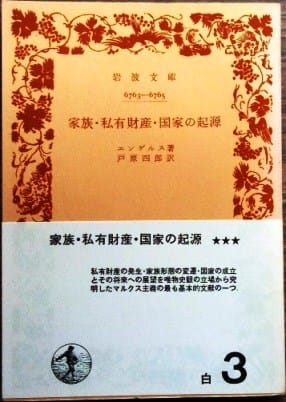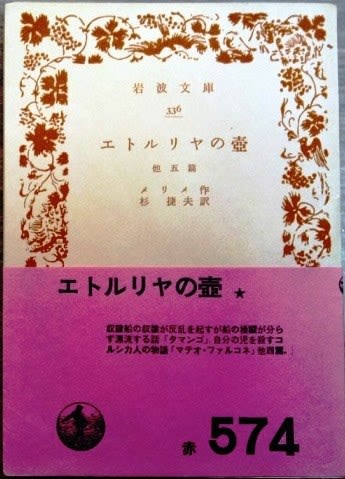羽仁五郎『都市の論理――歴史的条件・現代の闘争』(勁草書房、1968年)を読んだ。
以前の書き込み(江守五夫著『結婚の起源と歴史』)ですでに触れたことだが、ぼくは大学に入学したばかりの1969年の春から初夏にかけて、羽仁五郎『都市の論理』とエンゲルス『家族・私有財産・国家の起源』の読書会に短期間だけ参加した。
羽仁五郎『都市の論理』(1968年)は、発売当時ベストセラー書に名を連ねるほど売れていて、学生の間でも流行していた。ぼくはハードカバーを買ったが、その本は友人に貸したら返ってこなかったので、今は手元にない。
現在手元にあるのは、ペーパーバック版で、奥付には1979年3月発行、第31刷とある。10年ほど前に神田神保町の古本屋(今はなくなってしまった篠村書店)の店頭で見かけて買ったもので、裏表紙に50円と書いてある。新刊が売れたから、古本も安値で大量に出回っているのだろう。書き込みや傍線はないし、小口の汚れもなく、元の所有者が読んだ形跡はまったくない。
ぼくが参加した読書会は、もともとは羽仁『都市の論理』を読むために始まったのが、羽仁の本に触発されて『起源』を読むことになったのだと思う。羽仁は、『起源』を「アトラクティブ」で「スマアト」な本として高く評価し、エンゲルスを(1960年代当時の)ちょっとばかりかっこうのいい最近の学者など及ばないスマートな学者と評している。
その時は、結局、羽仁『都市の論理』を読み通すことはできず、エンゲルス『起源』も第6章で断念してしまったのだが、50年近くを経て、今回、改めて『都市の論理』を最初から読むことにした。『起源』の第6章以降もいずれ読もうと思う。前半よりも後半のほうが面白そうである。
今回読み返してみると、『都市の論理』は『起源』の読み方を指南する本ではなく、むしろ、『起源』の間隙を埋める本であり、羽仁の『都市』(岩波新書、1949年)を補完、補強する本と言えそうである。基本的には、マウレル(Maurer)という歴史家の『ドイツ都市法制史』全4巻という本に依拠しているようで(144頁)、Maurerと『都市』が頻繁に引用されているが、羽仁の博識と「自由都市」や「解放」、「反独占資本」への熱い思いが印象的である。
本書は、もともとは「地域」ないし「コミューン」における精神医療をめぐる勉強会から出発したというが、羽仁自身は、「コミュン」や「コミュニティ(地域社会)」という概念は非学問的として排斥しており、用いられるべきは「都市」ないし「(都市)自治体」であるという。
※ちなみに、羽仁がエンゲルス『起源』を引用する個所では岩波文庫版のページ数が書いてあるのだが、ぼくの持っている岩波文庫(戸原四郎訳)のページと照応していない。調べると、岩波文庫版の『起源』には1930年代に発行された西雅雄訳(1946年改訳版)というのがあったらしい。そっちのページ数なのだろう。手元の戸原訳では照合できなくて困った。後に西訳の1946年版も入手したが、これのページ数とも照応していなかった。1930年代の最初の西訳からの引用らしい。
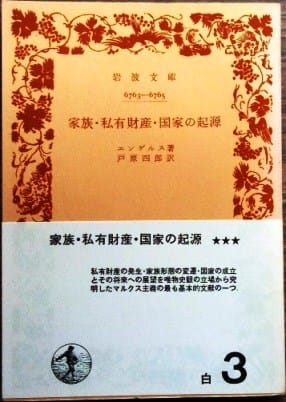
羽仁のエンゲルス解釈によれば、原始的な人間社会が破壊されて、私有財産制、一夫一婦家族が生まれたが、それがプロレタリアートによって回復される過程の最初に現われたのが都市であり(101頁)、原始共産社会と、来たるべきより高次の共同体との中間段階において原始的な社会を回復しようとするのが「都市」である(93頁)という。
そして、エジプト、ギリシア、アテネ、ローマなどの古代都市の隆盛と(それらの都市が基礎とした奴隷制の限界による)崩壊、フィレンツェ、ヴェネツィアなどルネサンス時代の自由都市の勃興、そして三十年戦争(と自由都市内部に発生したツンフト組合員や市会議員・評議員の地位の世襲などの腐敗)によって自由都市が崩壊し、農村に残っていた封建制を基礎とした絶対王政が成立し、ついで、絶対王政を打倒したフランス革命によって全国規模で自由都市共和政連邦が成立したという羽仁の歴史観が語られる。
自由都市で実現した家族からの解放、地域(農村)からの解放が、フランス革命によって全国的規模で市民に及んだが、解放された市民の中から有産者階級(資本家)と無産者階級(労働者)の分化が生じた。有産者による支配から無産者を解放する最初の革命が1848年の二月革命であり、1877年のパリ・コミューンは、階級闘争の場としての都市の可能性と政治組織の方向性(三権分立ではなく、執行委員会と人民裁判所による人民主権)を示したという(353頁~)。
ーー以上、『都市の論理』に何が書いてあるかを要約しようと試みたが、うまく書けなかったのは、羽仁の話が飛躍するためもあるが、要するにぼくの理解が足りないということであろう。以下は、部分的に印象に残ったことをアトランダムにいくつか。
かつての職場の近く、九段坂を上りきったあたり、靖国神社の向かい側に大村益次郎の銅像が立っている。「なぜここに大村が?」と不思議に思っていたが、羽仁によれば、上野に立てこもった彰義隊を維新革命軍が九段から砲撃して撃退したのだが、その革命軍の司令官が大村だったという。九段から上野の山は遠くはないが、そう近くはない。歩いたことはないが、本郷の東大赤門までが30分くらいだから、徒歩で1時間程度だろうか。大砲が届く距離だったとは意外である。その大村は明治2年に暗殺され、翌3年には民兵組織であった奇兵隊が弾圧され、その後、竹橋事件、秩父事件を弾圧し、最後に幸徳秋水の大逆事件をでっち上げたのが山縣有朋であり、この巡査出身の警察政治家が近代日本の方向を誤らせたと羽仁は言う(183頁)。
家(家族)は家父長的支配の場であり、最初の階級闘争は一夫一婦制家族における男と女の戦いであったという記述も見られるが、他方で、家には権力から個人を守るアジール(避難所)という役割もある、ヨーロッパの石造りの家は住居不可侵の象徴であるともいう(225-6頁)。その例として、メリメの『マテオ・ファルコネ』が出てくる(172頁)。父親が匿っていた革命軍の兵士を、懐中時計欲しさに政府軍に売り渡してしまった息子を父親が銃殺してしまう話を、羽仁は家の不可侵性のエピソードとして紹介するが、ぼくはあの話は家父長制的なイタリアの父親による「生殺与奪の権」の実例として読んだ(下の写真は「マテオ・ファルコネ」が入ったメリメの『エトルリヤの壺』)。
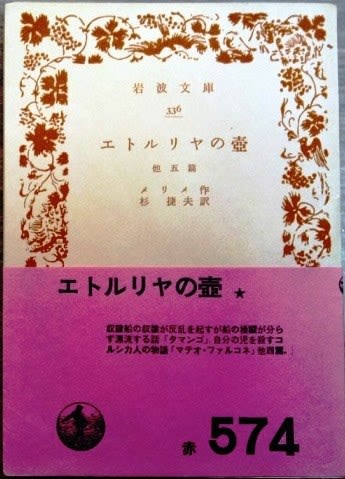
「試験地獄」(当時はこんな言葉があったのだ!)まで独占資本が原因だと、あらゆる社会悪が独占資本によるものとされている。独占資本と政府の癒着が様々な社会悪の原因であるのは間違いないだろうが、「試験地獄」にはもっと様々な要因があっただろう。
都市自治体に司法権を与えるべきだとして紹介される、自由都市の都市裁判所や(154頁)、陪審制などは、この本を読んだ影響だろうか、ぼくは行政法のゼミで、条例違反事件は自治体の裁判所を創設して、そこで裁くべきだと提案したこととがあった。伊佐千尋さんと倉田哲治弁護士らが立ち上げた「陪審裁判を考える会」にも参加した。
ぼくが住んでいる練馬区は、当時(1968年ころ)、水道普及率26%、下水道0%!、ガス36%で、いずれも都内最低、練馬区は「東京のチベット」(!)と言われたいたそうだ。そんな状態でありながら、区民会館の建設に12億円もかけようとしていると批判されている(388頁)。確かにぼくが練馬に引っ越した1960年には、プロパンガス、汲み取り便所、水道は私設だった(水道は現在も私設)。わが家の風呂は薪をくべてから石炭を焚いて沸かしていた。ぼくは1回100円の小遣いで、小1時間釜の前にしゃがんで風呂を沸かした。
羽仁未央、左幸子など羽仁の家族とのエピソードも出てくる。ベストセラーになる本は「私小説的」な要素が必須であると誰かが言っていたが(清水幾太郎『論文の書き方』に関してそう言っていた)、『都市の論理』にも私小説的というか個人的エピソードが結構出てくる。本書の中には家族からの解放への言及が頻出するが、羽仁にとって「家族からの解放」は切実だったのだろう。参議院議員時代の検事総長(一高で同級生だったと書いてあったので、調べると佐藤藤佐だった)との問答、羽仁の都市論を褒める手紙をよこした(マルクス主義歴史学者だった頃の)林健太郎のことなど。ただし、小泉信三、田中耕太郎、横田喜三郎、磯村英一、今井登志喜、江藤淳など、登場人物はみな過去の人になってしまった。上原専禄、高島善哉は登場するのに、「都市」といえば言及されて当然と思われる増田四郎が出てこないのはなぜなのか。
大学生になった1969年の初夏、高校時代の恩師を相模湖のお宅に訪ねた折に、羽仁の『都市の論理』を読んでいると話したところ、先生は、「おれの兄貴も兵隊に行くときに『ミケランジェロ』を持って行ったな・・・」と独り言のように仰った。羽仁には時代の若者に訴える力があったのだろう。
エンゲルスが目ざし、羽仁が目ざした自由で平等な社会はいまだ実現していない。むしろ独占資本は当時よりいっそう独占化し、人民の不平等-格差は拡大するばかりである。自由も怪しくなっているが、これからの時代を「俯瞰」して、(とくに若い)人々に影響力をもつ思想家は現れないのだろうか。
2021年2月5日 記