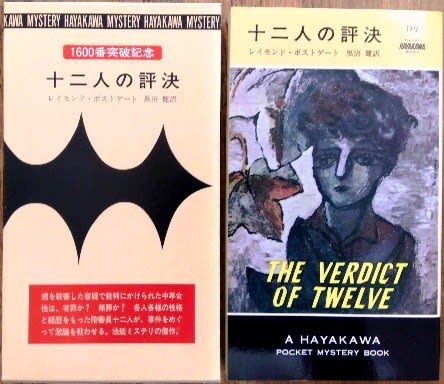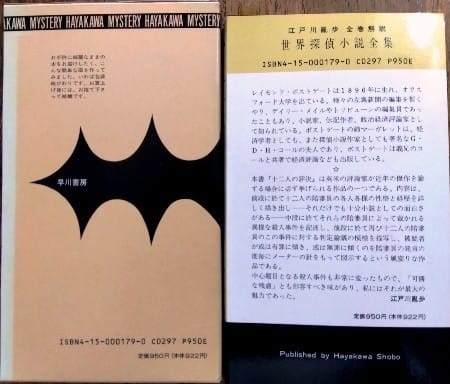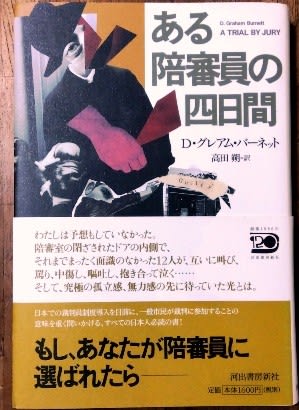伊藤純・伊藤真『宋姉妹--中国を支配した華麗なる一族』(角川文庫、1995年)を読んだ。
著者が「NHKスペシャル番組部チーフ・プロデューサー」という肩書であとがきを書いているところを見ると、NHKスペシャルか何かで放映された番組の制作過程での副産物なのだろうか。
たまたま、昨夜(9月27日(水)深夜)のNHKテレビ「映像の20世紀」(?)で、中国政治を動かした中国人女性をテーマにした番組を放映していた。文革前後から以降は、ぼくの同時代史を反芻することができて面白かった。それをきっかけに、本書をひっぱり出してきて、斜めに読んで断捨離することにした。
「映像の20世紀」は清朝末期の西太后から始まって、宋靄齢(あいれい)、宋慶齢、宋美齢の3姉妹、江青(毛沢東の妻)、王光美(劉少奇の夫人)、紅衛兵だった何とか彬彬という女性、そして蔡英文(宋美齢の設立した基金によって若き日に英国留学したそうだ)らの数奇な運命をたどる面白い内容だった。
上海の資産家一家に生まれた宋姉妹、長女の靄齢は財界人に嫁ぎ、次女の慶齢は孫文に嫁ぎ、三女の美齢は蔣介石に嫁いだ。
宋慶齢は孫文の中国革命(辛亥革命)の遺志を継いで最後まで中国の民主化(三民主義)を志向し、共産党に近い位置をとったが、文革時代には冷遇されたものの周恩来の庇護を受け、最終的には中国国家名誉主席の称号を与えられて亡くなる。
一方蔣介石に嫁いだ宋美齢は、抗日戦争時代には国民党総裁である夫を支え、堪能な英語力と社交性をもってアメリカからの支援を得るために奔走し、成果も挙げた。
昨夜のテレビによると、戦勝後のアジアのあり方を討議するために、連合国側のチャーチル、ルーズベルト、蔣介石が集ったカイロ会議では、宋美齢も蔣介石の通訳として陪席したが、後にチャーチルは、「印象に残ったのは宋美齢だけで、蔣介石は何をしゃべったのかまったく記憶にない」と語ったそうである。
カイロ会議で3人の首脳が並んで座った写真は有名だが、実はチャーチルの右隣りには宋美齢がちゃんと座っていたのである! 彼女がトリミングされてない映像も出てきた。
国共内戦に敗れ、蔣介石とともに台湾に敗走した宋美齢は、後にアメリカに永住し、中国大陸に戻ることはなく、台湾から英米への留学生を支援する基金の運営などに当たった。本書出版の時点では健在だったようだ。その後100歳を超えて亡くなったように記憶するが、晩年は、国民党政府による(中国)本土回復に非協力的になったアメリカ政府に不満を抱いていたようだ。
宋慶齢の死去に際して中国政府は靄齢、美齢姉妹にも招待状を送ったが2人が列席することはなかった。
毛沢東の後妻に収まった江青が、夫の威をかって文革時代に暴虐行為を繰り返したことは有名な話だが、昨夜の番組によると、江青の感情を突き動かしたのは、劉少奇夫人王光美に対する嫉妬心だったようだ。王光美は英語、フランス語など5か国語を操る華麗なファースト・レディだったらしい。それが江青の嫉妬心に火をつけ、残虐な仕打ちに出たようだ。
江青は死刑判決を受けながら、執行されることなく獄中で病死したように記憶していたが、昨夜の番組によると獄中で自殺したのだった。
本書の読後感だか、昨夜のテレビ番組の感想だか分からくなってしまったが、中国近代史に宋姉妹をはじめとする何人かの女性の活躍があったことは確かであり、宋慶齢、宋美齢、王光美、蔡英文らが優秀な女性だったことも確かだろうが、中国人女性が一般に政治的に有能といえるかは疑問である(江青や紅衛兵だった何某を考えよ!)。
宋姉妹の活躍は、実家の莫大な資金力と、結婚した配偶者(孫文、蔣介石)の政治的、カリスマ的力量によるところが大きかったように思う。純粋に個人的な実力によって地位を築き上げたのは(昨夜の番組に登場した女性のなかでは)蔡英文だけではなかったか。
2023年9月29日 記