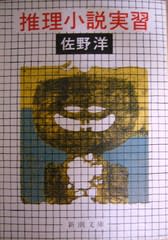内田康夫『軽井沢殺人事件』(角川ノベルス)を、ブック・オフ店頭の105円コーナーで見つけた。
数ヶ月前だったら決して手にすることのない本だが、(確か)軽井沢在住の多作作家がどんなものを書いているかを知りたくて買って帰った。
当然軽井沢を舞台に、豊田商事事件と東芝のココム違反事件とを下敷きにしたような事件を、探偵浅見何某と“信濃のコロンボ”が解明する。
昭和62年刊とある。
当時を記憶するぼくらの世代なら読み通せるが、今では通用しないのではないか。
ストーリーなんかどうでもいい、軽井沢の雰囲気を味わうことができれば十分という人なら、それなりに読めるだろう。
塩沢湖界隈がテニス民宿だらけになったのがいつ頃だったか記憶にないが、この小説に軽井沢高原文庫が登場するから、昭和62年にはあの文庫がすでに建っていたことがわかる。
離山のことをもっと描いてほしいところだった。どうせ“ご当地小説”にするのだったら。
表紙カバーの左下に描かれたシルエットが、この小説のいう「西南西西」の方角から見た離山なのだろう。
どちらかといえば離山の「西南西西」に住んでいるが、このような離山は見たことがない。少し南への偏りが足りないのかもしれない。
* 写真は、内田康夫『軽井沢殺人事件』(角川書店、昭和62年)の表紙カバー。古い本だったので、読んでいるうちに72ページと73ページの間で無線綴じがガバッとはずれてしまった。
2009/7/27