かって経営資源としてあげられてものは、「人」、「モノ」、「金」であった。最近はこれに「情報」や「知識資本」を加えた5つが経営資源としてあげられることも多いようである。 今日紹介する「あたたかい組織感情」(野田稔/ジェイフィール: ソフトバンククリエイティブ)は、さらに第6の経営資源として「組織感情」をあげ、その重要さを説いたものである。
この本では2つの興味深い手法が紹介されている。「組織感情マップ」を使った「自分感情と組織感情の分析」と「リフレクション・ラウンドテーブル:RRT」による「内省と相互コーチング」だ。
「組織感情マップ」というのは、組織の感情状態を把握・分析するためのツールである。これを作成することにより、自分感情や組織感情の現状が把握でき、目指すべき方向とのギャップが把握できるという優れものだ。しかし、残念なことに、本書の説明を読みながら実際にマップを作ろうとするといろいろと立ち止まらざるを得ない。例えば、質問の答をどのように数値化してレーダーチャートに乗せるのか、どこが感情崩壊ラインとの境界線となるのかといったようなことだ。また、組織感情マップのイメージ図をみるとおそらくミスプリだと思うのだが、本来4つの別々の感情が記載されるべきところ、右側の2つの感情と左側の2つの感情に同じものが記載されており、本文の説明や図中のレーダーチャートの項目と合致していないところがあるので、読者に戸惑いを与えるかもしれない。
「リフレクション・ラウンドテーブル:RRT」については、更に興味深い。色々な企業から参加者が集まるようなセミナーに参加するとグループ討議なるものをやらされる場合が多いが、どうも時間の無駄といったような思いをすることも多い。色々な企業から集まってきた者が、それぞれ業種も立場も問題意識も違うのに、仮想のケースをわいわいがやがや話しあってどれほどの教育効果があるのだろう。講師の時間稼ぎのようなもので、これだったらまだ講義を聴いているほうがずっといいというような思いをしたことはないだろうか。しかし、このRRTは違う。同じ組織の中で、同じような目的を持った者同士が内省と相互コーチングを繰り返して、自分たちで成長していく手法だからだ。本書には、そのためのノウハウも詳しく説明されている。
最近は、米国のサブプライム問題に端を発する経済の停滞により、職場の雰囲気もギスギスしがちになることも多いことだろう。しかしこんなときだからこそ、「組織感情」ということについて改めて考え、企業としての活力を盛り上げていくべき時期ではないかと思う。そのために、本書は有益な指針となり得るのではないだろうか。
なお、この本は、ソフトバンククリエイティブ社さまより献本いただいたものです。ありがとうございました。
*** この記事は姉妹ブログ3館共通掲載です。 ***
(応援クリックお願いします。) ⇒
「時空の流離人(風と雲の郷 本館)」はこちら
「本の宇宙(そら)」(風と雲の郷 貴賓館)はこちら
この本では2つの興味深い手法が紹介されている。「組織感情マップ」を使った「自分感情と組織感情の分析」と「リフレクション・ラウンドテーブル:RRT」による「内省と相互コーチング」だ。
「組織感情マップ」というのは、組織の感情状態を把握・分析するためのツールである。これを作成することにより、自分感情や組織感情の現状が把握でき、目指すべき方向とのギャップが把握できるという優れものだ。しかし、残念なことに、本書の説明を読みながら実際にマップを作ろうとするといろいろと立ち止まらざるを得ない。例えば、質問の答をどのように数値化してレーダーチャートに乗せるのか、どこが感情崩壊ラインとの境界線となるのかといったようなことだ。また、組織感情マップのイメージ図をみるとおそらくミスプリだと思うのだが、本来4つの別々の感情が記載されるべきところ、右側の2つの感情と左側の2つの感情に同じものが記載されており、本文の説明や図中のレーダーチャートの項目と合致していないところがあるので、読者に戸惑いを与えるかもしれない。
「リフレクション・ラウンドテーブル:RRT」については、更に興味深い。色々な企業から参加者が集まるようなセミナーに参加するとグループ討議なるものをやらされる場合が多いが、どうも時間の無駄といったような思いをすることも多い。色々な企業から集まってきた者が、それぞれ業種も立場も問題意識も違うのに、仮想のケースをわいわいがやがや話しあってどれほどの教育効果があるのだろう。講師の時間稼ぎのようなもので、これだったらまだ講義を聴いているほうがずっといいというような思いをしたことはないだろうか。しかし、このRRTは違う。同じ組織の中で、同じような目的を持った者同士が内省と相互コーチングを繰り返して、自分たちで成長していく手法だからだ。本書には、そのためのノウハウも詳しく説明されている。
最近は、米国のサブプライム問題に端を発する経済の停滞により、職場の雰囲気もギスギスしがちになることも多いことだろう。しかしこんなときだからこそ、「組織感情」ということについて改めて考え、企業としての活力を盛り上げていくべき時期ではないかと思う。そのために、本書は有益な指針となり得るのではないだろうか。
なお、この本は、ソフトバンククリエイティブ社さまより献本いただいたものです。ありがとうございました。
*** この記事は姉妹ブログ3館共通掲載です。 ***
(応援クリックお願いします。) ⇒
「時空の流離人(風と雲の郷 本館)」はこちら

「本の宇宙(そら)」(風と雲の郷 貴賓館)はこちら













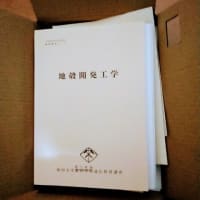













わたしも読みました。
会社の雰囲気を良くするためのコンサルティング会社の本でしたね。
確かに、管理職同士で語り合う場があってもいいかとは思いますね。
セミナーなどで時間稼ぎでやられるグループ討議は、スキルも知識も違う者同士、なかなか有意義な討議は難しいような気がします。