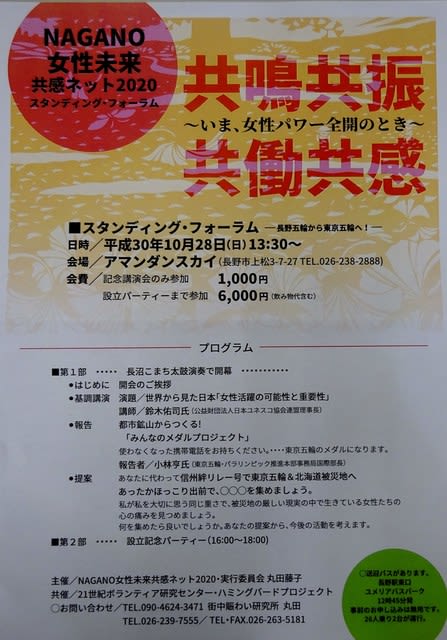3/30 Sat.
この日 「犀川南マレットゴルフ場愛護会総会[役員会]」 が行なわれ、後段の懇親会の場にカオを出させていただきました。
以前も触れましたが、かかる 「犀川南マレットゴルフ場」 については、私自身が初期の造成の頃から深く関わっており、いわゆる 「生みの親」 の一員となっていました。
その後も施設の維持管理には、陰に陽に協力させていただいていたしたが、一昨年に私が不祥事により議員を辞職したこともあり、とんと疎遠になってしまっているのです。
今回の晴れの18ホール拡張についても、陰ながら祝意を表するに止まっており、何というか 今までは 「身内同然」 であった愛護会ですら、すっかり敷居が高くなってしまっているのでした。
そんな中での愛護会総会でしたが、ありがたいことに、一部の役員さんがわざわざ連絡をくださり、この際だから ぜひ出席するようにと促され、馳せ参じた次第です。
私が着いた頃は 既に宴もたけなわ、各位は互いにこれまでの労をねぎらい合ったり、竣工した新18ホールの攻略法などに話しの花を咲かせていました。
そこへ私の入室ということで、話しの腰を折ってしまうのではないかと思いましたが、あにはからんや 参加のみなさんは歓待してくださり、中には握手を求めてくれる方も。
そのうえで、現在会長を務める H さんは「おかげさまで18ホールの拡張ができ、それも 以前 「開墾」 ともいえるご苦労を重ねた倉野さんたちの先人の努力があったからこそと思っています。
この施設はここまで発展しましたが、新たな課題も散見されるので、倉野さんにはまた以前のように力を発揮してもらいらいものです。」 と述べてくださいました。
今日の会合においては、ろくでもない経緯を踏んだうえにご無沙汰をするも、長い空白時間を経てもなお、相変わらずのご厚情をいただいたことに感謝の念が堪えないところでした。
そのうえで、さっそくに課題のあることをを伝えていただき、そこには単なる 「お久しぶり!」 で済まされない、これからもしっかり地域貢献せよとのご示唆をいただ感、私に課せられた期待と責務のようなものがにじみ出ているのを実感しました。
まさに 「身の引き締まる思いがする」 時間でもあったのでした。
近所の梅の老木に、今年も花芽がついていました。

歳を重ねてもなお「現役」であり続けるその姿に、凛々しささえも感じるところでした。

・