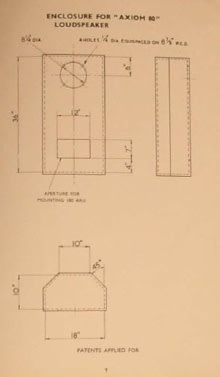オーディオの近況報告です。長くDENONのDL103でステレオ盤を聴いてきましたが、一関のベイシーでステレオ盤を聴いてから再度SHURE V15type3を聴きたくなり一度手放したカートリッジを買い直しました。また交換針も純正のVN35E、VN35Eの後年のタイプであるVN35MR、日本JICO製のVN35E用針ならびにスイス製pfanstiehl社の4764-DE針も予備として入手して聴き比べしてみました。以下は私の寝惚け耳と機器での聴感比べ報告です。
一番上の写真のが純正のVN35Eの写真で交換針にはSHUREとVN35Eの白文字となります。

二番目の写真、左から順番に純正のVN35MRでSHUREも文字は赤ベースに白文字、VN35MRは白文字となっています。真ん中が国産JICO製の針でSPECIAL TRAKINGの文字がシルバー地に黒文字印刷されたシールが貼られている。右がスイス製交換針で文字は全く無く味気ない交換針となっている。
純正VN35E=聴いた感じは純正のは申し分ない再生音でメリハリがあり力強さに溢れている。ドラムの音は特に迫力ある再生音を聴かせてくれる。純正のVN35Eで聴くインストものはかなり迫力があってベイシーの音に多少は近づいたような気がします。ただし女性ボーカル物には元気がありすぎて僕としては相応しくない。所有の女性ボーカル盤は大部分がモノラル盤なのでまずステレオで聴く事はないのですが念の為に少ないステレオ盤を聴いた。入手価格は未使用であればまず2万円以上はする。現在はまだオーディオ専門店やYオークション等で入手できる。
純正VN35MR=TYPE3より発売年は新しい針でVN35Eが入手難となった頃に代用的に使用されていました。VN35Eと比べると細部の表現はよく再現され遜色ないが、全体的に音がおとなしく上品になる。ハードバップには不向きでむしろクラシック向きではなかろうか。聴いていないがボーカル物には良いかも知れないので試す価値はあるように思える。後日の楽しみとします。この交換針は懇意なショップから2万弱で譲ってもらった品。
国産JICO製交換針=VN35Eに近づけた楕円針。値段は4千円~9千円という価格帯。純正針の3分の1か5分の1という値段だが純正針に近い音がする。あえてケチをつけると各楽器の分離度が多少劣るように思うのと高音が伸びきれないような気がする。が水準には達しているので純正針が入手できなくなれば僕はこの国産交換針を使うだろう。
スイス製交換針=もっとも安く求められる交換針で3千円~4千円で入手できる。再生音は低音から高音までまずまずの再生をしてくれるが、分離能がおとりステレオの各楽器の位置が不安定に感じる時がある。
*追記****
 もう一つの交換針を載せるのを忘れていたので追加します。実は素性を良く知らないのですが聞きかじりでは純正?或いは純正に近い?という事で確かな事は僕は知りません。当時の秋葉原で純正として売られていたような気もしますが不確かです。僕がSHUREを使っていた最後にはこの針を使っていたような気もしますが、これが入手難になってVN35MRを使ったが気にいらず、結果としてSHUREから離れていったように思います。上記写真はその交換針を装着したものですが、シルバー地に黒文字でSHUREとSUPER TRACK"PLUS"と表記されたシールが貼られています。先日はYオクで1万3千~5千程度の値で落札されていたように記憶しています。再生音はVN35Eに限りなく近く黙って聴かされれば違いは僕には分かりません。手持ちのは針ガードのガードが斜めに傾いているのが写真でも分かると思いますが針は盤に対して正しく接しています。
もう一つの交換針を載せるのを忘れていたので追加します。実は素性を良く知らないのですが聞きかじりでは純正?或いは純正に近い?という事で確かな事は僕は知りません。当時の秋葉原で純正として売られていたような気もしますが不確かです。僕がSHUREを使っていた最後にはこの針を使っていたような気もしますが、これが入手難になってVN35MRを使ったが気にいらず、結果としてSHUREから離れていったように思います。上記写真はその交換針を装着したものですが、シルバー地に黒文字でSHUREとSUPER TRACK"PLUS"と表記されたシールが貼られています。先日はYオクで1万3千~5千程度の値で落札されていたように記憶しています。再生音はVN35Eに限りなく近く黙って聴かされれば違いは僕には分かりません。手持ちのは針ガードのガードが斜めに傾いているのが写真でも分かると思いますが針は盤に対して正しく接しています。
一番上の写真のが純正のVN35Eの写真で交換針にはSHUREとVN35Eの白文字となります。

二番目の写真、左から順番に純正のVN35MRでSHUREも文字は赤ベースに白文字、VN35MRは白文字となっています。真ん中が国産JICO製の針でSPECIAL TRAKINGの文字がシルバー地に黒文字印刷されたシールが貼られている。右がスイス製交換針で文字は全く無く味気ない交換針となっている。
純正VN35E=聴いた感じは純正のは申し分ない再生音でメリハリがあり力強さに溢れている。ドラムの音は特に迫力ある再生音を聴かせてくれる。純正のVN35Eで聴くインストものはかなり迫力があってベイシーの音に多少は近づいたような気がします。ただし女性ボーカル物には元気がありすぎて僕としては相応しくない。所有の女性ボーカル盤は大部分がモノラル盤なのでまずステレオで聴く事はないのですが念の為に少ないステレオ盤を聴いた。入手価格は未使用であればまず2万円以上はする。現在はまだオーディオ専門店やYオークション等で入手できる。
純正VN35MR=TYPE3より発売年は新しい針でVN35Eが入手難となった頃に代用的に使用されていました。VN35Eと比べると細部の表現はよく再現され遜色ないが、全体的に音がおとなしく上品になる。ハードバップには不向きでむしろクラシック向きではなかろうか。聴いていないがボーカル物には良いかも知れないので試す価値はあるように思える。後日の楽しみとします。この交換針は懇意なショップから2万弱で譲ってもらった品。
国産JICO製交換針=VN35Eに近づけた楕円針。値段は4千円~9千円という価格帯。純正針の3分の1か5分の1という値段だが純正針に近い音がする。あえてケチをつけると各楽器の分離度が多少劣るように思うのと高音が伸びきれないような気がする。が水準には達しているので純正針が入手できなくなれば僕はこの国産交換針を使うだろう。
スイス製交換針=もっとも安く求められる交換針で3千円~4千円で入手できる。再生音は低音から高音までまずまずの再生をしてくれるが、分離能がおとりステレオの各楽器の位置が不安定に感じる時がある。
*追記****

















 ">
"> ">
">