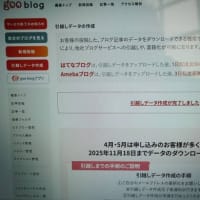龍源寺間歩までは上り坂だから帰りは下りとなって幾分は楽に、それでもこれだけ歩くと汗をかく。折り返しの最初はまだ山道の延長で建物などは何も無い、かなり下ってくると神社やお寺があったらしい場所になって、その先からは人家が疎らに現れてくる。さらに人家が多くなってやや古い街並みらしくなってきて、暫くでやっとバスを降りた中間点近くに、ここには五百羅漢が祀られる岩窟があったが、今回は古い街並みを中心に時間を使おうと、ちょっとだけ回り道して道路側からの写真を撮っただけで、またメインの街並みの方に戻ってしまう。
 向かい側の羅漢寺で拝観料を払って川向かいの洞窟内に
向かい側の羅漢寺で拝観料を払って川向かいの洞窟内に
 左手が五百羅漢像を祀る場所、中が岩窟となっているという
左手が五百羅漢像を祀る場所、中が岩窟となっているという
 道路側には一部が見える、これらを祀ったのは過酷な労働で短命だった鉱夫達の冥福を祈ってということも有ったのだろう
道路側には一部が見える、これらを祀ったのは過酷な労働で短命だった鉱夫達の冥福を祈ってということも有ったのだろう
中間点手前からはお土産屋などの店も多くなって、ここらからが地図にあった街並み地区の見どころとなっているようだ。その手始めに見つけた店は胡麻豆腐の製造販売をしているらしい中田商店、脇道には民芸品や銀製品などをお土産として売っている店も、ほかにも観光客を意識した設えの家々が連なるように並んでくるようになった。
 古い街の中にはこういう民芸品などを扱う店や銀製品を扱う店が多かった
古い街の中にはこういう民芸品などを扱う店や銀製品を扱う店が多かった
 塀に鳩の左官彫刻を乗せた家が1軒
塀に鳩の左官彫刻を乗せた家が1軒

 魚屋の文字もある看板なのに胡麻豆腐だけの店で、店先には金魚とメダカの水槽鉢があって青いメダカが珍しくて聞いたら、これらの青、赤、白、黒の4種類のメダカは珍しい種類で高いんだそうだ、こんな淡水魚の商売では魚屋とは言わないと思うがねぇ。胡麻豆腐好きの女房は、今日帰るなら保冷スチロールに入れていけば大丈夫というのでお買上げ、帰ってから数日間に渡って食べたが問題ありませんでした、かなり胡麻風味が強い味でしたよ。
魚屋の文字もある看板なのに胡麻豆腐だけの店で、店先には金魚とメダカの水槽鉢があって青いメダカが珍しくて聞いたら、これらの青、赤、白、黒の4種類のメダカは珍しい種類で高いんだそうだ、こんな淡水魚の商売では魚屋とは言わないと思うがねぇ。胡麻豆腐好きの女房は、今日帰るなら保冷スチロールに入れていけば大丈夫というのでお買上げ、帰ってから数日間に渡って食べたが問題ありませんでした、かなり胡麻風味が強い味でしたよ。
中間点付近からはこれまで以上にズラリと古くて重厚な建物も混じる家並みが続くようになって、伝統的建造物保存地区はここからが本番のようだ。その手始めにあるのが群言堂で道の両側にカフェ併設の石見銀山本店と物販だけの店が合い対してあった。バスで配られた案内マップでこの店の場所を見つけて、間歩を見たあとはここに一番立寄りたいと言っていた女房は、店に足を踏み入れたからにはこりゃ当分は出てこないでしょうな。
 左右に群言堂の店が
左右に群言堂の店が
 群言堂石見銀山本店
群言堂石見銀山本店
 入ったところがオブジェ展示ロビーみたいな場所になっていて、外との仕切りは開けっ放しでツバメが出入りし、中にはちょうど具合がいいと巣を作っていたが、この店らしい計らいですかね
入ったところがオブジェ展示ロビーみたいな場所になっていて、外との仕切りは開けっ放しでツバメが出入りし、中にはちょうど具合がいいと巣を作っていたが、この店らしい計らいですかね
 ツバメの巣に雛が既に、これから巣作りらしいツバメもいたが
ツバメの巣に雛が既に、これから巣作りらしいツバメもいたが
 奥がカフェ
奥がカフェ
 中はかなり広くてコの字型の建物配置で、中庭もいい感じに
中はかなり広くてコの字型の建物配置で、中庭もいい感じに
 一番奥には生地売場もあって、これには女房はもう買わずにはおられないと、バッグにしたいからと趣きのある生地を買っていた、今回はあまり買わなかったからいいですよ。
一番奥には生地売場もあって、これには女房はもう買わずにはおられないと、バッグにしたいからと趣きのある生地を買っていた、今回はあまり買わなかったからいいですよ。
さらに古い街並みが続いていく、冒頭写真も。
 街並み
街並み
 街並み
街並み
次に立寄ったのは有馬中栄堂という店で、この一軒だけで作っているという銀山の鉱夫も食べたと宣伝して試食販売していたげたのはというお菓子、珍しいからとこれも女房がお土産にと。
 銀山の鉱夫も食べていたというこの地だけだというげたのはというお菓子を売る店が、確かに不思議な食感と味わいで話題にはなるね。
銀山の鉱夫も食べていたというこの地だけだというげたのはというお菓子を売る店が、確かに不思議な食感と味わいで話題にはなるね。
街並みの最期にはまだ白い漆喰や赤い石州瓦が奇麗で、復元工事からまだそんなには年数がたっていないと思われる立派な造りの建物があって、その先の旧代官所跡までで街並み地域の散策は終了となる。
 右手は一番立派な屋敷の熊谷家住宅で、代官所御用を勤めて銀を扱う最も有力な商人だったと、真新しい石州瓦屋根と漆喰壁で修復されていますね
右手は一番立派な屋敷の熊谷家住宅で、代官所御用を勤めて銀を扱う最も有力な商人だったと、真新しい石州瓦屋根と漆喰壁で修復されていますね
 内部は有料だが外からも一部が見られるようになっている
内部は有料だが外からも一部が見られるようになっている
今回の石見銀山見物の最終集合地点が代官所跡まで来たところにある駐車場で、ここでも集合時間の10分ほど前にバスが回送されてくるようになっていて、皆さん遅れることなく御無事で時間通りに次への出発となった。
 代官所跡は石見銀山史料館として再整備されている
代官所跡は石見銀山史料館として再整備されている
 史料館では関連資料の展示に今回の特別展示は杉田玄白著の解体新書とあった
史料館では関連資料の展示に今回の特別展示は杉田玄白著の解体新書とあった