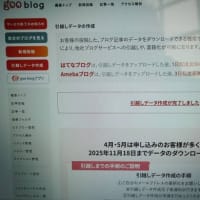数日前に龍の図柄の皿をいくつかと、漆器盆や飾り物で以前に紹介したものを再度リンクさせて紹介したが、まだガラクタも含めて残りもかなりあるから、追々と合間に書いていくつもり。
今回のは唯一僕の浜松の実家にあったもので、こんなものがあったとはついぞ知らなくて、父が死んで母を引き取って実家を始末した際に、押入れみたいな造り付け棚の奥から見つかったもの。引越しのために残った家財を整理、持っていくのと処分するのを選分けていた女房が見つけて、大声をあげたものだ。
ものは印判もので明治ぐらいのものだと思われるが、大きさが尺にはちょっと足りないが、厚めの深い丸鉢で、口縁は玉造り、裏にも縁取二重線が入って堂々としたものだ。模様の見込側の花みじんこと裏側の唐草は定番ではあるが、全体の形はこれまでに見たことが無いし、これだけの大きさのドッシリとしたのは少ないのでは。ということでこれは伊万里じゃなくて瀬戸のものかもしれない。

母に聞いたら、戦争で飛行場があった浜松は艦砲射撃などで丸焼けになり、疎開先から戦後すぐに今の家を建てて戻る際に、食器類などもロクなものはないだろうからと親戚から送られたのだそうだ。僕が幼稚園に入る前の小さい頃は使っていたらしいが、段々に食器類も揃ってきてからは大きいものだから出番が無くなって、それで僕の記憶には無かったのだ。
ということで唯一これだけが親から譲られた器だから大事に使おうと、正月などに筑前煮をドーンと盛り付けていたが、最近は家族数が少なくなってしまって仕舞われたままとなっている。
ほかにも浜松から持ってきたのは欅一枚天板の卓袱台、桐和箪笥、火鉢、昔の学校使いの椅子、薬用天秤精密秤などなど、それに今ではレトロな昭和の雰囲気がするものいくつか、それらは今でもインテリアにはしているが、明治生まれの父親は分家だったから由緒あるものは無い。中では卓袱台は食事にだけでなく、僕の小学校時代の勉強机だったこともあって、懐かしいものだ。

空き部屋に置いた卓袱台にこんなガラクタを並べて
今回のは唯一僕の浜松の実家にあったもので、こんなものがあったとはついぞ知らなくて、父が死んで母を引き取って実家を始末した際に、押入れみたいな造り付け棚の奥から見つかったもの。引越しのために残った家財を整理、持っていくのと処分するのを選分けていた女房が見つけて、大声をあげたものだ。
ものは印判もので明治ぐらいのものだと思われるが、大きさが尺にはちょっと足りないが、厚めの深い丸鉢で、口縁は玉造り、裏にも縁取二重線が入って堂々としたものだ。模様の見込側の花みじんこと裏側の唐草は定番ではあるが、全体の形はこれまでに見たことが無いし、これだけの大きさのドッシリとしたのは少ないのでは。ということでこれは伊万里じゃなくて瀬戸のものかもしれない。

母に聞いたら、戦争で飛行場があった浜松は艦砲射撃などで丸焼けになり、疎開先から戦後すぐに今の家を建てて戻る際に、食器類などもロクなものはないだろうからと親戚から送られたのだそうだ。僕が幼稚園に入る前の小さい頃は使っていたらしいが、段々に食器類も揃ってきてからは大きいものだから出番が無くなって、それで僕の記憶には無かったのだ。
ということで唯一これだけが親から譲られた器だから大事に使おうと、正月などに筑前煮をドーンと盛り付けていたが、最近は家族数が少なくなってしまって仕舞われたままとなっている。
ほかにも浜松から持ってきたのは欅一枚天板の卓袱台、桐和箪笥、火鉢、昔の学校使いの椅子、薬用天秤精密秤などなど、それに今ではレトロな昭和の雰囲気がするものいくつか、それらは今でもインテリアにはしているが、明治生まれの父親は分家だったから由緒あるものは無い。中では卓袱台は食事にだけでなく、僕の小学校時代の勉強机だったこともあって、懐かしいものだ。

空き部屋に置いた卓袱台にこんなガラクタを並べて