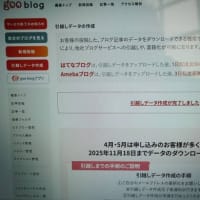2日目はまだ行ったことの無かった昭和村経由で柳津に寄り、時間によっては会津若松か喜多方を廻って次の宿のある猪苗代町に向かうことに。宿から程近くにスーパー風の店があったので、花泉の金瑞祥というのを仕入れる。南郷村から昭和村にでる401号線は山道ですれ違い出来ないようなかなり細い部分が各所にあり、数台ほどしか擦違わなかったけれど地図で見るより時間的には掛かってしまって、大回りするのも大変そうだしで、こんなことにも山奥に来たんだということを実感することになった。
平地に出てまもなくで最近出来たばかりというからむし織の里(販売所と展示館がある)があって寄道することに、期待せずに入ったのだがここで一つ教えられたことがある。からむしとはイラグサ科の多年草で、あの高価な宮古上布も同じ繊維だそうだと、こちらのものは越後上布や小千谷縮の材料として生産出荷されていたものだという。昨日買ったのは今時のもので麻が使われていて、昔の本物にはからむし以外のものは小千谷縮とは言わなかったのだとは初めて聞いた。ここで売っていた上布は、昔は二流品の糸で自家用に織っていた技術が残っていため今でも作れるのだとか。宮古上布や昨日に見た越後上布と同じような細かな絣織の非常に薄い生地は、本当に細い糸を使っていてお値段もここでも同様に一反150万円ぐらいと高価なもの、これは手間を考えると当然のことらしい。こちらでは今は若い織姫さんを全国から募集してからむし織の伝統を維持していて、最近は応募者が多くて選考が厳しいとも聞いた。
この日は編籠の実演と体験があるらしくお爺さんが籠を編みだ始めた最初に出くわし、展示していた胡桃皮の手提籠(籠は一個だけあって値段を訊いたら思いのほか安いぞと)とランプの笠や花入の外籠に使っても良いなと思ったマタタビ蔓の粗い円筒状籠とを7000円と1500円で、また竹笊籠の小さいのを800円で購入してしまった。帰ってから東京で見かけた胡桃籠は30000円以上もしていたから安い買物でしたねぇ。建物の外に出ると少しばかりのキノコをこれも売り始めたところで、天然のナメコ1パックが300円、香りがある原木マイタケは200gという嬉しいお値段で手に入れることができ、帰ってのマイタケ御飯とナメコ味噌汁が楽しみじゃと、米も清流米を買込んだことだし旨い飯が食えるぞとニンマリ。ここは捏ね鉢や編籠など概して今まで見たなかでは一番安いのでお薦めだ。
 からむし織の里
からむし織の里
 からむし織の里販売所店内
からむし織の里販売所店内


上布の見本が置いてあった 今回買った編物細工三つ
さらに道を北へ進めば、金山町では玉梨豆腐茶屋に立寄り、評判らしい青ばと寄せ豆腐500円を買い、家までは持って帰れないので途中で喰うことに。これも風味があって良かったが醤油が無かったのが残念至極、おまけで貰った豆腐ドーナツは軽い味わいでこれもことのほか旨く、今度来た時は是非お土産に買いたいものだね。
 玉梨豆腐茶屋
玉梨豆腐茶屋
昨日のR252号線にやっと戻ってくればすぐにこぶし館というのがあった。食堂と物産販売コーナーに加えて民俗資料館があり、資料館では展示の一つにこの地方の家屋の建て前の風習写真と説明が付けられた大きい藁人形があり、それがどんなものかは是非一見を、見れば分かるウッシッシものですぞ。
柳津では女房が是非ということで、かねてから行きたかった版画の斎藤清美術館へ、この地は版画家の故郷で、晩年を過ごしたということで美術館が出来たんですね。以前に会津若松で展覧会を見てこれは素晴らしいと思い、一度日本橋三越で2点だけ見た時には欲しいけれど高くて変えず、その後は出会えなかったものを昨年栃木の画廊で偶然見つけ、稔りの会津シリーズというのの一枚をまずまずのお値段で買うことが出来たのです。この実物は今回は展示されてはいなかったものの、同じ絵の印刷版があって販売していた。ペンキ屋から画家、そして安井曽太郎の白を基調とした版画を見て感動し版画の道へと、独自に90歳を過ぎる迄活躍したその絵は、会津の風景シリーズが特に有名であるが、今回は女と花がテーマとなっていた。他にも猫シリーズが幾つか展示されていて、単純な構図に画家出身の何かがあって、油絵にはない味わいで、版画ならではの素晴らしいものになっている作品を鑑賞できましたよ。
 斉藤清美術館
斉藤清美術館
 稔の会津シリーズの一つ
稔の会津シリーズの一つ
腹が減ってきたがすぐ近くに川に向かって懸崖造りになっている七日堂裸まいりで有名な虚空蔵菩薩を祀る円蔵寺があるので立寄り、参道にある(江戸末に寺が焼け今後そんな災難に)泡ないようにというコジツケ気味の名物粟饅頭と栗1個入った饅頭を買って、日保ちのしない粟饅頭の方を間食。そのあと会津坂下に入って道沿いに搗きたての餅と蕎麦を食べさせるみやま茶屋というのがあったので、やっと遅めの昼と白い更科系のざるを食べる。これは後で知ったのだが柳津の美術館近くに旨い蕎麦屋があったんだそうで、残念でしたね。
 斉藤清美術館から圓蔵寺方面を
斉藤清美術館から圓蔵寺方面を
時間はまだあるので、湯川町にある奈良時代法相宗の学僧で、かの最澄と論争した徳一上人が開いた勝常寺に寄ってみたが、今は寂れた寺で、宝物館には国宝の薬師、日光、月光の3体を含め12体が納められているとのことだが、拝観時間なのに誰もいない有様であった。そこで会津若松は明日にして、喜多方の方に大回りしていこうと北上、市役所の休日無料駐車場へ車を入れる。
喜多方では休日だからもう3時近くというのにラーメンマップを手に目的の店で食べようという客が街をぞろぞろ、有名店はどこも行列、町中広いところは駐車だらけと、最近は朝早くにやってきて7時頃からやっているまことや坂内で食べていたのでこれには唖然。僕が始めてここに来た20年前はラーメンの町を売出し始めた頃で、確か人気のまこと食堂でも一杯350円でタオルのお土産付きだったと記憶する。今日は昔一度食べただけで煮干の匂いが強烈だった大安食堂で醤油550円を注文、前のような匂いは少なく、喜多方風より背油の多めな焦がした苦味のような重さがあるので聞いてみたら、煮干は昔のままだがやはり背油を多くしている由、目黒の勝丸のスープに似た感じが幾分入っている。横浜ラーメン博物館に出店していたので交流があったのかな。
 まこと食堂の行列
まこと食堂の行列
これまでに僕が食べたラーメンのうち4店のものを以下に。


まこと食堂 大安食堂


源来軒 はせ川(塩)
あとは市内に9軒あるうちの女杜氏の経営する蔵元清川に立寄り、酒造りの井戸水は今回は谷川ICで調達したので汲まずに3年古酒の太左衛門酒<現在はこの銘柄は造っていない>だけを買う。そのあと蓮沼製麺でパックラーメンを求め、駅の西側に新設された道沿いにある漆器店を2軒ばかり覗いて、陶磁器や風鈴、飾り物なども置いている店の方で、飾り棚などのディスプレーにするミニチュアの福猫5匹セットと桐下駄グッズを買っておく。喜多方はラーメンだけでなく漆器や桐製品などの工芸品も有名だが、何と言っても蔵の町と呼ばれていて、街中に多くの蔵があるのに道路側からは歩道屋根や店看板などで見えなくなっていて存在が分からないものが多い、でも裏に入れば立派な蔵が見られるし、煉瓦造洋風蔵などもあってちょっと離れた三谷地区が煉瓦造では有名である。それらを見学してさらに街中心部では会津若松にならった北方のれん会なる名店会があったはずで、それに参加している老舗の店なども廻ってみるのも良いのでは、そういえば市北部には温泉もあって、道の駅には市営の公衆温泉蔵の湯も出来ている。
 北方風土館も蔵元
北方風土館も蔵元
 駅前から馬車が<今でもあるかな>
駅前から馬車が<今でもあるかな>
宿へは来る時に塩川迄の帰り道方向が混んでいたので一本東側の抜け道を南下、そのあとはいつも通る会津若松北側の地方道を東に走って夕方5時には宿に到着。ナビはこういう時には便利ですねぇ。
さて今日の温泉旅館も、ある所からの情報を得て予約した悠ゆ亭という客室5部屋の小さな宿。予約を入れた数日後にテレビ東京の小さな名旅館の番組に出てしまい、最近は休前日は3ヶ月前迄一杯とのことだ。気さくな主人と女将と到着後すぐのコーヒーサービスで話していたら、5年前脱サラで始めたのだが、出身がなんと僕と同じ浜松でそれも歩いて20分程の所、生まれは一つ下で高校は別であったが、またここに来る前住んでいたのが横浜の我家から車で30分もかからない向ヶ丘遊園の民家園近くだったとのことで、これにはすっかり話がはずんでしまった。
 悠ゆ亭外観1
悠ゆ亭外観1
 悠ゆ亭外観2
悠ゆ亭外観2
ここは客室が少ないので風呂は一つだけ、一巡するまでは順番で入り、あとは扉が開いていれば24時間自由にという方式。やや大きめの石造りの浴槽はゆったり、ぬるめの弱食塩石膏泉は柔らかくジックリ浸かっていられ、久しぶりに女房に背中を流してもらうこととなった。
さてカウンター、囲炉裏、テーブルに分かれての食事は地のものをなるべく使った懐石風と蕎麦の料理で、主人が試行錯誤して作り出したものとか、季節で内容は変るそうだが本日の献立は
ジュンサイとキゥイの酢の物
ホタテと蕎麦実の山椒入焼甘味噌和えとエビと蕎麦実の甘酢和えの小鉢2つ
蕎麦の田楽(粳粉を混ぜて練って串にして焼く、これが旨い)
岩魚の囲炉裏での串焼
(これは木島平のグルービーの囲炉裏で長時間ジックリコンガリと焼きあがったものの方が上ではあるが)
米沢牛のタン塩串焼(田楽風仕立てでカウンター裏の炭火コンロで焼くのがグッド)
蕎麦豆腐
蕎麦すいとん(鶏の出汁が濃厚でいいぞ)
蕎麦粉と実の団子風揚物
最後は十割蕎麦の手打実演付き(今までで一番硬く歯ごたえがあって盛岡冷麺みたい、僕はもう少し田舎風の二八のほうがいいな)、デザートも蕎麦の実入りフルーツシロップ掛け、あとは蕎麦湯で仕上げというものであった。酒は地元の稲川の冷酒を、すっきりした中にも味わいのある酒でこれもいける。夜7時半から2時間弱の泊り客全員での和気あいあいの食事であった。なおこの後の季節はキノコ料理がメインになるそうで、次はその時期を狙おうかな。料金は休日前料金で11000円と、これはトイレが無い部屋ばかりだからではあるんだけど。
 囲炉裏席もある
囲炉裏席もある
 主人は蕎麦打ち中
主人は蕎麦打ち中
翌朝は8時半から食事ということで、朝風呂のあと散歩で坂道を登って青年の家の方まで歩く。途中の森林の脇にはトリカブトが咲いているのには、目の前が猪苗代湖でもここらの土地自体は山の中なんだと。猪苗代湖を望む高台、今日も天気は最高で景色の中の田園の色付きが鮮やかで、このシーズンは緑の林の先に畦で区切られた稲穂の黄色がまさに稔りの会津の斎藤清の世界だと、僕は紅葉の赤よりむしろ好きな風景なのですよ。(冒頭写真は猪苗代湖のほうから見た磐梯山である)
朝食は粕漬鮭の焼物がメインで納豆、海苔、湯豆腐、生卵、味噌汁、漬物と日本の正しい食事、御飯がまた美味しいので聞くと、これも土地の米には拘っているとか、そういえば同じく会津米に拘った鰻のゑびやでは確か炭火で炊いてあって旨かったのを思い出した。食後はコーヒーが出ておしまい。この宿は蕎麦アレルギーの人や子供連れ向きではないけれど、我々などにはまた来ようという気を起こさせてくれるもてなしであったなと。ただ、ゆっくりしてもらいたいということは分かるけれども、早起きで先を急ぐ人のことも考えて8時前からの食事にしてもらうと好都合なのだが、全員が揃ってという建前を守っているとなると難しいですかね。