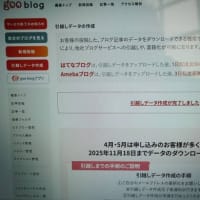9月前半の山荘周辺の草花の二回目も雑草類が中心であるが、一部は庭にも侵入してきているぐらいの見慣れたものも、これらは一回目のものも含めて犬の散歩コースで写真に撮ったものばかりだが、そんな狭い範囲内でも日当たりと日陰、野原と水辺というように植物にとってはそれぞれの環境に合った場所で懸命に生きているのを知ることができる。
山荘の庭でも周辺でも繁殖力が強くて群落になってしまうのがミズヒキで、ほとんどが赤い花なのだが一部には白花もあって、これは山荘の庭の隅にあった白花のミズヒキである。近くには赤花もあるのだがもう間引いている。冒頭写真はこのミズヒキ付近から枝垂桜の下などに繁茂していた雑草取りをした後の写真、残す野草をチェックしながら全て手作業でやるから意外と大変なのですよ。

ゲンノショウコは至る所に勢力を伸ばしていて、現の証拠というように胃腸薬として効き目がある薬草だというが、今は利用しているという話は聞かないから単なる雑草にすぎない存在となってしまったようだ。この花も白とやや赤みを帯びたものがあるが、下の写真は白花で、種類としてはフウロソウの仲間というが、大きさも色でもアサマフウロなどとは比べ物にならない地味な花だ。写真の奥のほうにはツユクサの花も見える、これももう雑草となって繁茂する。

軽井沢の花という古い図鑑でタカアザミとあったアザミで、これは水路沿いに大きくなっていたがやや湿っている日当たりがいい場所が適しているらしい。人間の背丈ほどもあって、花はやや下向きに咲く。

まだ蕾の段階だが、花がアザミに似た感じになりそうな背の高い植物を見つけて調べたらセイタカトウヒレンというらしい、葉はアザミとは全く違う感じだが、アザミにも近いキク科の植物とあった。周りの雑草に負けずに背を伸ばしたが高くなり過ぎて、この写真のように横向きになってしまったという姿になっている。今までここで見たことは無かったのだが、昨年に周りの樹木を切っていてそれから大きくなったらしい。

蕾を見つけてから咲くまでを9日も待ったのに遂に花を開かなかったのはアキカラマツ、図鑑で調べたら花は地味でそんなに期待するものではないらしい。全体に有毒性があるというが薬草でもあるらしくて、毒も少なければ薬になるということですか。同じような葉は各所で見られたが、花蕾を付けていたのは少なかった。

黄色い小さな花が半日陰に咲いているのに気が付いて、調べたらナガミノツルキケマンらしい。ケマンソウは春に咲くものとばかりに思っていたが、これは秋に咲く種類らしい。タイツリソウや高山植物の女王のコマクサも同じ仲間だとあったが、これはあくまでもヒッソリと咲いていた。

8月末から咲きだし今真っ盛りなのがツリフネソウ、8月にはこの白花という珍しいのを見つけてアップしたが、水辺に多いがやや湿気た場所にも進出し、赤と黄色の花が競い合っているのを各所で見ることができる。これだけ繁茂しているのに花持ちはしないから、切花にはならないのが残念だね。

水辺に見られるのが以下のオタカラコウ、アケボノソウ、ミゾソバ、アキノウナギツカミなど、この中ではアケボノソウはそんじょそこらで見られるというものではないようだ。
タカラコウにはオタカラコウとメタカラコウが図鑑にあったが、これは葉の形が丸くまとまっていて尖った部分が無いのでオタカラコウらしい。昨年はもっと早くに咲いていたと記憶するが、今年は9月になってから咲き始めた。

アケボノソウはこの水路のもっと上流の日陰で見つけたことがあるが、今回はそちらではまだ見られず、その代わりに下流の場所の日なたで何株かが多くの花を咲かせていた。きっと上流から種がこちらに流れ着いて、条件よろしく成長したんでしょうな。遠目にはただの小さ目の白い花だが、よく見ると花弁の斑模様が奇麗だ。


水辺に繁茂するのがミゾソバと、アキノウナギツカミという変な名前の草で、下の写真のように混生している。花はミゾソバの方は白でやや大き目、もう一方はやや赤みを帯びたやや小さ目の花だが形は似ていて一見ソバの花みたい。アキノウナギツカミはザラザラすろ剛毛があって、ヌルヌルするウナギも容易に掴めるだろうということからの命名らしい。雑草と言ってもこれだけ盛んに咲いていると、目に鮮やかに飛び込んでくる。



ミゾソバ アキノウナギツカミ