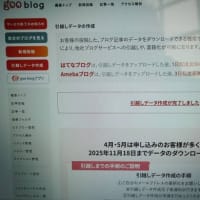台風15号の影響が土曜日はまだ無く雨は降らないということで、ここ数年9月に続けてとなる栃木は花之江の郷の女郎花を見に行くことに。ただ今日は遅めに出たので途中は栃木花センターに寄り、栃木市内で食事、花之江の郷を見たら帰るという予定で、佐野ラーメンや宇都宮餃子までは廻らなかった。佐野のラーメン屋も喜多方を見習って朝から営業すれば、早くから出かけて周辺の見所に寄道しながら夜は宇都宮の餃子までと、ぐるっと廻るという魅力の旅ができるのにと、県の観光関係者に言いたいですね。
朝9時少し前に出発、首都高速がまあまあ空いていたので、10時30分頃には佐野インターから近くの岩舟町にある栃木花センターに着いた。ここは春のカタクリ自生で有名な三毳山公園の東側にあり、山野草も森の中に植込んで整備が進められているほか、農産物直売所もあって繁盛している。花センターでは春と秋は地元山野草愛好会のいくつかのグループによる展示会と即売があって、見事な展示品のように手塩をかければなるであろう素材の草花をかなり安く買うこともできる。そう言えば岩舟山野草自慢会なる愉快な名前のグールプの展示会もあったっけ。祖母に頼まれていたので野ぶどうの鉢500円、小型なサワギキョウ400円を買ってみたがはたして育てられるかねぇ。ガーデニング用苗などもシーズンにはたくさん売っているし、一般園芸店よりは多少とも珍しいものも置いており、展示会の方も年間予定ができているようなので、植物好きな方は催し物を確かめて出かけられては如何でしょうかね。


栃木花センターの春の花壇 園芸植物直売所


山野草展示会の様子で左は即売コーナー、右は見事な展示品
昼近くなったので次は栃木市に向かう。途中の道沿いは大平町のぶどう団地なるものがあって、脇道までぶどうと梨の栽培農家のもぎ取り直売所が並んでいる。ぶどうは巨峰が主体で山梨のように中央高速の渋滞でゲンナリするくらいならこちらの方はまだそんなに混雑していないので穴場である。
栃木ではこの前続けて成都酒家の四川料理だったので今度は和食をと、旅館が昼だけやっているかな半に入ってみた。メニューは少ないがちょっと品の良い味わいのある料理で、女房ともども雅弁当1530円を頂く。実はこれが一番高い料理で刺身、揚物、煮物その他の盛込み、小鉢に御飯と味噌汁、果物のセットで男性には軽めの量、女性なら十分といったところだろう。そのあと市内を少し散策、屋台会館ができたり隣接の三連蔵も改装され蔵の町美術館となり、中心街路は昨年整備が終わって綺麗になって、川越、佐原と同じく小江戸として、蔵や巴波川沿いの風情とともにこじんまりながら趣ある町ではある。東京芸大出の漆芸家が同級生などの作品を含め販売しているギャラリーみうら(平成15年に閉店)や益子の作家物などを現地より安く売っているギャラリーぜん(成都酒家を教えてもらった店)には来れば必ず立寄る。またこれから行く花之江の郷を作った和菓子屋もめん弥の本店では、来店者にはお茶と菓子のサービスがある。がんこ職人の和菓子のキャッチフレーズで都内デパートにも出ているが、ここでは昔はお茶も本当のお薄が供されて初めて行った時はびっくりしたものだ。なお駐車場は中心街に有料があるが、土日は市役所の駐車場が無料なのでそちらに入れ、歩いて鯉の泳ぐ用水路や明治の木造洋館庁舎なども見て街ブラするのがオススメ。もともと栃木は川を利用した舟運の最上流中心地として栄えた町だそうで、5年に一度の祭は今年は11月17、18日にあり見事な山車もでるという。


巴波川沿いで
 かな半の雅弁当
かな半の雅弁当
花之江の郷は市街から栃木インターを越えた都賀町にあり、もめん弥が運営している山野草を中心にした自然植物園で、この手の施設では箱根湿性花園が一番だと思っているが、個人の施設としては立派の一語である。特に秋の今頃は女郎花が有名で、これにミソハギが一面に生えた湿地帯の中を大勢の客が訪れている。今年はミソハギはもう終わりかけで、両方が同時に盛りだった一昨年のような場面は幸運な年だったのかも。それより僕はここでは池に可憐に咲く睡蓮の一種アサザの黄色い花(冒頭写真)が好きで、これだけは箱根よりもっと多くの花が咲き誇って見事なもの、この花は毎日咲き終わるというから一体どれくらいの花が咲くんだろうか。園内の入場料は800円、山ゾーンと湿地ゾーンがあり約1時間ほどかけて園内巡りをし、さらに園外では山野草の販売もしているので気に入った物を求めるのも良いのでは。
 ミソハギ
ミソハギ
 オミナエシ
オミナエシ
この近辺は植物好きにはまだまだ見所も多くて、春先4月初めにはこのすぐ近くにもカタクリとアズマイチゲが自生している場所があって、そちらは無料である。でもこういう所はアマチュアカメラマンが近接撮影しようとロープ内に足を踏み入れていたりして、いい年こいてみっともなく情けない光景だけは何とかならないでしょうかね。ほかには出流蕎麦で有名な所や神主が経営しているという柏倉温泉などはまだ行ってないので、まだまだ日帰りで気楽に訪れたい所だ。その際は佐野のラーメン、宇都宮の餃子も旅程に組み入れたい。このラーメンと餃子コースの別ルートとしては鑁阿寺の足利や大川美術館などがある桐生、さらに渡良瀬渓谷まで廻って宇都宮まで出る強行軍向きの旅があって、これにはフランス料理を昼にというもう一つおまけ付きも考えられる。さらに毎月第一土曜は桐生で骨董市もあり、これらはまたの機会に紹介したいもの。骨董市と言えば城下町館林でも町興しに開催されるようになったらしく、この町のつつじが岡公園と分福茶釜の茂林寺、白鳥飛来の多々良湖だけは知っていたが、最近出来た館林美術館の建物と景観も有名になっているようだから足を伸ばすところも増えた。この館林と足利、さらに群馬に入った桐生や利根川の南側埼玉県の加須はうどんでも有名だったよな。
帰りは日光の紅葉シーズンなど混雑するシーズンを避けた時期なので東北道自体はそんなでもなかったのだが、首都高だけは箱崎あたりはいつも混雑するので場合によっては向島で降りてしまった方が正解ということもあり、途中の渋滞の距離表示に注意して行かないとね。
店データ
店データ
とちぎ花センター 岩舟町下津原 1636 0282-55-5775
花之江の郷 都賀町大柿 1312 0282-92-8739
かな半 栃木市万町 5-2 0282-22-0108
もめん弥 栃木市倭町 2-18 0282-22-7400

(今回の軽井沢では草むしりに精を出したり、周辺に出歩いたりしていてパソコンに向かう時間が少なくて、こちらでのことについては今後時間を見て書く予定である)