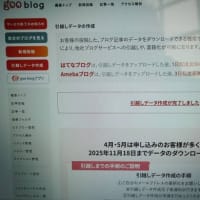今回も帰りのバスの集合時間の午後2時40分までの時間の使い方を、湯本駅まで出て街歩きしてみることに。チェックアウトは10時となっているが、湯本駅までの無料バスの第一便が9時45分というのでそれに間に合わせて済まして、大きな荷物だけはクロークに預けて出発。この二日目の昼間の過ごし方はホテルに残るとなると午後1時半まではショーはないし、宿泊棟の温泉は朝9時から午後2時までは掃除タイムとなってしまうから、朝は早くから入れる露天の与一と全館のオープン時間からとなる大プールで遊ぶか一般のスプリングパークでということになる。そのために前日のチェックインでは二日間有効の入場券が渡されたが、温泉にはもう何回も入ったしプールもねぇと、それにこの日は寒さが緩んでいたこともあってほぼアテがなくとも古くからの温泉地をブラついてみようかと。
ハワイアンズから湯本駅までは10分ほど、乗り合わせた宿泊客のほとんどはJR駅の利用のようだったが、老夫婦の一組だけは我々同様に湯本温泉街の散策ということのようであった。まず最初に駅併設の観光案内所で近くに地元のスーパーがないかと訊いたら、駅の反対側へ陸橋を超えてすぐにあるというが、地元産のいい魚は小名浜まで行かないと買えないだろうということであった。以前に干物を買ったことがある老人夫婦がやっていた小さな魚屋があったはずと、今でもまだやっているかと訊いてみたら鶴のあし湯のもっと先にあったかななんて覚束ない返事に、それではダメ元とまずはスーパーから回ってみることに。
 陸橋から湯本駅を
陸橋から湯本駅を
陸橋に登ったらすぐに教わったスーパーMARUTOという看板が見えましたよ、いかにも地元密着型らしいこじんまりした店で何か地元産の旨いものがありそうと期待して入店、それがありふれたものばかりでこれはという珍しい地場食材は見当たらない。魚もカツオなどが焼津産と韓国産というのには、せめていわき市の魚となっているメヒカリの干物ぐらいは置いてあるかと思ったのにねぇ、わずかに目についたのは地元産じゃない子持カレイの煮付があったぐらいでこれは残念でした。
 地元スーパーのMARUTO
地元スーパーのMARUTO
駅前に戻って商店が並ぶ通りから温泉旅館が集まる場所へと一回りしていくことに、以前も歩いてみてかなりウラブレテきている感じを受けてはいたが、町興しに期待して温泉客などを迎えるためのブロンズ像(冒頭写真も途中のポケットパークにあったブロンズ像、この写真の中に一匹歩きしていた犬が写っているが道路を横切ったりとスイスイと、首輪があったから飼い犬だと思うけれど普段から放し飼いしているんだろうか、やはり田舎町ということですかね)が街中にあって、それは面白いとは思うけれどこれにプラスアルファが欲しいところである。中では猫の象の案内板の記載内容が愉快であったが、かなりに説明板が壊れていたり汚れていたりで、メンテももっとすることとより目立つデザインのものにしたらと思いますが。
 手前が猫のブロンズでまだ名前が無いとあった
手前が猫のブロンズでまだ名前が無いとあった
駅前正面の崖の下にはいわき湯本温泉の由来の看板が立てられたモニュメントみたいなものがあって、有馬温泉と道後温泉とここが日本三大古泉となっているんだそうだが、三つの中では遅れをとってしまっているようで、ハワイアンズと共存して活気を呼び込む手立ては考えられないんでしょうか。温泉地での夜の泊り客を昼間もつなぎとめる手立てを考えないと、街を歩いてみるといくつかレトロで興味をひくものはあると思うんですが。それらを観光用街歩きコースに組み込んで整備し、さらに観光客に喜ばれる新鮮市場みたいなものを中心部に作ったらどうですか、それも魚だけの小名浜とは一味違うものにして、そこを資本がある所に任せるんじゃなく地元商店の中で意欲がある人を集めて、各自に競わせて多様な商品を扱うようにするということを提案します。
 日本三大古泉の掲示が
日本三大古泉の掲示が
公衆共同浴場ではさはこの湯は有名だが駅近くにもややこじんまりだがみゆきの湯という温泉公衆浴場があって、料金は220円とあった、さらに介護浴室もあるというからいかにも温泉が生活に根付いているということだ。でも身障者用以外の駐車場が無いのは観光客には不便、駅に隣接する駐車場を利用してくれとなっていたが無料券でも出るのかな。
 みゆきの湯
みゆきの湯
温泉街を散策中に三重塔を見掛けた、その周囲には瓦屋根だけが見えるだけだが本堂などのいくつかの建物があるようで、相当に大きな寺らしいと分かる。あとで調べたら勝行院という寺だそうで七伽藍が揃う名刹とか、かの最澄と宗論をした奈良仏教界の高僧で会津で布教した徳一が開基というから歴史ある寺で、日本三大古泉の地には相応しい、但し三重塔自体は新しいものということだ。
 勝行院の三重塔
勝行院の三重塔
途中にあった老舗らしい温泉旅館はちょっとばかり魅力的、入口にある建物は実に奥ゆかしい和風建築を残していて宿の看板になっている、その奥に新しく増築したほうはどういう使い方をしているのか、泊り客に新旧両方を上手く使って楽しめるようにしているなら泊まってみたいと思わせる雰囲気がある、これも日本三大古泉ならではという感じの宿だ。
 老舗らしい旅館
老舗らしい旅館
有名な共同浴場のさはこの湯はこの日火曜日は定休日で設備洗浄の車が駐車していたが、さはことは三函と書いて昔のここの温泉地名だったと由来には書いてあった、今回で初めて名前の由来を教えられました。
 さはこの湯
さはこの湯
古くからの温泉地には温泉神社はつきもので、ここにもその名前を見つけて隣に常磐湯本財産区と書かれたタンクもあるから源泉があるのかもと、階段下の鳥居まで来たら硫黄臭が漂いそれらしい神社だと。でも階段を登って行った境内ではそれらしきは見つからなくて、さっきの匂いは何処からだったんだろうと戻ってきたら、なんと鳥居の陰にあった石碑の上に湯けむりらしきが見える、その石のテッペンからはチョロチョロと流れ出ているのが温泉であった、それでこの近くのモミジだけはまだ葉を落とさずにいたんだね、最初にもう全部が落葉しているのになんでここの木だけがと不思議だったのが納得。
 温泉神社
温泉神社
 硫黄の臭いがする石の上には湯気が
硫黄の臭いがする石の上には湯気が
街には駅前にある足湯のほかにもやや離れた場所に鶴のあし湯というのがあって、この日はご老人だけが利用しているようであったが、この場所だと観光客には使いにくいと思うが、ここも歩きで来て立寄るしかないからまずは滞在客を増やさないと宝の持ち腐れだ。
 鶴のあし湯全景
鶴のあし湯全景