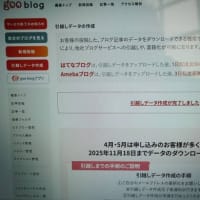今日の宿がある水府村までの迂回コースとして、烏山から馬頭町経由で大子町に出て行くことに。まず烏山は烏山和紙と山あげ祭というのがが有名です。山あげ会館という展示館には一度だけ入ったことがあって、祭の様子をロボット人形風に見せていて、街中心部の道路を舞台に演じる芝居の大道具の展開趣向から名付けられたことがよく分かり、ほのぼのと面白かったと記憶がある。毎年7月末の暑い時期に祭があるだが、一度は見てみたいものですねぇ。
昨年は立寄ったものの今回はパスした烏山和紙会館では、和紙以外に工芸雑貨も販売している。市内にある酒蔵では東力士の島崎酒造はかなり拘りの蔵元で、5、10、15年という古酒まで販売しているという珍しい店。もちろん保存手数料がかかるため、かなりお値段の張る酒で、黄色味がかってやや酸化臭がするため、日本酒という感じからは離れた味わいで好き嫌いは分かれるでしょうが、確かにまるやかさは加わっているがワインの華やか熟成風味という訳にはいかないと思いますよ。他にはこの近くに烏山焼の店を謳う、商号あらまんの萬さろんという和風の立派な明治の木造商家建築があり、地元3人ほどの作品を販売していたが、そこそこのお値段で益子と比べるとどうでしょうかねぇ。もう一つ市街から馬頭町に向う道路沿いの高台には、倶門窯という看板が目印の工房があり、こちらは浜田庄司の最後の弟子という瀧田項一の窯で、ぐい呑でも三越では5万円ほどで売っている大家の部類に入る作家が在住、絵柄は益子風とは違ってもっと鮮やかな色彩の図が特徴です。そう言えば和紙会館の工芸品売場には大家の倅の方の作品を展示販売していたが、やはり似た作風になっていましたね。
 島崎酒造
島崎酒造
 利き酒コーナー
利き酒コーナー
馬頭町には小砂子焼の窯元がいくつかあるが、黒と茶系の民芸風焼物が主体の中でやや作風が違う国山窯は、主人が陶磁研究で早稲田大学の文学博士号を取ったという変り種。この窯では青磁風釉薬を多く使い、これと茶系の釉薬とを使い分けた図柄の作品は僕の好みです。三笠宮妃殿下が馬頭の旅館にお泊りの折、食事の食器に使われたという揃いが展示してあったが、現在販売してはいないものにかなり魅力的なものがありましたよ。ここでは安いミルクピッチャーを、一輪挿し兼用にと2個だけ女房が購入してサヨウナラ。この途中、馬頭と大子を結ぶ東西幹線から北にある小砂子に入る道筋に、手作りハム、ソーセージの組合が作った田舎レストラン巴夢が新しく出来ていたが、確かここのハムも旨かったと記憶している。
 国山窯直売所
国山窯直売所
 三笠宮妃殿下用食器
三笠宮妃殿下用食器
そうこうしているうちに時間もよろしいようでと、あとは宿まで直行することに、途中馬頭町役場裏に新たに建設され建築雑誌を賑した広重美術館にも立寄りたかったのだが、時間的に次の機会にということで諦める。十分に時間があれば馬頭には公衆温泉かりがねの湯などがあって、ノンビリと立寄湯するのもいいでしょうけどねぇ。袋田の滝方面手前から一山越えて右折、水府村に入るとかなり細い道を南下することになり、岩倉鉱泉の看板を目印に右折して一本道の行き止まりにある民宿風旅館に到着する。
今日の宿は一日6組までというこじんまりしたアットホームな田舎の旅館であるが、100年以上の歴史があって現在の若女将で4代目だそうだ。最初訪れた時からは風呂が立派になったり、新しい部屋が増えたりと努力が見られる、でも値段は変わらずで頑張っています。今回は地元の7人の団体客と我々2人だけ。鉱泉はアルカリ性メタケイ酸泉で、やや肌がツルッとするサラサラの湯、古くからの利用客によれば最初はもっと下の川沿いに湧き出した場所近くにあって混浴風呂だったそうで、やや硫黄臭もあったそうだ。現在の浴室はその上の方に単独で建てられ、石張りに高い木造吹抜天井の立派な風呂になっている、客室数に対しては大きめで結構気持ちよく入れるが、冬場の洗い場はやや寒いのだけが難点ですかね。また客室がある母屋から浴室に渡る長い廊下には花が生けられて、ここだけは立派な旅館に来たという感じ、庭もお爺さんが手入れしていて立派な農家の座敷前庭の雰囲気がある。
食事は我々が泊まっていつも出るのがシャモ鍋とカツオの刺身。刺身は近くの魚屋から仕出ししてもらうそうだが、いつも新鮮なのにはビックリする、山の中とは思われません。ご飯か蕎麦を選べるというので蕎麦を頼んだがその量にもビックリ、鍋の最後は残してしまい勿体無いことに。蕎麦が出た時に、最近東京で有名だという慈久庵という店がこちらに移ってきたんですが、注文してから1時間は待たすと評判が悪いんですとの話、それに地元の人は更科という白い蕎麦は好みでないみたいと。阿佐ヶ谷の有名店も田舎に来たら気取ってはいけないようですね。酒は水府村の地酒富久錦の純米冷酒を飲んだが、名水の里に恥じず柔かい味わいでかなりイケルものでしたよ。
 岩倉鉱泉
岩倉鉱泉
 浴室に続く長い廊下
浴室に続く長い廊下
 浴室
浴室
 夕食
夕食
 お婆さん手打ちの蕎麦
お婆さん手打ちの蕎麦
翌朝は7時半に朝食とは朝が早い我々には嬉しいですねぇ。茨城らしく納豆は当然として、塩鮭、生卵、海苔、ホーレンソウお浸し、ワカメ味噌汁に梅干は一般の旅館の定番、ご飯は今日も二杯、この日は名物の凍みコンニャクは出ませんでしたが、生卵の黄身の紅がかったまでの濃い色にはいかにも栄養豊富で体に良さそうだと。