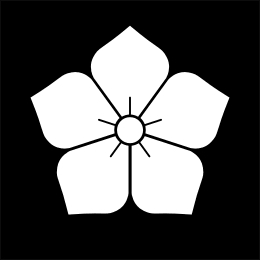http://www.asahi.com/paper/front.html
世界史は学んでおいた方が良いよお。
地球規模で、歴史を学ぶことは、
人間という生き物を知ることにつながる。
思想哲学や、宗教、科学、経済、法学・・・、
全ての分野に関わる学びですよ。
世界史を学んでないと、
何をするにも、了見が狭くなってね、困ったもんです。
なんでこんな事が言えるのかというと、
私自身が、学生時代に世界史を学ばなかったから。
もうすでに、私の高校時代には、受験対策のためのカリキュラムがしかれてあって、
ご多分に漏れず、共通一次試験で必要となる科目だけしか勉強しませんでした。
今回のような騒ぎにならなかっただけの話ですよ。
お坊さんの専門の勉強をするようになって、
初めて世界の歴史の必要性に気づき、
大慌てで勉強するも、時すでにおそし。
あれよあれよと言う間に、
押し寄せる課題につぶされて、
中途半端にやり過ごしてしまいました。
しかし、冬休み返上で単位を補充していくっていっても、
他の受験科目の補習だけでも時間が足りないくらいでしょ?
どうなるのかしら?
それに、世界史のおもしろさって、そのステージステージで展開する
物語を理解してこそ深みが出て来るってもんで、
暗記のための勉強や、とりあえずザーッとやり過ごす勉強じゃ、
はっきりいって、最初からやらない方が、
身体や頭のためには健康的だと思ったりもするのですが、
いかがなもんでしょ?ねえ。
グーグルの
世界史は学んでおいた方が良いよお。
地球規模で、歴史を学ぶことは、
人間という生き物を知ることにつながる。
思想哲学や、宗教、科学、経済、法学・・・、
全ての分野に関わる学びですよ。
世界史を学んでないと、
何をするにも、了見が狭くなってね、困ったもんです。
なんでこんな事が言えるのかというと、
私自身が、学生時代に世界史を学ばなかったから。
もうすでに、私の高校時代には、受験対策のためのカリキュラムがしかれてあって、
ご多分に漏れず、共通一次試験で必要となる科目だけしか勉強しませんでした。
今回のような騒ぎにならなかっただけの話ですよ。
お坊さんの専門の勉強をするようになって、
初めて世界の歴史の必要性に気づき、
大慌てで勉強するも、時すでにおそし。
あれよあれよと言う間に、
押し寄せる課題につぶされて、
中途半端にやり過ごしてしまいました。
しかし、冬休み返上で単位を補充していくっていっても、
他の受験科目の補習だけでも時間が足りないくらいでしょ?
どうなるのかしら?
それに、世界史のおもしろさって、そのステージステージで展開する
物語を理解してこそ深みが出て来るってもんで、
暗記のための勉強や、とりあえずザーッとやり過ごす勉強じゃ、
はっきりいって、最初からやらない方が、
身体や頭のためには健康的だと思ったりもするのですが、
いかがなもんでしょ?ねえ。
グーグルの