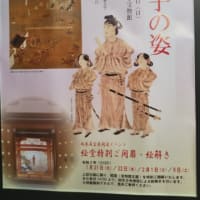昨日のミーティングの合間に、青野先生が「白内障」についてミニレクチャーをしてくれました。
奇しくも先日母が両眼を手術したところで母は老人性ですが、実は糖尿病と白内障には深い関係があります。
さて、
母は長く強度の近視のために、眼鏡をかけてもほとんど見えない状況でした。
眼科はここ10年でとても進歩した分野のひとつで、セカンドオピニオンも含め、ちゃんと眼科で話を聞いて、と、私はこの数年何度も言ってきました。
しかし、移った眼科でも、矯正視力も出ないので、手術はリスクだけなので無駄と言われて母はあきらめていたのです。
ところが数ヶ月前にほとんど見えなくなり、もう一度病院を変わりました。
すると、すぐに白内障の手術をするという話になり、市民病院を紹介されこの度両眼の手術をすることになったのです。
母の手術前の視力は0.01かそれ以下ということで、視力の回復はあまり見込めないという話だったのですが、手術後、ド近視の私には理解できない距離の字が見えるというのです。
退院後、両眼が0.5、0.7まで回復しているということが判りました。
眼鏡さえ普段の生活には必要なくなってしまったのです。
私はそのとき10年前のことを思い出しました。
開業医できちんとした糖尿病の診断を受けられず、A1c12.3%を放置されました。
私は、難病でも1型糖尿病のように稀な病気でもなかっただけに、私がその開業医に抱いた医療不信は相当に大きなものでした。
医学は日々進歩しています。
病気の概念も治療方法も大きく変わることはしばしばあります。
そして医師は正しい知識ときちんとした認識を持っているのが当然だと思っていました。
でも糖尿病医療についてきちんとした認識を持っていない医師や、血液検査と対症的な薬物療法しかできない医師がいること、そして私が何も理解できないまま医療を中断してしまったことは事実で、私はその後さらにつらい経験を経て、医療も医学も絶対ではない不確実なものだと理解しました。
あらゆる意味で患者としての努力も必要だと考えるようになりました。
世間では病診連携と言いますし、現在では開業医の先生でも研鑽を続ける先生を多く知るようになりましたが、私たちには個々の先生の医療の質を問う術がないというのが医療の現実なのです。
白内障の手術は、以前は、とことん進んでから行われるものであったようです。
また眼内レンズやその安定技術、患者の負担の軽減もここ10年ほどで大変進歩したようです。
母に手術は無理と言っていた先生は、どのような認識をお持ちだったのでしょう。
どのような理由で不可能と判断されていたのでしょうね…
母はおもしろいことを言いました。
きれい好きな母が自宅に戻って、部屋の汚れにびっくりしたこと。
そして鏡を見て、自分の顔のしわにとても驚いたんだそうです。
浦島太郎みたいです。
そして。
母の手術をした市民病院は、建て替えられてから数年の新しい建物です。
(私の通った小学校の跡地に建てられ、私の小学校はなくなってしまいました…)
しかし医師の数はあまり多くなく、大学病院から派遣された中堅医師がほとんどの科で1-2人体制で外来を担当しておられたようです。
眼科は2人で、母の手術を担当した先生も月曜から金曜に毎日午前の外来を終えてから数件のオペを行っていたようです。
小児科は例に漏れず1人体制でした。
産婦人科は、10月から毎日の外来が危ぶまれていたようですが、何とか2人体制を保てたことが掲示してありました。
前にしばらくの間ここに赴任された糖尿病の先生が、この病院の糖尿病医療の現状を嘆いておられました。
北九州市は政令都市で救急医療や小児医療にはいろいろ尽力されているようですが、高齢化率も高く、特に地理的に孤立したこの地域の公立病院も他と同様の地域医療の問題を抱えているような気がしました。
そして人口は減り公立病院はこんな状況であるのとは対照的に、町には開業医がとても増えていました。
新しい建物があればまず新しく開業したクリニックでした。
ちょっと不思議な町の風景でした。
奇しくも先日母が両眼を手術したところで母は老人性ですが、実は糖尿病と白内障には深い関係があります。
さて、
母は長く強度の近視のために、眼鏡をかけてもほとんど見えない状況でした。
眼科はここ10年でとても進歩した分野のひとつで、セカンドオピニオンも含め、ちゃんと眼科で話を聞いて、と、私はこの数年何度も言ってきました。
しかし、移った眼科でも、矯正視力も出ないので、手術はリスクだけなので無駄と言われて母はあきらめていたのです。
ところが数ヶ月前にほとんど見えなくなり、もう一度病院を変わりました。
すると、すぐに白内障の手術をするという話になり、市民病院を紹介されこの度両眼の手術をすることになったのです。
母の手術前の視力は0.01かそれ以下ということで、視力の回復はあまり見込めないという話だったのですが、手術後、ド近視の私には理解できない距離の字が見えるというのです。
退院後、両眼が0.5、0.7まで回復しているということが判りました。
眼鏡さえ普段の生活には必要なくなってしまったのです。
私はそのとき10年前のことを思い出しました。
開業医できちんとした糖尿病の診断を受けられず、A1c12.3%を放置されました。
私は、難病でも1型糖尿病のように稀な病気でもなかっただけに、私がその開業医に抱いた医療不信は相当に大きなものでした。
医学は日々進歩しています。
病気の概念も治療方法も大きく変わることはしばしばあります。
そして医師は正しい知識ときちんとした認識を持っているのが当然だと思っていました。
でも糖尿病医療についてきちんとした認識を持っていない医師や、血液検査と対症的な薬物療法しかできない医師がいること、そして私が何も理解できないまま医療を中断してしまったことは事実で、私はその後さらにつらい経験を経て、医療も医学も絶対ではない不確実なものだと理解しました。
あらゆる意味で患者としての努力も必要だと考えるようになりました。
世間では病診連携と言いますし、現在では開業医の先生でも研鑽を続ける先生を多く知るようになりましたが、私たちには個々の先生の医療の質を問う術がないというのが医療の現実なのです。
白内障の手術は、以前は、とことん進んでから行われるものであったようです。
また眼内レンズやその安定技術、患者の負担の軽減もここ10年ほどで大変進歩したようです。
母に手術は無理と言っていた先生は、どのような認識をお持ちだったのでしょう。
どのような理由で不可能と判断されていたのでしょうね…
母はおもしろいことを言いました。
きれい好きな母が自宅に戻って、部屋の汚れにびっくりしたこと。
そして鏡を見て、自分の顔のしわにとても驚いたんだそうです。
浦島太郎みたいです。
そして。
母の手術をした市民病院は、建て替えられてから数年の新しい建物です。
(私の通った小学校の跡地に建てられ、私の小学校はなくなってしまいました…)
しかし医師の数はあまり多くなく、大学病院から派遣された中堅医師がほとんどの科で1-2人体制で外来を担当しておられたようです。
眼科は2人で、母の手術を担当した先生も月曜から金曜に毎日午前の外来を終えてから数件のオペを行っていたようです。
小児科は例に漏れず1人体制でした。
産婦人科は、10月から毎日の外来が危ぶまれていたようですが、何とか2人体制を保てたことが掲示してありました。
前にしばらくの間ここに赴任された糖尿病の先生が、この病院の糖尿病医療の現状を嘆いておられました。
北九州市は政令都市で救急医療や小児医療にはいろいろ尽力されているようですが、高齢化率も高く、特に地理的に孤立したこの地域の公立病院も他と同様の地域医療の問題を抱えているような気がしました。
そして人口は減り公立病院はこんな状況であるのとは対照的に、町には開業医がとても増えていました。
新しい建物があればまず新しく開業したクリニックでした。
ちょっと不思議な町の風景でした。