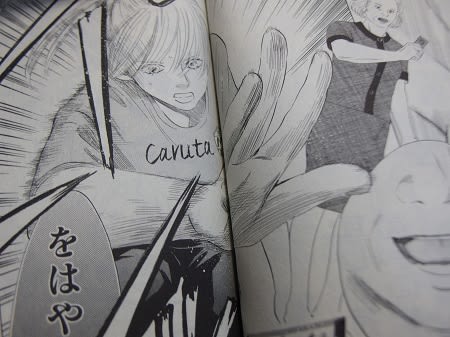長男の嫁から「これを読まないと人生をしくじる」といって貴志祐介の『天使の囀り』(1998/角川書店)を薦められた。
「BOOK」データベースによると、
北島早苗は、ホスピスで終末期医療に携わる精神科医。恋人で作家の高梨は、病的な死恐怖症だったが、新聞社主催のアマゾン調査隊に参加してからは、人格が異様な変容を見せ、あれほど怖れていた『死』に魅せられたように、自殺してしまう。さらに、調査隊の他のメンバーも、次々と異常な方法で自殺を遂げていることがわかる。アマゾンで、いったい何が起きたのか?高梨が死の直前に残した「天使の囀りが聞こえる」という言葉は、何を意味するのか? 前人未到の恐怖が、あなたを襲う。
というもの。
高梨のほかにアマゾンに同行した動物恐怖症の大学教授はのこのことトラに近づき身をさらすようにして食われて死ぬ。同じく同行したカメラの女性(母親)は最愛の一人っ子をを殺害してしまう。それは前の子をなくしていただけに一番の恐怖のはずである。
醜形恐怖に取り憑かれていた青年は自らの顔貌を薬品でどろどろに溶かして死ぬ。不潔恐怖症の囲碁少女はアオコの腐敗臭漂う沼で水死する。
いってしまうと、ブラジル脳線虫が寄生したのである。このことはネタバレなのだが、ミステリーとしては割と早い段階で線虫が寄生したのだとわかる。
作者がネタをばらしてしまうのに興味を最後まで維持できるところがすばらしい。
神話と生物学との関わりとか知識を満足させてくれるとともに、ヒトがヒトでなくなっていく奇態の描写は背筋が震えるほど怖くスリリング。匂いに包まれて嘔吐しそう。
文章がていねいで落ち着いていてテンポがある。すなわち描写が優れていること。
たとえば帰国して様変わりした高梨が早苗を抱こうと迫るシーンや、寄生した依田に接吻されるときのおぞましさの描写は極上。
またゲームの中でしか恋をできない青年の「沙織里ちゃん」に対するバーチャルな恋心もぞくぞくする。
本書は「ホラー」といわれるようだ。
ぼくはホラーでもサスペンスでもなんでもおもしろければ読む。基本的に文章が優れていることと甘くないことである。文章が優れているということは描写力とテンポ、リズム感である。
嫁から薦められた作家はこれで二人目。
最初は京極夏彦の『姑獲鳥の夏』であった。嫁は推理小説として惹かれたらしいがぼくは京極堂シーリズよりまず『ヒトでなし』『嗤う伊右衛門』『数えずの井戸』など興味を持った。結果、嫁より多く京極さんを読んだことになる。
ぼくから嫁に薦めたのが恩田陸『蜜蜂と遠雷』である。
本を読み合うことで人の性格や嗜好を確認していくのも乙なものである。