
ゆうべつれづれに「スポーツライブ+」を見た。
全日本プロレスかと思ったら大日本プロレスであった。録画は2019年8/4後楽園ホールのもの。5年半も前のやつだが、なんと、そこにグレート小鹿がいた。
目を疑った。40年前の風貌がそう変わっていなかった。この録画の小鹿さんは77歳。
グレート小鹿はジャイアント馬場時代に全日本プロレスで活躍した選手。大熊元司と組んで極道コンビ」としてアジアタッグ王座をとるなど一時代を築いた。
相棒の大熊は51歳でこの世を去り、御大ジャイアント馬場も26年前に没した。
一時代過ぎ去っている。これは亡霊ではないか。
だが、小鹿さんは矍鑠として動き、殴るや蹴るや、叩かれるや踏みつけられるや、とても老人ではなかった。若手が遠慮なく蹴り、殴っていた。この録画の小鹿は77歳である。

今年、小鹿さんは82歳になった。
東スポが1月8日に配信したところでは、リング復帰を宣言したとか。この録画の後だろう。胃がん、大腸がん、膀胱がんにかかりその治療でリングに立てなかったようだ。それを克服し、2月の再検査で異常がなければまたリングに立つという。
唖然とした。
小生は73歳。彼より9歳若いが、殴る、蹴るなど暴行を受けたら寝たきりになるだろう。小鹿さんはそれが積み重ねてきた仕事だからできるのだろうが、それにしても、82歳でかような骨仕事に立ち向かう気力、体力はどこから出てくるのか。
73歳の小生は、歩くだけである。
有識者が老人も筋トレをしたほうがいいというので、腕立て伏せを1週間続けたら、体こ強張った。結果、鍼灸治療を受けにいくはめになった。歩くだけにしよう。
グレート小鹿さんを仰ぎ見るばかりある。













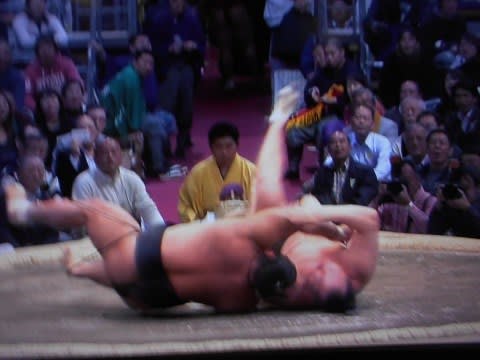
 左、篠原の本来ならば一本勝ち
左、篠原の本来ならば一本勝ち







