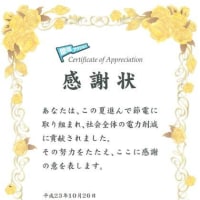私的話法と公的話法の特徴を挙げると,次のようになる。
私的話法
・日常的
・生活的
・個人的
・私人的
・個性的
・性格的
公的話法
・非日常
・職務的
・社会的
・公務的
・標準的
・技術的
授業中に子どもたちが話すとき,話したいように話すのではいけない。
教師は私的話法を使わせるべきではない。
野口芳宏氏は次のように言う。
教室で話す時,授業で発言する時,教室で音読する時には「公的話法」「公的音読」を用いよ。私的話法,私的音読は不可である。このような指導を徹底するだけでも子供の「伝え合う表現スキル」は一変する。(『実践国語研究』2010年1月号)
私が現在担任している3年生のクラスの実態はどうかというと,授業中に関しては丁寧な言葉遣いで話している子が多い。
授業中ばかりではない。私に対して話すときは大半の子が敬語を使っている。
これは言語環境との関係があるだろう。
私は教室では丁寧な言葉遣いで話している。
授業中,休み時間に関わらず,子どもに対しては「~です」「~ます」と話している。
これは一見すると不自然な光景であろう。
子どもにとっては,とっつきにくい先生であるかもしれない。
だが,私のキャラクターもあるのだろうが,実際はそのような受け止められ方はしていないようである。
公的話法は非日常的なコミュニケーション,社会的なコミュニケーションなのである。
教師が自ら範を示す必要がある。
しかも,徹底していかなければならないのではないだろうか。
教師が私的話法を用いれば,たちまち公的話法は崩れていってしまうだろう。
言葉遣いはよい。公的話法に関して,私のクラスでは次のような課題がある。
・声が小さい。
・公的話法で話し合えない。
これらは他者意識の欠如が原因であるといえる。
「声が届かなくても別に構わない」「話したいように話せばよい」というような潜在意識があるのではないだろうか。
相手の立場を考えないから,このような実情になってしまうのである。
子供たちの公的話法のスキルをさらに高める指導が必要である。
私的話法
・日常的
・生活的
・個人的
・私人的
・個性的
・性格的
公的話法
・非日常
・職務的
・社会的
・公務的
・標準的
・技術的
授業中に子どもたちが話すとき,話したいように話すのではいけない。
教師は私的話法を使わせるべきではない。
野口芳宏氏は次のように言う。
教室で話す時,授業で発言する時,教室で音読する時には「公的話法」「公的音読」を用いよ。私的話法,私的音読は不可である。このような指導を徹底するだけでも子供の「伝え合う表現スキル」は一変する。(『実践国語研究』2010年1月号)
私が現在担任している3年生のクラスの実態はどうかというと,授業中に関しては丁寧な言葉遣いで話している子が多い。
授業中ばかりではない。私に対して話すときは大半の子が敬語を使っている。
これは言語環境との関係があるだろう。
私は教室では丁寧な言葉遣いで話している。
授業中,休み時間に関わらず,子どもに対しては「~です」「~ます」と話している。
これは一見すると不自然な光景であろう。
子どもにとっては,とっつきにくい先生であるかもしれない。
だが,私のキャラクターもあるのだろうが,実際はそのような受け止められ方はしていないようである。
公的話法は非日常的なコミュニケーション,社会的なコミュニケーションなのである。
教師が自ら範を示す必要がある。
しかも,徹底していかなければならないのではないだろうか。
教師が私的話法を用いれば,たちまち公的話法は崩れていってしまうだろう。
言葉遣いはよい。公的話法に関して,私のクラスでは次のような課題がある。
・声が小さい。
・公的話法で話し合えない。
これらは他者意識の欠如が原因であるといえる。
「声が届かなくても別に構わない」「話したいように話せばよい」というような潜在意識があるのではないだろうか。
相手の立場を考えないから,このような実情になってしまうのである。
子供たちの公的話法のスキルをさらに高める指導が必要である。