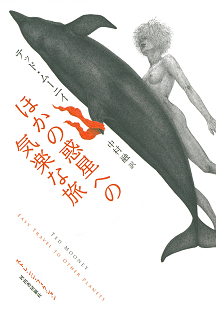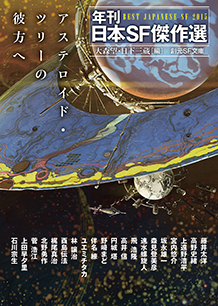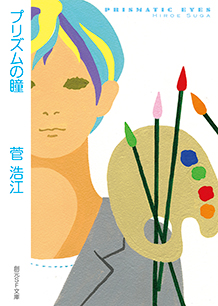『ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン』 ピーター・トライアス (新☆ハヤカワ・SF・シリーズ)
なんと、新☆ハヤカワ・SF・シリーズと、ハヤカワ文庫(上下組)の同時発売。危うく両方買いそうになった。まぁ、文庫版の方を買う人が多いとは思うが、この版型で集めているので、こちらで。
第二次世界大戦で日本とドイツが勝利し、アメリカ西海岸が日本の、アメリカ東海岸はドイツの統治下におかれて、40年。
冒頭は西海岸の日本人収容所の悲惨な状況とそこからの解放のシーンから始まるが、40年後の世界はまるでその裏返し。アメリカ西海岸全体が収容所になってしまったような、特高と憲兵が我が物顔で闊歩する見事なディストピア。それに加えて、謎の技術力でメカ(=巨大ロボット)を作り、国家的にゲームに興じるというクールジャパン的日本像が描かれる。
表紙はまるで『パシフィック・リム』(これは文庫版も同様テイスト)だが、内容は『高い城の男』というか、完全なディストピア小説。主人公ふたりのエピソードはなかなかエグい。ここが変だよジャパネスク文化のもとで、日本製のメカが暴れまわる話と思って読み始めたら、いきなり特高や反乱分子の拷問シーンはグロいし、メカ同士の戦闘シーンは悲壮感丸出しだし、爽快感もなにも無い。
著者のピーター・トライアスは、名前からはわかりにくいがアジア系アメリカ人だとのこと。幼少期を韓国で過ごしたとあるので、韓国系か。日本製のゲームを持っていたことで怒られたとの反日的言動にもさらされたようだが、映画やゲームから日本文化の影響を多大に受けているのは確かなようで。個別のオタク的ネタや、お遊び要素はそこら中にあふれている。
しかし、この小説のメインのターゲットはそこにはなく、日系と非日系の階層社会、絶対天皇に対する本音と建前を使い分ける社会、特高による監視社会といったあたりが主題なのか。しかし、ちょっと戯画的にすぎるような気もするので、どう取ればよいのかわからないのが正直なところ。
というのも、この手の小説は、戦前戦中の日本社会をどこまで正しく理解していて、批判的にしろ好意的にしろ、どこまで本気で書いているのかわからないのだよね。こんな社会ダメだろうと言えば、現代の日本人だってダメだろうと同意するだろうし、現代アメリカ社会の裏返しに取るとしても安直すぎるし。あり得ないファンタジーの一種として持ってきた舞台と見るのが正しければ、そこはあまり突っ込まないでいいような気もするし。
ものすごく惹きこまれたし、笑って怒って泣けるという非常に大きな振幅で心を揺さぶってくる小説ではあるけれど、日本人としてこの小説に対してどういう態度で接するべきか、戸惑ってしまうのが正直なところ。
SFシリーズ版の解説では、本国では「村上春樹的」との評を受けたようだが、訳文で読む限りは、どっちかというと「村上龍的」な感じ。『五分後の世界』がテイスト的には近い。もっとも、向いている方向は、あれとは正反対なのかもしれない。