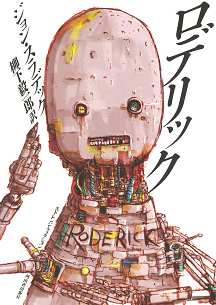折りしも「バーナード嬢×ハヤカワ文庫 読破したふり禁止フェア」なんてものも開催中だが、「一度も読んでないけど私の中ではすでに、読破したっぽいフンイキになっている !!」といえば、その代名詞とも言えるSF作家がハーラン・エリスンなのではないだろうか。
『死の鳥』は、上記のフェアにもラインナップされている『世界の中心で愛を叫んだ獣』に続き、(なんと!)日本で出版された2冊目の短編集。なんでこれまで出版されなかったのかは本当に謎。
表題作の「死の鳥」はもちろん、「「悔い改めよ、ハーレクィン!」とチクタクマンはいった」とか、「おれには口がない、それでもおれは叫ぶ」とか、あまりにもタイトルが有名で、すっかり読んだ気になっている人も多いのではないか。なんか、それこそアニメやラノベで使われそうなタイトルでもあるし。
エリスンといえば、解説にもある通り、というかS-Fマガジンでの紹介が悪いんだろうけれど、華麗でスタイリッシュな文体と、誰彼かまわず噛みつく論争屋というイメージが先行しているが、確かにスタイリッシュと言われる独特にひねくれた世界観は味わい深かった。
とはいえ、やっぱりそれなりに古臭さは感じるわけで、2、30年遅いよという残念感が強い。なんというか、どうしても古典SFのお勉強をしているような感覚になってしまう。
しかしもちろん、読者を試すような構成や、まるで詩人が叫ぶような文体は、まだ新鮮さを失っているわけではない。
最新作(といっても1987年だが)の「ソフト・モンキー」でも顕著であるが、彼の嗜好はいわゆる空想科学小説というより、もっと思弁小説(あるいは、もっと言えば純文学?)に近いところ(だから当時からニュー・ウェーブと言われていたのだが)にあるようで、SF的にどうなのっていう部分はあるのだけれど、短編小説として(今風にいうところの)普通におもしろい。というか、普通に(!)エキサイティングだ。
あまりのビッグネームゆえに、SFファンはどうしても基礎教養として構えて読んでしまうのではないかと思うので、かえって先入観の無い「群像」とか「すばる」とかを読んでいる層に受けるんではないかと思うんだけれど、いかがですかね。その手の人の感想って、聞いたことないんだけれど。
○「「悔いあらためよ、ハーレクィン!」とチクタクマンはいった」
個人的に時間は守る方で、遅刻は重罪だと思っているので、ハーレクィンは死刑。
○「竜討つものにまぼろしを」
解説の“サイケデリック”というより、テレビゲームを連想してしまったのだが、たしかに1966年じゃドラゴンクエストどころか、その元ネタとされるD&D(TRPG)も世に出ていないのだよな。
○「おれには口がない、それでもおれは叫ぶ」
これも今ではネタ的にはありふれてしまったが、1967年かよ。タイトルもエリスンの性格の苛烈さを表しているようだ。
○「プリティー・マギー・マネーアイズ」
世にも奇妙な的な怪談調。そういえば、「アウター・リミッツ」の脚本もやっていたのだよね。
○「世界の縁に立つ世界をさまようもの」
これも叫んでいる。誰に届くわけでもないのに叫び続けるというのはエリスンの好んだモチーフなのだろうか。まさに叫ぶ詩人。
○「死の鳥」
最後の“マーク・トウェインに捧げる”の意味が分からなくて落第しそう。読者への問いは作品解釈のための補助線であるとともに、ミスリードする罠でもあるので侮れない。
○「鞭うたれた犬たちのうめき」
暴力への苛烈なメッセージ性を受け取るとともに、共同体の本質的なおぞましさも感じる。飲み込まれないこと。
○「北緯38度54分、西経77度0分13秒 ランゲルハンス島沖を漂流中」
ランゲルハンス島という体内組織をホントの島に見立てるという、いかにも非理系的な小説。ミクロの決死圏的な設定がどうしてこうなるのかというと、ニューウェーブだから(ここ笑うところ)。正直言って、すべてのネタは解明できてません。なお、ここは(ある意味、とっても)面白いので読んでみるといいかも。
○「ジェフティは5つ」
ただの怪談でも、ただの懐古趣味でもなく感じるのは、読者への最後の問いかけのせいか。
○「ソフト・モンキー」
SF読みなので、このての小説に対して何を書けばいいのかわからない。何を言っても小並感でしかなく。しかし、もしアランが実体だったとしたら……。