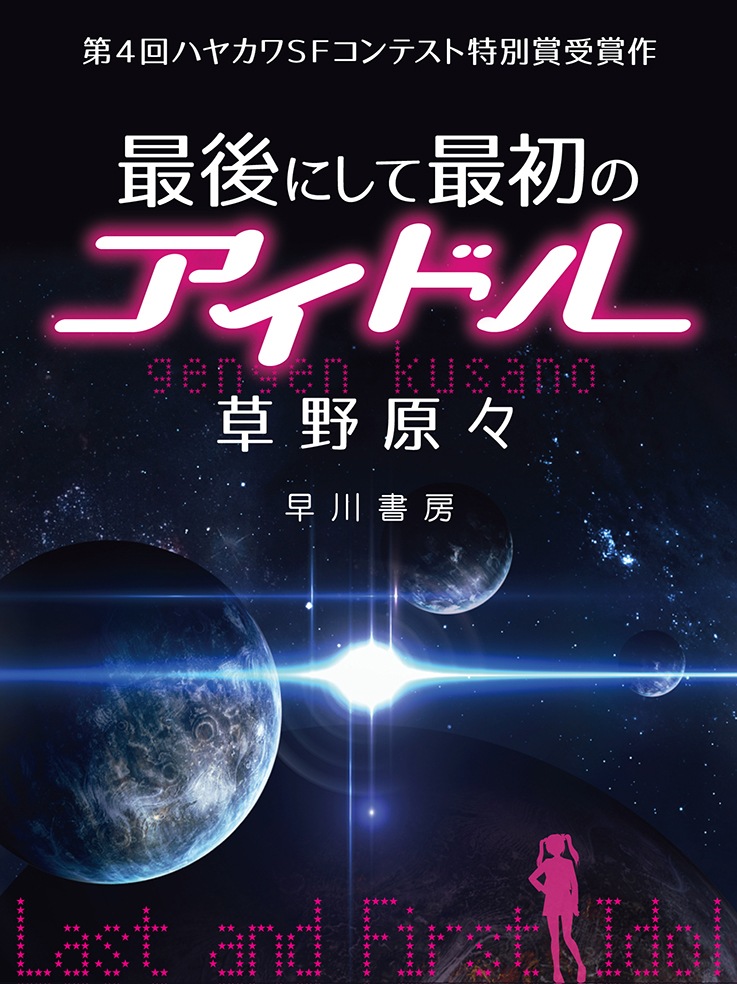なぜSFカテゴリなのか。森見氏は立派な日本SF大賞受賞作家なのだから仕方がない。直木賞は逃したけどな!
さて、この小説は森見氏デビュー10周年企画のひとつだったはずが、いったい何年目の10周年なのだという、待ちに待った新作である。軽妙な話の多い森見氏にとっては『きつねのはなし』以来のダークな作風、いわば、“裏”登美彦氏の10周年集大成である。
しかし、この、なんとなく釈然としない読後感はなんなのか。まさに、きつねにつまままれた感じだ。
森見氏の作品といえば、道中えらくとっ散らかりながらも、驚くべきことにすべてが落ち着くところに落ち着くという結末の付け方が魅力のひとつなのだと思う。それがどうしたことか、この話は論理的におかしいぞ。
英会話スクールの仲間6人が鞍馬の火祭に出かけた。そこで、長谷川さんひとりが行方不明となった。その10年後、残った5人が再び鞍馬の火祭へ。宿で夕食を食べている間に語られる“4人”の告白。
以下ネタバレ全開に付き注意;
何がおかしいかというと、まず各話のラストシーンだ。彼らは銅版画の「夜行」に誘われ、怪異に出逢い、そして、飲み込まれようとしていた。そして、そこから帰ってきたという記述はないのだ。怪談のお約束のごとく、尻切れトンボになる。もちろん、語り手がそこにいるのだから、帰ってきていないはずはない。いや、本当にそうだろうか。帰ってきたのではなく、この世界に引き込まれたのだとしたら……。
少なくとも、「夜行」の世界と、「曙光」の世界、ふたつがあるのは確定している。まるで、パラレルワールドのように。そして、中井や藤村はどちらにも存在している。そして岸田も、いや、岸田は「夜行」の世界では死んでいて、「曙光」の世界では生きている。長谷川さんは「夜行」の世界から失踪した。この物語全体の語り手である大橋は「曙光」の世界から失踪した。
まったくもって不思議だ。「曙光」の世界にいた長谷川は「曙光」の長谷川であって、「夜行」の世界から失踪した長谷川ではない。大橋も逆パターンながら同様だ。なのに、大橋は「夜行」の世界から失踪した長谷川に会ったつもりで、安心と失望の入り混じった気持ちでラストシーンを迎える。
いやいや、それおかしいって!
たとえば、第1夜。中井の妻とホテルマンの妻は同一人物であって同一人物ではない。おそらくは、ふたりは「夜行」と「曙光」のように表裏の関係にある。それが、銅版画によってつながった穴によって、語り手側の世界、つまり「夜行」側でクロスオーバーしてしまった。これが俺的解釈。
しかし、そうなのであれば、長谷川もどこかでふたり存在しなければならないはずだ。
そして、尾道の向島に住む少女、リュックにスヌーピーのヌイグルミを付けた少女が長谷川なのであれば、田辺はなぜ天竜峡でそれに気づかなかったのか。それとも、彼女らは別人なのか。
長谷川は銅版画のカギを握る人物であり、おそらく、銅版画の中の女性は長谷川である。つまり長谷川は誰でもあり、誰でもない。
では大橋はどうか。「曙光」の世界から消えた大橋はどこにいったのか。
ここで、「夜行」におらず、「曙光」にいる人物を探せば、なんとなく答えがわかる。そう、岸田だ。
というわけで、「曙光」の岸田=「夜行」の大橋という説を唱えてみたいのだが、はて。
森見登美彦の小説はファンタジックなものが多いが、その内容は実にロジカルである。因果関係もはっきりしていて、オカルティックに逃げてお茶を濁すことはない。そうであるからこそ、この納得のいかなさには隠れた理由があるに違いないと思ってしまうのだ。
決して、結末をつけるのに困ってしまったとか、何年も書いていたので途中で矛盾が出てしまったわけではない……と思いたい。