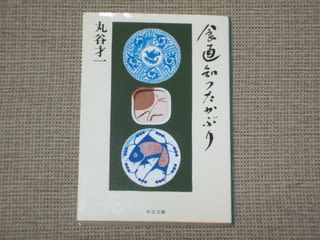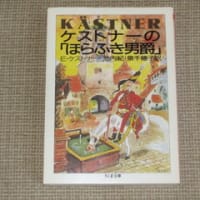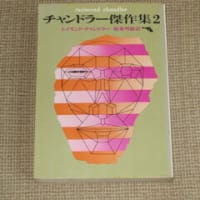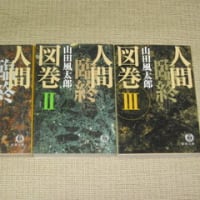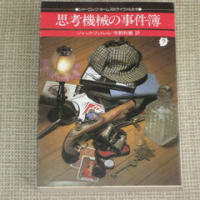丸谷才一 2010年 中公文庫版
去年の末くらいからか、なんか丸谷才一が読みたくなってしかたない。
むかし長編をいくつか読んだだけなんだけど、手元に本がそれほど無い。
もしかして当時はガッコのトショカンで借りて読んでたのかもしれない。
そんな読みたかったら、まとめて読みたいんなら、オトナなんだから、全集でも買えばいいんだろうけど、私にとって本を読むというのは、そういうもんでもないという気がする。
全集なんてのは、飾るためのものぢゃないかと秘かに思ってるから。置く場所もないしね。カネが無いのが最大の理由かもしれないが。
ということで、古本屋で、文庫を中心にボチボチ探しては買って読んでみたりしてる。
(困ったことに、どうやら今の時代というのは、文庫でもすぐ絶版になっちゃうみたいである。)
これも2月くらいだったかな、古本屋の文庫棚にあったのを見つけて、読んでみることにしたもの。
あんまり食べものの話とか集めてんのを読む趣味はないんだけど、これはとてもおもしろく、好きな本のカテゴリーに入れたくなった。
なんせ食べものの描写が、見事なんである。この作家だから、あたりまえかもしれないけど。
まず、外見を丁寧に正確に書き表すだけでも、なんともうまい。
>胡瓜のピクルズとカリフラワーと芽キャベツとセロリをそれぞれ刻んであへたもの。フォアグラ。スモークト・サーモン。小海老。キャヴィア。レバーのパイ。ゆで卵の上にイクラをのせたもの。ブルーチーズ。これだけが皿の上に目白押しにのつてゐるので、何となく嬉しくなる。
とか。(~ヨコハマ 朝がゆ ホテルの洋食)
>濃い鳶いろの二串で、同じ色のタレが皿の上に薄く流れ、それに脂のすぢが斑らに浮いてゐるのを見ただけで、そのことはよく判つた。
とか。(~岐阜では鮎はオカズである)
>次は輪島塗の蒔絵の小蓋盆にのせて、口取り。黒塗りに金ぶちの盆が、添へてある白梅のつぼみの一枚を引立て、そしてその可憐な白梅が、ドゼウの蒲焼二串、ユベシ、百合の根、菜の花の辛子あへ、河豚の一塩をさはやかに見せてゐる。
とか。(~九谷づくしで加賀料理)
>まづ、お通しが三品。穴子のしぐれ煮。これを四角い小皿にのせて。ちよいとしつこく、こころもち品のない味加減なのが、いかにも穴子らしくてよろしい。次が海老の活き造り。ワサビで。それから、海老の脚を丹念に炙つたやつを、朱泥の円い小皿にのせて。美味。
とか。(~神君以来の天ぷらの味)
しかし、いろんなものを食べるねと思うんだが、
>ほかのことならともかく、食べものにかけては、ものはためしといふ積極的な態度が肝心なのである。(~信濃にはソバとサクラと)
という姿勢なので、どこへでも行って何でも食べる。うらやましい。
さて、並んでるものを見てるだけでこれだから、それを口のなかに入れたときの書きっぷりは、それはすごいことになる。
気に入ったもの感心したもの、ここに並べ立てたら、まるで一冊まるごと抜き書きするはめになるので、そんなことはしない。
たとえば、
>和知の鮎は、大ぶりで肥つてゐて、よく脂が乗ってゐた。言ふまでもなく天然もので、炙るのは炭火。こんなに肥つてゐて味は大丈夫かしらといささか心配だつたけれど、豊饒にして脆美、まことによろしい。それは極めて淡泊でありながら、しかも同時にこの上なく豪奢な感じの、いはば奇蹟的な一品になつてゐた。
とか。(~八十翁の京料理)
>大ぶりの肉片があつさりと焼かれたのを、大きな小鉢のなかの大根おろし(これに醤油とガーリックと唐辛子と味の素をかける)にちよいとひたして口にしたとき、わたしは、ねつとりと柔くてしかも腰の強い感触にうつとりしてゐた。そのとき頭にきらめいたのは「柔媚」といふ漢語だつたが、(略)わたしはさながら年上の女の手練手管に翻弄される少年のやうにのぼせあがつたのである。
とか。(~伊賀と伊勢は牛肉の国)
>伊豆の狩野川の鮎ださうだが、わたしはこれこそ本当の鮎の天ぷらだといふ気がした。淡泊なくせに豊満、豪奢なくせに清楚。非の打ちどころのない味である。かういふ温くておいしいものを口にして噛んでゐると、今の東京でも、至福といふ言葉を思ひ出すことができる。
とか。(~神君以来の天ぷらの味)
どうしても長くなるんである。
これでもかってくらい書くんだけど、尊敬することには、
>本当は、この「傑作であつた」のあとに感嘆符を打ちたいくらゐなのだが、あの記号を添へると文章に気品がなくなるのでさうしないだけである。(ヨコハマ 朝がゆ ホテルの洋食)
というポリシーによって、「!」の数でウマイというんぢゃなくて、どれだけ文章表現できるか取り組むというのがプロだ。
ボキャブラリーも豊富だし。古来からの漢文や詩歌に詳しくなければ、こうは熟語は出てこないだろう。
ところが、圧倒されながら、「あとがき」までたどり着いたところで、タネアカシがあった。
>『食通知つたかぶり』は何よりもまづ文章の練習として書かれた。昔、與謝野晶子は弟子たちに、食べものの味のことを歌に詠むのはむづかしいからおよしなさいと教へたさうだが、散文で書くのだつてけつこう藝が要る。(略)ところどころ文壇交遊録のやうになつたり、珍味佳肴をめぐる詞華集の趣を呈したりしたけれど、主たる感心はあくまでも言葉によつてどれだけものの味を追へるかといふことにあつた。
ということだそうだ。
お見事です。文章表現の教科書にして、辞書とならべて机のそばに置いておきたくなる。
初出は昭和47年から50年にかけて、「文藝春秋」で隔月掲載されていたものらしい。
各章のタイトルは以下のとおり。
・神戸の街で和漢洋食
・長崎になほ存す幕末の味
・信濃にはソバとサクラと
・ヨコハマ 朝がゆ ホテルの洋食
・岡山に西国一の鮨やあり
・岐阜では鮎はオカズである
・八十翁の京料理
・伊賀と伊勢は牛肉の国
・利根の川風ウナギの匂ひ
・九谷づくしで加賀料理
・由緒正しい食ひ倒れ
・神君以来の天ぷらの味
・四国遍路はウドンで終る
・裏日本随一のフランス料理
・雪見としやれて長浜の鴨
・春の築地の焼鳥丼
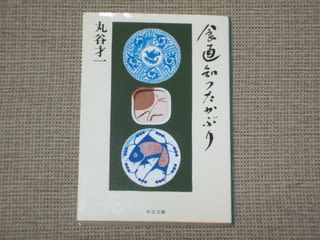
去年の末くらいからか、なんか丸谷才一が読みたくなってしかたない。
むかし長編をいくつか読んだだけなんだけど、手元に本がそれほど無い。
もしかして当時はガッコのトショカンで借りて読んでたのかもしれない。
そんな読みたかったら、まとめて読みたいんなら、オトナなんだから、全集でも買えばいいんだろうけど、私にとって本を読むというのは、そういうもんでもないという気がする。
全集なんてのは、飾るためのものぢゃないかと秘かに思ってるから。置く場所もないしね。カネが無いのが最大の理由かもしれないが。
ということで、古本屋で、文庫を中心にボチボチ探しては買って読んでみたりしてる。
(困ったことに、どうやら今の時代というのは、文庫でもすぐ絶版になっちゃうみたいである。)
これも2月くらいだったかな、古本屋の文庫棚にあったのを見つけて、読んでみることにしたもの。
あんまり食べものの話とか集めてんのを読む趣味はないんだけど、これはとてもおもしろく、好きな本のカテゴリーに入れたくなった。
なんせ食べものの描写が、見事なんである。この作家だから、あたりまえかもしれないけど。
まず、外見を丁寧に正確に書き表すだけでも、なんともうまい。
>胡瓜のピクルズとカリフラワーと芽キャベツとセロリをそれぞれ刻んであへたもの。フォアグラ。スモークト・サーモン。小海老。キャヴィア。レバーのパイ。ゆで卵の上にイクラをのせたもの。ブルーチーズ。これだけが皿の上に目白押しにのつてゐるので、何となく嬉しくなる。
とか。(~ヨコハマ 朝がゆ ホテルの洋食)
>濃い鳶いろの二串で、同じ色のタレが皿の上に薄く流れ、それに脂のすぢが斑らに浮いてゐるのを見ただけで、そのことはよく判つた。
とか。(~岐阜では鮎はオカズである)
>次は輪島塗の蒔絵の小蓋盆にのせて、口取り。黒塗りに金ぶちの盆が、添へてある白梅のつぼみの一枚を引立て、そしてその可憐な白梅が、ドゼウの蒲焼二串、ユベシ、百合の根、菜の花の辛子あへ、河豚の一塩をさはやかに見せてゐる。
とか。(~九谷づくしで加賀料理)
>まづ、お通しが三品。穴子のしぐれ煮。これを四角い小皿にのせて。ちよいとしつこく、こころもち品のない味加減なのが、いかにも穴子らしくてよろしい。次が海老の活き造り。ワサビで。それから、海老の脚を丹念に炙つたやつを、朱泥の円い小皿にのせて。美味。
とか。(~神君以来の天ぷらの味)
しかし、いろんなものを食べるねと思うんだが、
>ほかのことならともかく、食べものにかけては、ものはためしといふ積極的な態度が肝心なのである。(~信濃にはソバとサクラと)
という姿勢なので、どこへでも行って何でも食べる。うらやましい。
さて、並んでるものを見てるだけでこれだから、それを口のなかに入れたときの書きっぷりは、それはすごいことになる。
気に入ったもの感心したもの、ここに並べ立てたら、まるで一冊まるごと抜き書きするはめになるので、そんなことはしない。
たとえば、
>和知の鮎は、大ぶりで肥つてゐて、よく脂が乗ってゐた。言ふまでもなく天然もので、炙るのは炭火。こんなに肥つてゐて味は大丈夫かしらといささか心配だつたけれど、豊饒にして脆美、まことによろしい。それは極めて淡泊でありながら、しかも同時にこの上なく豪奢な感じの、いはば奇蹟的な一品になつてゐた。
とか。(~八十翁の京料理)
>大ぶりの肉片があつさりと焼かれたのを、大きな小鉢のなかの大根おろし(これに醤油とガーリックと唐辛子と味の素をかける)にちよいとひたして口にしたとき、わたしは、ねつとりと柔くてしかも腰の強い感触にうつとりしてゐた。そのとき頭にきらめいたのは「柔媚」といふ漢語だつたが、(略)わたしはさながら年上の女の手練手管に翻弄される少年のやうにのぼせあがつたのである。
とか。(~伊賀と伊勢は牛肉の国)
>伊豆の狩野川の鮎ださうだが、わたしはこれこそ本当の鮎の天ぷらだといふ気がした。淡泊なくせに豊満、豪奢なくせに清楚。非の打ちどころのない味である。かういふ温くておいしいものを口にして噛んでゐると、今の東京でも、至福といふ言葉を思ひ出すことができる。
とか。(~神君以来の天ぷらの味)
どうしても長くなるんである。
これでもかってくらい書くんだけど、尊敬することには、
>本当は、この「傑作であつた」のあとに感嘆符を打ちたいくらゐなのだが、あの記号を添へると文章に気品がなくなるのでさうしないだけである。(ヨコハマ 朝がゆ ホテルの洋食)
というポリシーによって、「!」の数でウマイというんぢゃなくて、どれだけ文章表現できるか取り組むというのがプロだ。
ボキャブラリーも豊富だし。古来からの漢文や詩歌に詳しくなければ、こうは熟語は出てこないだろう。
ところが、圧倒されながら、「あとがき」までたどり着いたところで、タネアカシがあった。
>『食通知つたかぶり』は何よりもまづ文章の練習として書かれた。昔、與謝野晶子は弟子たちに、食べものの味のことを歌に詠むのはむづかしいからおよしなさいと教へたさうだが、散文で書くのだつてけつこう藝が要る。(略)ところどころ文壇交遊録のやうになつたり、珍味佳肴をめぐる詞華集の趣を呈したりしたけれど、主たる感心はあくまでも言葉によつてどれだけものの味を追へるかといふことにあつた。
ということだそうだ。
お見事です。文章表現の教科書にして、辞書とならべて机のそばに置いておきたくなる。
初出は昭和47年から50年にかけて、「文藝春秋」で隔月掲載されていたものらしい。
各章のタイトルは以下のとおり。
・神戸の街で和漢洋食
・長崎になほ存す幕末の味
・信濃にはソバとサクラと
・ヨコハマ 朝がゆ ホテルの洋食
・岡山に西国一の鮨やあり
・岐阜では鮎はオカズである
・八十翁の京料理
・伊賀と伊勢は牛肉の国
・利根の川風ウナギの匂ひ
・九谷づくしで加賀料理
・由緒正しい食ひ倒れ
・神君以来の天ぷらの味
・四国遍路はウドンで終る
・裏日本随一のフランス料理
・雪見としやれて長浜の鴨
・春の築地の焼鳥丼