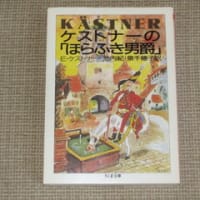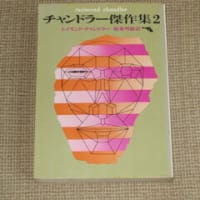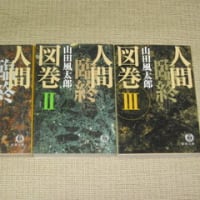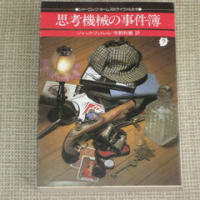E・ケストナー/池内紀・泉千穂子訳 二〇〇〇年 ちくま文庫版
これは今年2月に地元の古本屋で買った文庫。棚を見ていて、あーこんなのあるんだって、手に取ったら、まあふつうの値段だし、読みたくなってしまった。
たしか学生んとき、ドイツ語のテキストで「ほらふき男爵」読んだと思うんだけど、あれはケストナー版だったのかどうかまではおぼえちゃいない。
訳者解説によると、オマージュとかぢゃなく、「再話」であるということらしい。(文学では、カバーとは言わんのかな。)
ナチス・ドイツによって本を焼き捨てられて、執筆・出版を禁じられたケストナーは、どっか亡命したりしないでドイツにとどまり、再話を書いてスイスの出版社から絵本にしたんだという、それが1938年の「オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」。
タイトルの「ほらふき男爵」が絵本になったのは戦後の1952年だけど、戦時中に映画のシナリオとして書いたら、作者名つけなかったのにやっぱナチスに目をつけられたらしい。
本書読んでみたら、「ドン・キホーテ」とか「ガリバー旅行記」があったのが意外、それってスペインとかイギリスじゃんねえ、ドイツのもの以外も取り扱うんだ、って。
「ほらふき男爵」はだいたい知ってたような話なんで、一読したなかでは、「シルダの町の人びと」がおもしろかったかな。
まだ火薬が発明されていなかったころのこと、ドイツのへそにあたるあたりにあった、シルダという町の人びとがちょっと変わってたって話。
人の話は真に受けるけど、おかしなことばかりするので、はっきり言って他の町の人たちからは手のつけられないバカ者と思われ、国じゅうの笑いものになっていたという。
しかし、
>シルダの町の人びとは、バカだったのではない。バカのふりをしていただけ。(p.90)
なんだという。
もとは勤勉で有能でしっかり者ぞろいだったんだけど、それで皇帝や国王や太守から招かれることが多く、男たちが町を留守にしているあいだに町は荒れてしまった。
そこでみんな町にかえってきて相談したんだけど、よその地方や国から放っておかれるためには、バカなふりをするしかなかろう、って結論に至る。
バカなふりをしてると本当にバカになっちゃわないかって懸念もあったんだけど、実行に移すのみと突き進んだ結果、心配したとおりになっちゃう。
いいじゃん、それでみんなハッピーなら。
本書のコンテンツは以下のとおり。
ほらふき男爵
はじめに
教会の塔にのぼった馬のこと
馬を丸呑みした狼のこと
大酒飲みの将軍
じゅずつなぎの鴨、ならびにさまざまな狩りの話
まっぷたつの「リトアニア人」
砲弾にまたがって飛んだこと、ならびにそのほかの冒険
トルコの太守と賭けをしたこと
いまひとたびの月世界旅行
ドン・キホーテ
はじめに
晴れの騎士叙任式
十字路の戦い
風車との戦い
かぶと半分、耳半分
魔法の宿
天と地のあいだ
カゴに入って帰郷する
水城と水辺の冒険
木馬にのって空を飛ぶ
バルセロナにて
シルダの町の人びと
シルダの町の人びとは、ほんとうにバカだったのか
シルダの町の人びと、町役場を建てる
シルダの町の人びと、共有地で塩をそだてる
シルダの町の町長は詩人にかぎる
皇帝、シルダの町を訪問する
シルダの町の人びと、牛を壁にのぼらせる
シルダの町の人びと、教会の鐘を沈める
シルダの町の人びと、ザリガニを裁判にかける
シルダの町の仕立て屋の心臓はどこにあるか
シルダの町では、むろん、教育は一日にしてならず
シルダの町の顛末、かつは愚か者を見わけるしるしについて
オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら
読者諸君!
オイレンシュピーゲルが三度の洗礼を受けたこと
オイレンシュピーゲルが綱渡りを覚えたしだい
オイレンシュピーゲルが蜂の巣で眠ったこと
オイレンシュピーゲルが病人の治療をしたこと
オイレンシュピーゲルが、ふくろうと尾なが猿を焼いたこと
オイレンシュピーゲルがラッパ吹きになったこと
オイレンシュピーゲルが土地を買うこと
オイレンシュピーゲルがロバに文字を教えたこと
オイレンシュピーゲルが仕立て屋に教えをたれたこと
風が三人の仕立て職人を空に吹きとばしたこと
オイレンシュピーゲルが毛皮職人をだましたこと
オイレンシュピーゲルがミルクを買い占めたこと
ガリバー旅行記
はじめに
君子危うきに近よらず
千五百頭の馬で千五百メートル
皇帝のあらたな悩み
つまさき立ちして首都見物
戦艦略奪
新しいシャツと強敵
きなくさい話
別れ、そして帰郷
巨人がひとり、またひとり……
大男と大音響
十メートル以下の子どもは半額
首都の生活
海に浮かぶ家
長靴をはいた猫
まだ猫は出てこない
遺産わけ
なみの猫じゃない
ほしいものが三つ
シャコのお見舞い
猫、ふたたびまかり出る
ハンスは川で水あび
してやったり
カラバス伯爵の婚礼

これは今年2月に地元の古本屋で買った文庫。棚を見ていて、あーこんなのあるんだって、手に取ったら、まあふつうの値段だし、読みたくなってしまった。
たしか学生んとき、ドイツ語のテキストで「ほらふき男爵」読んだと思うんだけど、あれはケストナー版だったのかどうかまではおぼえちゃいない。
訳者解説によると、オマージュとかぢゃなく、「再話」であるということらしい。(文学では、カバーとは言わんのかな。)
ナチス・ドイツによって本を焼き捨てられて、執筆・出版を禁じられたケストナーは、どっか亡命したりしないでドイツにとどまり、再話を書いてスイスの出版社から絵本にしたんだという、それが1938年の「オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」。
タイトルの「ほらふき男爵」が絵本になったのは戦後の1952年だけど、戦時中に映画のシナリオとして書いたら、作者名つけなかったのにやっぱナチスに目をつけられたらしい。
本書読んでみたら、「ドン・キホーテ」とか「ガリバー旅行記」があったのが意外、それってスペインとかイギリスじゃんねえ、ドイツのもの以外も取り扱うんだ、って。
「ほらふき男爵」はだいたい知ってたような話なんで、一読したなかでは、「シルダの町の人びと」がおもしろかったかな。
まだ火薬が発明されていなかったころのこと、ドイツのへそにあたるあたりにあった、シルダという町の人びとがちょっと変わってたって話。
人の話は真に受けるけど、おかしなことばかりするので、はっきり言って他の町の人たちからは手のつけられないバカ者と思われ、国じゅうの笑いものになっていたという。
しかし、
>シルダの町の人びとは、バカだったのではない。バカのふりをしていただけ。(p.90)
なんだという。
もとは勤勉で有能でしっかり者ぞろいだったんだけど、それで皇帝や国王や太守から招かれることが多く、男たちが町を留守にしているあいだに町は荒れてしまった。
そこでみんな町にかえってきて相談したんだけど、よその地方や国から放っておかれるためには、バカなふりをするしかなかろう、って結論に至る。
バカなふりをしてると本当にバカになっちゃわないかって懸念もあったんだけど、実行に移すのみと突き進んだ結果、心配したとおりになっちゃう。
いいじゃん、それでみんなハッピーなら。
本書のコンテンツは以下のとおり。
ほらふき男爵
はじめに
教会の塔にのぼった馬のこと
馬を丸呑みした狼のこと
大酒飲みの将軍
じゅずつなぎの鴨、ならびにさまざまな狩りの話
まっぷたつの「リトアニア人」
砲弾にまたがって飛んだこと、ならびにそのほかの冒険
トルコの太守と賭けをしたこと
いまひとたびの月世界旅行
ドン・キホーテ
はじめに
晴れの騎士叙任式
十字路の戦い
風車との戦い
かぶと半分、耳半分
魔法の宿
天と地のあいだ
カゴに入って帰郷する
水城と水辺の冒険
木馬にのって空を飛ぶ
バルセロナにて
シルダの町の人びと
シルダの町の人びとは、ほんとうにバカだったのか
シルダの町の人びと、町役場を建てる
シルダの町の人びと、共有地で塩をそだてる
シルダの町の町長は詩人にかぎる
皇帝、シルダの町を訪問する
シルダの町の人びと、牛を壁にのぼらせる
シルダの町の人びと、教会の鐘を沈める
シルダの町の人びと、ザリガニを裁判にかける
シルダの町の仕立て屋の心臓はどこにあるか
シルダの町では、むろん、教育は一日にしてならず
シルダの町の顛末、かつは愚か者を見わけるしるしについて
オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら
読者諸君!
オイレンシュピーゲルが三度の洗礼を受けたこと
オイレンシュピーゲルが綱渡りを覚えたしだい
オイレンシュピーゲルが蜂の巣で眠ったこと
オイレンシュピーゲルが病人の治療をしたこと
オイレンシュピーゲルが、ふくろうと尾なが猿を焼いたこと
オイレンシュピーゲルがラッパ吹きになったこと
オイレンシュピーゲルが土地を買うこと
オイレンシュピーゲルがロバに文字を教えたこと
オイレンシュピーゲルが仕立て屋に教えをたれたこと
風が三人の仕立て職人を空に吹きとばしたこと
オイレンシュピーゲルが毛皮職人をだましたこと
オイレンシュピーゲルがミルクを買い占めたこと
ガリバー旅行記
はじめに
君子危うきに近よらず
千五百頭の馬で千五百メートル
皇帝のあらたな悩み
つまさき立ちして首都見物
戦艦略奪
新しいシャツと強敵
きなくさい話
別れ、そして帰郷
巨人がひとり、またひとり……
大男と大音響
十メートル以下の子どもは半額
首都の生活
海に浮かぶ家
長靴をはいた猫
まだ猫は出てこない
遺産わけ
なみの猫じゃない
ほしいものが三つ
シャコのお見舞い
猫、ふたたびまかり出る
ハンスは川で水あび
してやったり
カラバス伯爵の婚礼