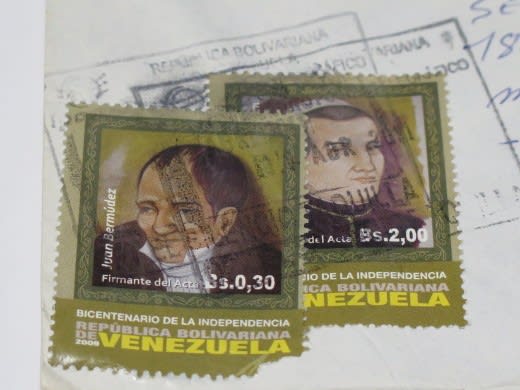JW - Svalbard
ノルウェー領の島なので切手は、NORGE(英語ではNorway)と共通であるが
消印に中心都市のLONGYEARBYENがしっかり押されていたのでJWからだと判った。
ノルウェーはスカンジナビア半島西岸の他に、JX(Jan Mayen)、JW(Svalbard)、南氷洋の3Y(Bouvet)を
領土に持っており、ノルウェー自身は3Y/P(Peter1)の領有も主張しているが南極条約から認められていない。
そんな領土の一つであるSvalbardであるが、ヴァイキングの古文書にはそれらしい情報が見られるものの
歴史に明確に出てくるのは16世紀頃、欧州各国の捕鯨隊が寄る捕鯨基地として活用される。当時はどの国の領有か
曖昧だったようだが、19世紀末から20世紀にかけて資源採掘(石炭)のために各国が人をこの地に送り込む。
そこで1920年にパリ会議の席でスヴァールバル条約が締結され、ノルウェーの領有権は認めるが、条約加盟国すべては
ノルウェーの法律に従うことなく独自にこの地で経済活動ができる、と言うものである。ちなみに我が国は1920年からの原加盟国である。
無線の上では本国の人が島から運用するケースが度々あるので左程珍しくは無いが
極地からの運用であるので、年がら年中と言うわけにはいかない。
この地には、Svalbard Global Seed Vault(スヴァールバル世界種子貯蔵庫)と言う施設が出来ている。
いわゆるノアの箱舟で、世界の終末の日に備えた種子の貯蔵庫、なのだそうだ。資金協力者はあのビルゲイツだ。
Exploring the Arctic's Global Seed Vault
450万種類の種子を1品種当たり500粒保存し、ただ保存するだけでなくちゃんと種子を定期的に入れ替えて
保存している様だ。
なお、この施設には、故)田辺光彰氏の野生稲モニュメント作品が貯蔵庫VIPルーム壁面に飾られているとのことだ。
そんなSvalbard、2015年にロシアの後押しを得て新たにスヴァールヴァル条約に加わった加盟国がある。
P5 北朝鮮である。
アンダーグラウンドのゴシップ記事しか無いが、噂では万一の際の亡命先としてこの地が選ばれているとのこと。
国家元首も植物の種子もみんなが一緒に乗るノアの箱舟
Svalbardは、そんな地になりかねない。
露欧米(加)の三地域からほぼ同距離に位置するSvalbard
地の利を活かした活用方法は無いものだろうか。