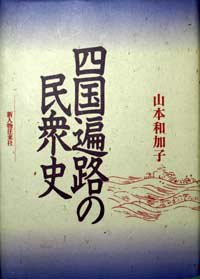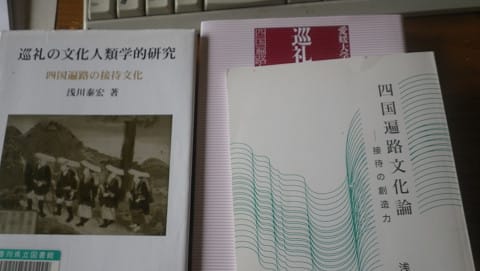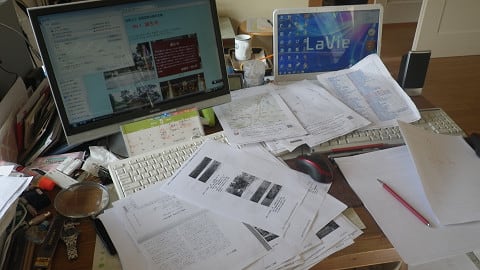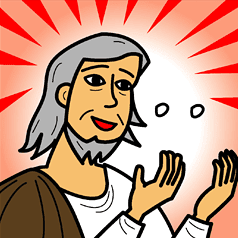さぬき市地方は高気圧に覆われて概ね晴れていたが、一時、雲が広がり雨の降っている所があったという。気温は21度から31度、湿度は94%から63%・風は1mから4mの南東の風が吹いたりもした。明日の3日は、前線や低気圧の影響で雨が降り、昼過ぎからは雷を伴う所がある見込みとか。

今日は「半夏生」の日。半夏生(はんげしょう)は雑節の1つで、半夏(カラスビシャク)という薬草が生える頃。一説に、ハンゲショウ(カタシログサ)という草の葉が名前の通り半分白くなって化粧しているようになる頃とも言う。本来は七十二候の1つ「半夏生」(はんげしょうず)から作られた暦日で、かつては夏至から数えて11日目としていたが、現在では天球上の黄経100度の点を太陽が通過する日となっていて、毎年7月2日頃にあたる。この頃に降る雨を「半夏雨」(はんげあめ)と言い、大雨になることが多い。地域によっては「半夏水」(はんげみず)とも言うらしい。

昨日、瀬戸内海歴史民俗資料館で、このパンフレットを見つけたので、今日は高松市玉藻町にある「香川県立ミュージアム」に行ってみた。高松城の東手、香川県民ホール近くにある建物で、少し前までは「香川県立歴史資料館」とか言うておったような・・・。

すると、県展をやっているというので、順路上だからと、まずは県展から見ることにした。

これは、65歳の誕生日になればいただける「長寿手帳」。これを受付で提示をすれば、このミュージアムは無料で見学できる。

今季の県展は「書」の部門。これでも「書」なのか?と思うような作品が眼に付いた。当然、普通の楷書体とか草書体とか隷書体とかの作品も並んではいる。これは書ではなくて「絵」だろう・・と思うようなものもあった。でも、どの作品も「落書きだな」と思うようなものは一つとしてない(当然なのだが)。

香川県美術展覧会(通称「県展」)は、県民の日頃の創作活動の成果である優れた美術作品を展覧し、美術に対する理解と鑑賞の機会とするため、昭和9年から始まっている全国で最も歴史のある、地域に根ざした公募展で、今年で79回目の開催となる。

その後、常設展示の空海展を見たあと、今回の特別展示の「撃てっ!」の火縄銃の展示を見た。戦国時代に普及し、強力な兵器として定着した火縄銃。大名家の軍団に大量の鉄炮が配備される一方、将軍や大名自身が鉄炮を愛用するということも行われた。鉄炮を所有したのは武士階級の者だけではなく、江戸時代の農村や山村にも多数の鉄炮が存在し、その総数は武士階級のそれをはるかに上回る数であったともいわれている。

この展覧会では、このミュージアムが収蔵する火縄銃やその他の鉄砲を展示し、古文書や古記録から近世において鉄砲がどのように位置づけられ、取り扱われてきたのかを見せてくれている。(写真は図録から)

毎年7月2日頃に暦の上の「半夏生(はんげしょう)」が来るが、この日を「うどんの日」と1980年に香川県生麺事業協同組合が制定し、以来「半夏生」の日が「うどんの日」になっている。農家においては田植え終了の目安の日。半夏生(はんげしょう)のころは、天から毒気が降るという言い伝えがあって、井戸に蓋をしたり、酒や肉を断ったり、野菜や筍を食べるのを控えたりする風習が各地にあった。讃岐地方の農家では半夏生のころ、田植えや麦刈りが終わった労をねぎらう為に、うどんを打って食べる風習があった。それにちなんで「うどんの日」の由来となったということだ。

ということで、久々にここにやってきた。さぬき市長尾西笠堂にある「笠堂や」というプチセルフのお店。ここも半年ぶりくらいになる。

で、夏らしく、「梅おろしぶっかけうどん小の冷や」をお願いした。ま、早く言えば、普通のぶっかけうどんに大根おろしと大きな南校梅を乗せたもの。大根おろしに梅の酸っぱさが混じって、暑さを忘れるような味だった。これで330円。そろそろとうどんの味にも慣れてきて、おいしくうどんが食べられるようになった。

火縄銃つながりで、鎌田共済会郷土博物館にも寄ってみたかったのだが、少し方角が違うもので、明日にでも行ってみようと思っている。それに、東かがわ市歴史民俗資料館にも・・・。

今日の掲示板は右側のこれ。「命には所有権もなく価格もつけられないからこそ尊いのです」というもの。これまた、意表を突くような言葉。ググってみても出典も出拠もわからない。「いのち」の所有権とか、「いのち」の価格・・・というのは民事裁判を連想するんだけれど、この場合にはそういう話ではない。命の大きさとか、いのちの重さとか、いのちの形とか・・・、とにかく、そういうものではかることができないから、いのちって、尊いのだと思うし、それぞれに違っているからこそ、尊いものだと思う・・・。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね。