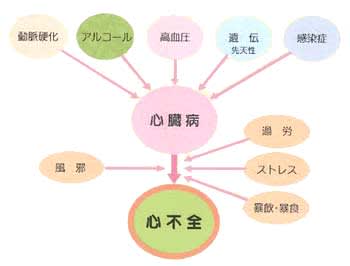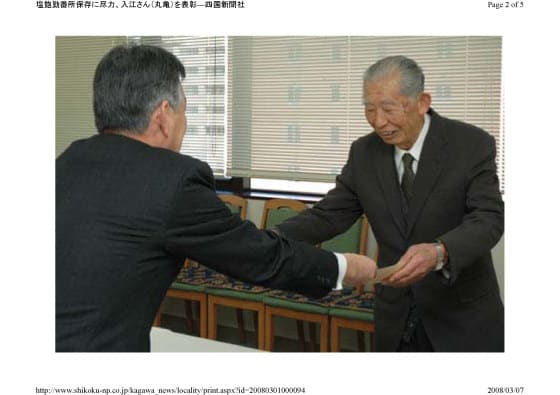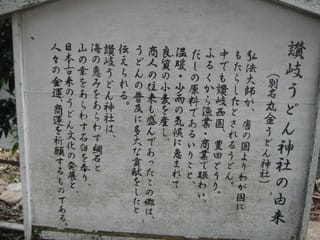まして・・雨季には・・虫などの生き物がごそがさと這い出してくる。そういう時期に歩いたら虫たちを踏みつぶしてしまう・・。だから・・歩けない・・。
だから・・この・・雨の時期には出歩かずに・・お勉強をするようになった。これを・・「安居:あんご」といい、「安居寮」というものができて、お勉強をする時期になった・・。京都の「龍谷大学」の前身も・・その・・「安居寮」というものやった・・。

だからして・・、本山あたりでは、この時期に勉強会を開く・・。これを・・「安居」といい、この時期には・・「安居寮」が開設される・・。
そういうことで・・京都の本山に・・お勉強に行った訳だ・・。
平成10年頃からは・・毎年・・お勉強に行ってたんだけれど、あの台風があってからは・・それどころやなくなって・・しばらくお休みをしていたんだけれど、時間的な余裕も生まれたもので・・久々に・・京都に行ったってわけだ。

朝の五時半に起きて・・お隣の西本願寺の「おあさじ」という六時からのおつとめに出て・・・おなかをすかせておいて・・、七時からの朝食・・。これがおいしんだ・・。で・・八時からは・・うちの寺の「晨朝:じんじょう」という朝のお勤めに出る。これにはご門主さまがご出仕される大事な朝のお仕事。
これが終われば・・講義が始まる・・。今回は「浄土論註」に学ぶ・・・という難しいお話。

昔の中国に・・曇鸞大師という方がいて・・あるとき、病気になった。そこで、不老長寿の秘法を学んだが、三蔵流支という仏師に出会い、「数年ほど長生きしたところで何になるのか。この経典には永遠の命が説かれていると」教えられ、その仙術の教典を焼き捨てて仏教に帰依した。そして書き上げた書物が・・「浄土論註」という解説書ということ。
その・・お勉強という訳だが・・大学の講義並みだから・・・難しい,難しい・・。

ま、最後には試験というか、レポート提出があるから・・寝るわけにもいかないし・・。あ、このおばちゃん・・寝てはるなぁ・・。
二泊三日の研修会だけれど、宿泊費と食費は無料・・。交通費だけ出せばお勉強代がただだということで・・全国からお坊さんたちがやってきている。この講師の先生は西本願寺の「補教」という偉い先生らしい・・。
私が本山で勉強したときの教授が、「田舎の勉強よりも、都の昼寝」ということを教えてくれたが、田舎でいくら勉強しても勉強にはならないが、都で昼寝をしていてもなんだかんだとお勉強になる・・みたいなお話やった・・。確かに・・そう思うことがしばしば・・。

普段には知ることのできない・・本山の最新情報やら、仏教界の動きや流れ・・、お寺さんの持つ悩みやら・・お坊さんたちの生の生活のありようだとか・・。
皆さんは・・右足から歩き出しますか、左足からですかね・・。意識したことはないですかね・・。お坊さんは・・左足から歩かないといかんのです。階段を上るにも・・・左足をあげて段に上がり、右足を上げてそろえる。「左・右」「左・右」と一段ずつ上がるんです。右足で一段、左足で二段・・みたいに、普通は歩くでしょ・・。これを・・「さ(左)・う(右)」「さ・う」というんですね・・。
この左から歩くのはなぜか・・みたいな話。左大臣が上職で、右大臣がその下・・みたいな位置関係にあるとか・・。お雛さんのお内裏さんは左に置くとか・・。つまらん話の中にも・・「なるほど・・」というようなお話があちこちで聞こえる・・。さすが・・お坊さんの世界やね。

最近は・・便利になったものか、合理化なのか・・、昼食と夕食はこういう・・お弁当にペットボトルのお茶・・。ま、無料だから・・・おいしいですよ。
朝食だけは・・お茶碗にお味噌汁・納豆・のり・・などのセルフサービスで食べ放題・・・。これがまた・・おいしい。
夜は・・自習とか自分でのお勉強・・・。ま、ほとんどが夜の京都の町に消えて・・おふとんだけが並んでますわ・・。
じゃぁ、また。