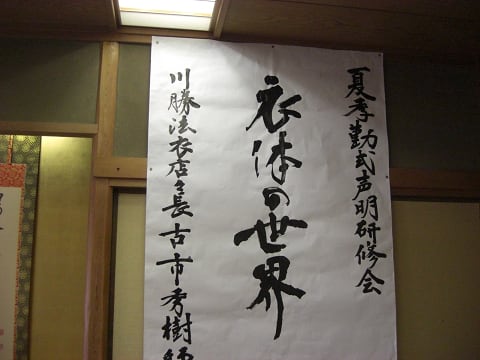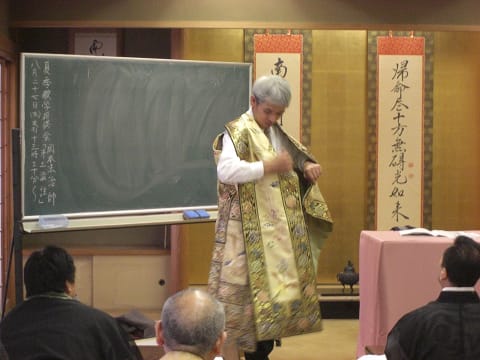またしても書いたばかりのブログを消してしまった・・・。再度・・書き直し。
今朝は雨で始まった・・。雨だからと、先日のさぬき広島で出会った・・草刈りボランティアのおじさんに頼まれたお勉強を始めてみた・・・。このおじさんのいうことには・・「未来に語り継ぎたい話」としての「英国士官レキの墓」を元にして・・2016年には・・「150周年記念レキ祭り」をやろう・・・というものだ。2016年というのは、その海軍士官レキさんが亡くなった・・慶応(けいおう)二年(1866年)から数えて150年後ってことだ・・。
このおじさん・・内緒だけれど、実は丸亀市役所のとある部長さんなんだ。そういう人と・・草刈りを通じて・・お友達になってしまって・・。そのなりゆきで・・「レキ祭り」にかかわりあうことになった・・・。
ま・・深い話は別として・・。

これが・・広島沖で海底調査をやった「英国軍艦シルビア号」と行動をともにした「第一丁卯(だいいちていぼう)丸」で、これに長崎伝習所で測量術を学んだ「柳楢悦:やなぎならよし」が乗っていて、レキらと行動をともにした・・というのだ。
そこでは勝海舟とか咸臨丸乗り組みの水夫らと出あっていたはずなんだという・・。そういう可能性がないでもないのだけれど・・。
そういうことで、私はその基礎調査をやっていたわけだ。で、最新鋭のレーザープリンターで資料をどんどこと吐き出して・・百ページほどの資料ができた。インクジェットとは違って早くてきれいだなぁと感心する・・。

で・・十時過ぎからけいこばぁと・・三木町にある動物病院「光昇堂」で、ゴンちゃんの薬を買いに行く。一錠だけで・・1200円もする。これを明日の朝・・飲ませれば・・今度は五月まで要観察・・・。最近は倒れたりはしないのでたぶん、大丈夫だろうとは思うのだけれど・・。
で・・、とあるスーパーで(というてもこのあたりでは・・マルナカなんだけれど)食材を買ったら・・こんなものが眼に着いた・・。

韓国製の発泡酒で・・350mlの24本詰で1980円と言う安さ・・。試しに・・6本だけ買ってみたけれど・・飲みやすくてクセがない・・。まさに・・「のみごろ」なんだなぁと思う・・・。これはいいなぁと思った。のどに優しいし、お財布にも家計にもやさしい・・。
その後・・、けいこばぁが一度は行きたい・・と言うてたおうどん屋さん「滝音:たきね」に行ってみた。私は何度も行ったことがあるんだけれど、お昼になると道路は混むし、駐車場はいっぱいになるわで・・人気のお店。だから・・11時前でないと落ち着いておうどんが食べられない・・。ま、混んでいたり、行列が好きな方もおいでにはなるのだけれど。

そうはいうても・・普通のうどん屋さんだからね・・。特別・・金や銀のおうどんがあるわけやない・・・。行列をしてまで食べるような特別なおうどんでもない・・。普通の・・さぬきにある・・おうどんなんだけれど。
で・・けいこばあは・・いつものかけうどん小におでん・・。私はしっぽくうどんが希望だったけれど、ここにもしっぽくはない・・。仕方がないので・・ぶっかけ小のぬくいん・・を注文した・・。250円であったような・・。

このおうどんの中のレモンがねぇ・・最後までお出汁に残っていて・・なんとなくトロピカルな風味になったのが印象的・・・。レモン味のおうどん・・・みたいな。
けいこばぁは・・「おいしいおいしい・・」を連発してかけうどんを食べていた。そんなに感動するような味でもおうどんでもないとは思うのだけれど、確かに麺がおいしいし、なめらかでつやがある・・。お出汁もそれなりにおいしいから・・最後の最後まで飲みほしてしまえる・・。残すのがもったいなくなるようなお出汁だし・・。ま、お勧めのお店ではあるね・・。

そんなんで・・午後からも・・引き続いて・・幕府軍艦一覧とか・・海上保安庁水路部情報とか・・を調べていて日が暮れた・・・。
じゃぁ、また、明日、会えるといいね。
今朝は雨で始まった・・。雨だからと、先日のさぬき広島で出会った・・草刈りボランティアのおじさんに頼まれたお勉強を始めてみた・・・。このおじさんのいうことには・・「未来に語り継ぎたい話」としての「英国士官レキの墓」を元にして・・2016年には・・「150周年記念レキ祭り」をやろう・・・というものだ。2016年というのは、その海軍士官レキさんが亡くなった・・慶応(けいおう)二年(1866年)から数えて150年後ってことだ・・。
このおじさん・・内緒だけれど、実は丸亀市役所のとある部長さんなんだ。そういう人と・・草刈りを通じて・・お友達になってしまって・・。そのなりゆきで・・「レキ祭り」にかかわりあうことになった・・・。
ま・・深い話は別として・・。

これが・・広島沖で海底調査をやった「英国軍艦シルビア号」と行動をともにした「第一丁卯(だいいちていぼう)丸」で、これに長崎伝習所で測量術を学んだ「柳楢悦:やなぎならよし」が乗っていて、レキらと行動をともにした・・というのだ。
そこでは勝海舟とか咸臨丸乗り組みの水夫らと出あっていたはずなんだという・・。そういう可能性がないでもないのだけれど・・。
そういうことで、私はその基礎調査をやっていたわけだ。で、最新鋭のレーザープリンターで資料をどんどこと吐き出して・・百ページほどの資料ができた。インクジェットとは違って早くてきれいだなぁと感心する・・。

で・・十時過ぎからけいこばぁと・・三木町にある動物病院「光昇堂」で、ゴンちゃんの薬を買いに行く。一錠だけで・・1200円もする。これを明日の朝・・飲ませれば・・今度は五月まで要観察・・・。最近は倒れたりはしないのでたぶん、大丈夫だろうとは思うのだけれど・・。
で・・、とあるスーパーで(というてもこのあたりでは・・マルナカなんだけれど)食材を買ったら・・こんなものが眼に着いた・・。

韓国製の発泡酒で・・350mlの24本詰で1980円と言う安さ・・。試しに・・6本だけ買ってみたけれど・・飲みやすくてクセがない・・。まさに・・「のみごろ」なんだなぁと思う・・・。これはいいなぁと思った。のどに優しいし、お財布にも家計にもやさしい・・。
その後・・、けいこばぁが一度は行きたい・・と言うてたおうどん屋さん「滝音:たきね」に行ってみた。私は何度も行ったことがあるんだけれど、お昼になると道路は混むし、駐車場はいっぱいになるわで・・人気のお店。だから・・11時前でないと落ち着いておうどんが食べられない・・。ま、混んでいたり、行列が好きな方もおいでにはなるのだけれど。

そうはいうても・・普通のうどん屋さんだからね・・。特別・・金や銀のおうどんがあるわけやない・・・。行列をしてまで食べるような特別なおうどんでもない・・。普通の・・さぬきにある・・おうどんなんだけれど。
で・・けいこばあは・・いつものかけうどん小におでん・・。私はしっぽくうどんが希望だったけれど、ここにもしっぽくはない・・。仕方がないので・・ぶっかけ小のぬくいん・・を注文した・・。250円であったような・・。

このおうどんの中のレモンがねぇ・・最後までお出汁に残っていて・・なんとなくトロピカルな風味になったのが印象的・・・。レモン味のおうどん・・・みたいな。
けいこばぁは・・「おいしいおいしい・・」を連発してかけうどんを食べていた。そんなに感動するような味でもおうどんでもないとは思うのだけれど、確かに麺がおいしいし、なめらかでつやがある・・。お出汁もそれなりにおいしいから・・最後の最後まで飲みほしてしまえる・・。残すのがもったいなくなるようなお出汁だし・・。ま、お勧めのお店ではあるね・・。

そんなんで・・午後からも・・引き続いて・・幕府軍艦一覧とか・・海上保安庁水路部情報とか・・を調べていて日が暮れた・・・。
じゃぁ、また、明日、会えるといいね。