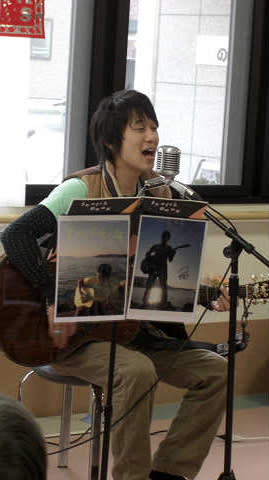さて、今日も大霜の朝になった。きっと、いい天気になるなぁと思った。気象予報士ではないのだけれど・・。
円覚寺の「叶丸難船図絵馬」は、遭難を免れた感謝を込めて奉納されたもので、荒れ狂う大波に翻弄(ほんろう)される弁才船の姿が描かれている。叶丸(かのうまる)は松前藩の御用船で、これと全く同じ絵馬が、北海道松前町の渡海神社(とかいじんじゃ)にも奉納されている。


遭難時には帆を下ろし、船を安定させるため船首から碇(いかり)を垂らした。時には自ら帆柱を切り倒すこともあった。どうしようもなくなると、乗組員は丁髷(ちょんまげ)のモトドリを切って、神仏の加護を一心に祈った。その願いが通じたのか、この絵馬では、神仏が瑞雲に乗り、御幣(ごへい)に姿を変えて、救いに現れている。


遭難を免れた後でも、御礼として、神仏との約束に従って自分の丁髷を切り、これを絵馬として奉納する風習があった。円覚寺には「髷額」(まげがく)と呼ばれる丁髷の絵馬が多く残されており、全国的にも貴重な資料となっている。
で・・さぬき広島にある海難絵図だが・・

左上に剥落しているが・・御幣が描かれていた跡が見える・・。写真では見えないのだけれど。上の画像の叶丸の絵馬では右上に御幣があるが、普通は・・左上に御幣や阿弥陀、釈迦三尊、紫雲などが描かれるという・・。下の画像左の左上に御幣が見える。


上段右側は西洋の海難絵馬だが、同じように左上端にマリア様が描かれている。
さて・・広島神社の絵馬の前の部分に、二人の水夫が合掌して神仏に祈る姿が見える。この時代、嵐に遭遇した場合には、帆を下ろし、あるいは帆柱を切り倒し、錨を前に入れ、まげを切り、紙くじを引き、最後には神仏に祈るしかない・・。

さて、この向井さんの絵馬は、遭難時にロープを後ろに流して船を安定させているということで、大いに参考になるということで取り上げられる海難絵馬なのだが、当日に参加した会員さんから、「ロープを後ろに流すのは不自然ではないか」という意見が出た。ガフという前帆を出して前を安定させているならば、ロープも前に流さないと意味がないし、ガフが風を後ろから受けているから、ロープを後ろに流しても前に流れてしまう・・・という意見が出た・・・。なるほどなぁ・・。それはそうだ。

これは、同じ広島神社にあった海難絵馬の一つの「白賀氏」のものだが、荷物の米俵を海の中に投げ捨てている。これを「跳ね荷」といい、「捨て荷」「荷打」とか言われて、船のバランスを保つために荷物を捨てることをいうらしい。白くなった部分の上側に米俵が山積みになっている。その海のほうには・・米俵が投げ込まれている図が見える。
ま、おおまかだけれど、海難絵馬には、こうしたものが見えてくるというお話だった。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね。
円覚寺の「叶丸難船図絵馬」は、遭難を免れた感謝を込めて奉納されたもので、荒れ狂う大波に翻弄(ほんろう)される弁才船の姿が描かれている。叶丸(かのうまる)は松前藩の御用船で、これと全く同じ絵馬が、北海道松前町の渡海神社(とかいじんじゃ)にも奉納されている。


遭難時には帆を下ろし、船を安定させるため船首から碇(いかり)を垂らした。時には自ら帆柱を切り倒すこともあった。どうしようもなくなると、乗組員は丁髷(ちょんまげ)のモトドリを切って、神仏の加護を一心に祈った。その願いが通じたのか、この絵馬では、神仏が瑞雲に乗り、御幣(ごへい)に姿を変えて、救いに現れている。


遭難を免れた後でも、御礼として、神仏との約束に従って自分の丁髷を切り、これを絵馬として奉納する風習があった。円覚寺には「髷額」(まげがく)と呼ばれる丁髷の絵馬が多く残されており、全国的にも貴重な資料となっている。
で・・さぬき広島にある海難絵図だが・・

左上に剥落しているが・・御幣が描かれていた跡が見える・・。写真では見えないのだけれど。上の画像の叶丸の絵馬では右上に御幣があるが、普通は・・左上に御幣や阿弥陀、釈迦三尊、紫雲などが描かれるという・・。下の画像左の左上に御幣が見える。


上段右側は西洋の海難絵馬だが、同じように左上端にマリア様が描かれている。
さて・・広島神社の絵馬の前の部分に、二人の水夫が合掌して神仏に祈る姿が見える。この時代、嵐に遭遇した場合には、帆を下ろし、あるいは帆柱を切り倒し、錨を前に入れ、まげを切り、紙くじを引き、最後には神仏に祈るしかない・・。

さて、この向井さんの絵馬は、遭難時にロープを後ろに流して船を安定させているということで、大いに参考になるということで取り上げられる海難絵馬なのだが、当日に参加した会員さんから、「ロープを後ろに流すのは不自然ではないか」という意見が出た。ガフという前帆を出して前を安定させているならば、ロープも前に流さないと意味がないし、ガフが風を後ろから受けているから、ロープを後ろに流しても前に流れてしまう・・・という意見が出た・・・。なるほどなぁ・・。それはそうだ。

これは、同じ広島神社にあった海難絵馬の一つの「白賀氏」のものだが、荷物の米俵を海の中に投げ捨てている。これを「跳ね荷」といい、「捨て荷」「荷打」とか言われて、船のバランスを保つために荷物を捨てることをいうらしい。白くなった部分の上側に米俵が山積みになっている。その海のほうには・・米俵が投げ込まれている図が見える。
ま、おおまかだけれど、海難絵馬には、こうしたものが見えてくるというお話だった。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね。