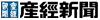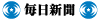免疫のブレーキ役発見、革新的がん治療に道筋 本庶佑氏にノーベル医学・生理学賞
ノーベル医学・生理学賞に輝いた京都大の本庶佑特別教授(76)は免疫を抑制するブレーキ役のタンパク質「PD−1」を発見し、免疫学の新たな地平を切り開いた。成果はがん治療薬として実用化し、革新的ながん免疫療法として世界から注目を集めている。
PD−1は、免疫の中心的な役割を果たすリンパ球の一種、T細胞の表面に存在するタンパク質。京大教授だった本庶氏の研究室で平成3(1991)年に発見されたもので、翌年に論文発表された。
その機能は当初、不明だったが、本庶氏は免疫の働きを抑制していることを実験で明らかにし、11年に発表した。遺伝子操作してPD−1を作れないようにしたマウスでは、免疫反応が強まり、自分の細胞を攻撃してしまう「自己免疫疾患」が起きたのだ。
T細胞は体内に侵入した病原菌などの異物を攻撃して殺す役割を持っている。一方、がん細胞は、自分自身の細胞が異常に増殖するように変化したものだ。このため、T細胞はがん細胞を攻撃できないと考えられていた。
ところが、1960年にノーベル医学・生理学賞を受賞した豪科学者が異説を唱えた。健康な人の体内でも1日に約3千個ものがん細胞が生まれる。それなのに、がんにならないのは免疫のおかげだとする説だ。
だとすれば、自分の細胞であるがん細胞が、どのように免疫の攻撃を受けるのか大きな謎だった。本庶氏は免疫を抑制するPD−1の仕組みを遮断すれば、T細胞が、がん細胞を攻撃できると考えた。
PD−1は活性化したT細胞の表面にある。体の細胞の表面にはPD−1と結合するタンパク質がある。PD−1を鍵に例えると、鍵穴に相当する物質だ。
両者が結合するとブレーキ信号が送られ、活性化していたT細胞が休眠状態に陥り、免疫攻撃が抑制されるのだ。本庶氏は米国との共同研究で2つの鍵穴物質を発見。この働きにより正常組織の細胞は免疫攻撃から守られていることを明らかにした。
さらに本庶氏は、重いがん患者で鍵穴物質が増えていることを見いだした。がん細胞はPD−1の機能をいわば悪用し、表面に鍵穴をたくさん作ることで、免疫を巧みにすり抜けていることを突き止めた。
PD−1や鍵穴物質にくっついて、両者の結合を妨げる抗体を投与すると、ブレーキ信号がなくなりT細胞が活性化され、がんの増殖や転移が抑制されることも確かめた。
これらの成果から、本庶氏はPD−1をがんの免疫療法に応用できると確信し、小野薬品工業(大阪)と共同研究を開始。開発されたがん治療薬「オプジーボ」が26年9月、同社から発売された。PD−1に結合する抗体薬で、ブレーキ信号をブロックする働きを持つ。がんだけを狙い撃ちできる可能性があり、副作用の頻度が少ないがん治療法として期待されている。